診療をしていると、休み明けなどはどうしても予約が集中します。結果として、どれだけ時間通りに進めようとしても、待たせてしまう患者さんが出ます。ある程度待たせれば、必ず「まだですか?」という声が受付に届きます。診察室に入ってからも、あからさまに態度が悪い人もいます。
「先生、この患者さん(カルテを指差して)結構待たされて怒っています。早くみてください。」
予約がパンパンに入っているからそうなるよね、って話で、現場としては努力はしていますが、しょーがないんです。それでいて診察したら、めちゃくちゃ不機嫌な人。います。初対面の人にこれだけ不機嫌でいる人ってなんなんでしょうか?正直器の小さい大人だなぁと思いながら、関わりたくないからもう来ないでほしいと思います。
そう、それはあまり得をしない行為です。徳も積まれませんし、周囲からは「自分のことしか考えない人」というレッテルを貼られるでしょう。そんな人に出くわすたび、私の胸には、言葉にしづらいやるせなさが広がります。
「俺の時間が」という理屈もわかります。時間は有限です。しかし、その有限の時間を何十人もの人間が同時に動かしているのです。時間とは、そもそも何なのでしょうか。
この記事はこんな方に向けて書いています
- 待ち時間や遅延に強いストレスを感じる方
- 日常の小さな苛立ちが大きな人間関係の摩擦につながっていると感じる方
- 「時間は有限」という言葉に少し息苦しさを感じる方
- 他者との関係性の中で「自分の時間」の価値を見直したい方
時間は「共有される資源」か「私有財産」か
私たちは時間をしばしば“個人の所有物”のように考えます。「俺の時間を奪うな」という言葉の裏には、時間をお金のように所有する感覚が潜んでいます。
しかし、病院の待合室に座る時間は、他の患者、医師、看護師、受付、すべての人間が絡み合う“共有の資源”です。自分一人の効率化を優先することは、往々にして他者の時間の浪費を伴います。
時間は錯覚であるという視点
物理学的にも哲学的にも、時間は絶対的な実体ではないとされます。
どういうことでしょうか???
人間が感じる1分は、状況や感情によって長くも短くもなります。
診察の待ち時間が長く感じられるのは、待つことへの不安や苛立ちが時間感覚を歪めるからです。逆に、会話や読書に没頭すれば、同じ待ち時間でも苦にならないことがあります。
「心の狭さ」は時間感覚を貧しくする
小さな遅れに過剰反応し、周囲を責める人は、結果的に自分の世界を狭めています。時間を自分の城壁の内側だけで守ろうとすると、他者との関係や偶然の出会い、余白の喜びを失います。
「一事が万事」と言いますが、この態度は日常のあらゆる場面で表れます。そして、本人は気づかぬうちに損をしているのです。
まとめ
時間は有限でありながら、同時に錯覚でもあります。その感覚をどう扱うかで、人生の豊かさは変わります。待ち時間を奪われたと憤る人は、実際には自分自身の心を奪っているのかもしれません。銭形刑事みたいなこと言うね。
診療の現場で出会うその小さな苛立ちは、私に「時間とは何か」を問いかけてきます。そして答えはいつも、「共有される資源としての時間を、もっと寛大に扱うこと」へと行き着くのです。
ということで、こちらの話を仏教でいうところの「我執」という言葉に注目してさらに深ぼってみました。

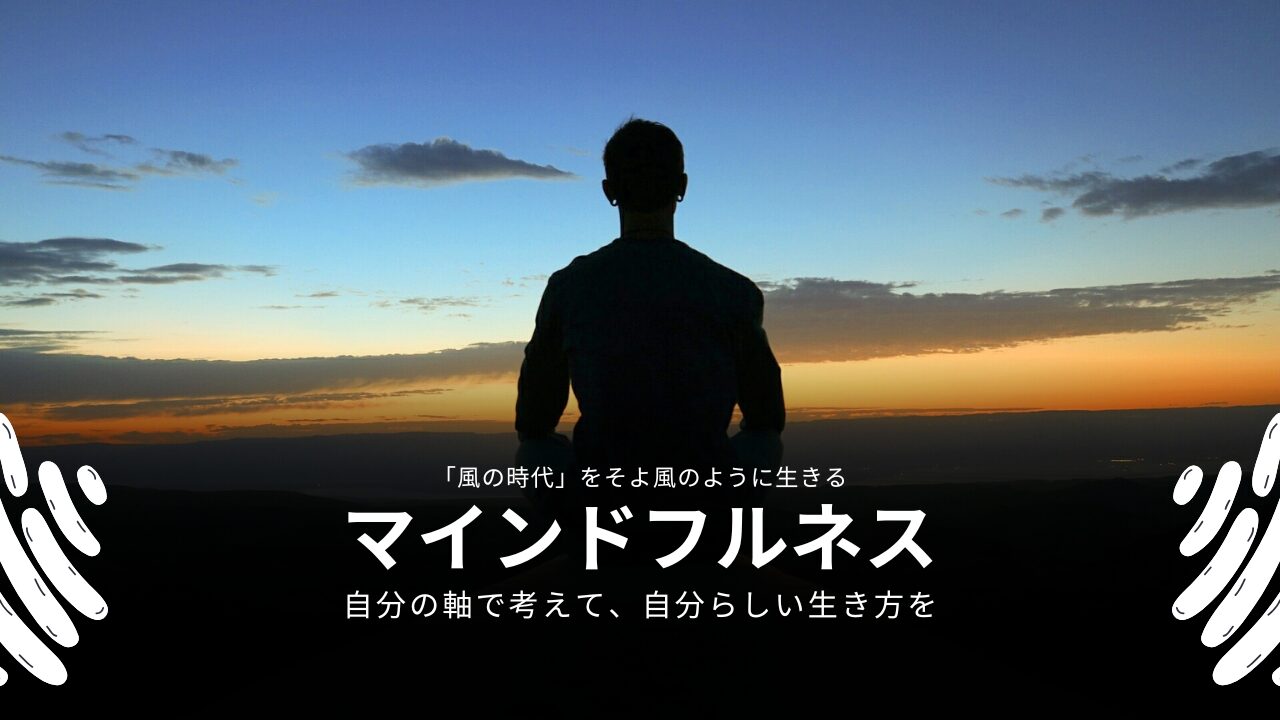


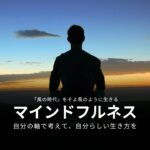
コメント