前回は、診察の待ち時間に関して不満を言う人の考えや、それに対する現場の思いや時間という概念に関する話をしました。前回の記事はこちら👉リンク
私は「時間は共有される資源であり、奪い奪われるものではない」という話をしました。
しかし診療の現場では、それでも待ち時間に苛立ち、態度を荒げる人はいます。
私は仏教徒でもないのですが、仏教の教えというのはやはり昔ながらの日本人的な思想があり、とても馴染みがいいのです。そこで調べていくと――この感覚は、仏教が言う「我執」にとても近いのではないかと。
本稿は医師としての臨床経験と仏教思想の知識をもとに執筆しています。宗教的解釈には諸説があるため、一次資料の確認を推奨します。
時間は誰のものでもない ― 無常の教え
仏教の根本にある「無常」の思想は、すべてが常に変化し続け、同じ瞬間は二度と訪れないことを示します。
時間は物のように所有できるものではなく、ただ流れ、移り変わる現象にすぎません。
にもかかわらず、「自分の時間が奪われた」と怒るのは、時間を私有財産と錯覚しているからです。無常を理解すれば、時間は「奪われる」ものではなく、ただ「過ぎゆく」だけだとわかるはずです。
待ち時間は縁起の現れ
診療の遅れには、無数の因果が絡み合っています。
他の患者の症状や急患対応、交通事情、スタッフの体調、機器の不調――これらが一つでも違えば、時間の流れは変わっていたでしょう。
仏教の「縁起」は、この相互依存の関係を説きます。待ち時間は、その網の目の中で自然に生じた現象であり、誰か一人の意志や怠慢だけで起こるものではありません。
我執が時間を狭くする
我執とは、「自分」という固定的な存在への執着です。
自分の都合、自分の予定、自分の不快感を中心に世界を評価する態度は、時間を極めて狭く、窮屈なものにします。
待たされることに怒る人は、結果的に「自分が守ろうとする時間」よりも「心の広さ」を失っているのです。仏教は、この我執こそが苦しみの根本だと説きます。
待つことを修行に変える
もし、待ち時間を「修行の場」として捉えることができたら――それは大きな転換になります。
坐禅のように呼吸を整え、今この瞬間を観察する。スマホではなく、自分の内側に目を向ける。
すると、時間は敵ではなく、むしろ師となります。そこには苛立ちも、奪われた感覚もなく、ただ「今」があるだけです。
まとめ
時間に縛られる人間は、「自分」と「自分の時間」という二重の鎖を自らにつけています。
仏教的な視点に立てば、無常を受け入れることで時間から解き放たれ、縁起を知ることで他者との関係が広がり、我執を手放すことで心は軽くなります。
前回の結論に、私はこう付け加えたいのです。
時間から解き放たれるとは、同時に“自分”からも解き放たれることだと。
難しくいってみましたが、、、
診察時間の待ち時間というのは、そこに予約を取っている(縁や因果のある人々が)たくさんいれば
その因果の中で、自然と優先順位が決まるもので、己の力ではどうにもできないものであると
自分の力でどうにもできないものに対して不満を抱き、さらにそれを表出して他者を巻き込む
これはさらに悪いこと。
本来は、待たせて申し訳なったと思う医療従事者の気持ちも興醒めさせてしまい
もうこの人とは関わりたくないという気持ちにさせているのです。
- Q仏教で「時間」はどう捉えられますか?
- A
無常として、絶え間なく変化する現象とされます。
- Q待ち時間の苛立ちはなぜ生じるのですか?
- A
時間を所有物とみなし、自分本位の感覚に固執するためです。
- Q縁起は待ち時間とどう関係しますか?
- A
遅れは多くの因果が相互に作用した結果であり、一人のせいではありません。
- Q我執を緩める方法は?
- A
呼吸法や瞑想で「自分」という感覚を相対化することです。
- Q待ち時間をポジティブに過ごすコツは?
- A
今この瞬間に意識を向け、観察や感謝の心を持つことです。
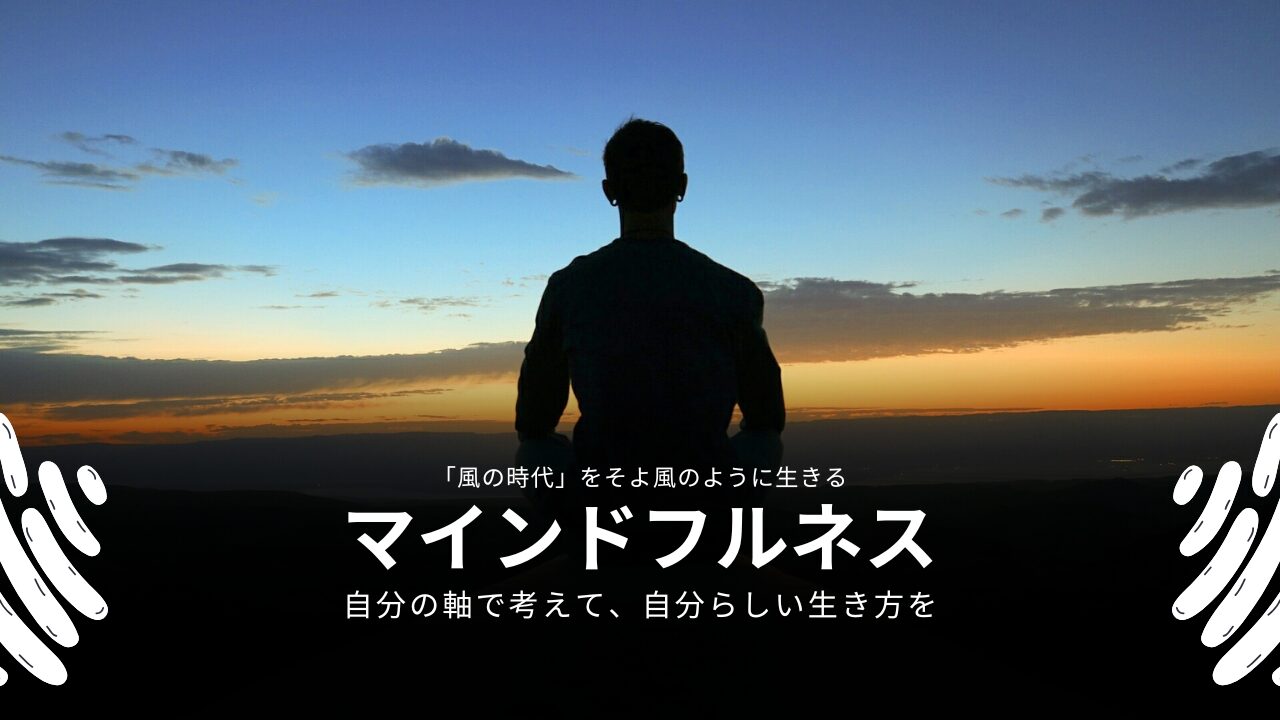

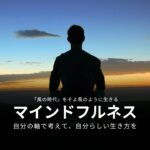
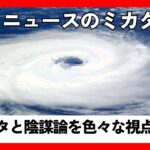
コメント