持ち家か賃貸か──かつては「どちらが得か」というライフプランの延長で語られてきたこの問いが、今や日本銀行の金融政策と資本主義社会の構造を問うテーマへと変貌しています。2023年以降、日銀は長らく続いたゼロ金利政策を転換し、利上げという新たなステージに突入しました。これまで「金利がない世界」では見えにくかったリスクが、住宅ローンや賃貸料といった日常的な支出にリアルに浮かび上がりつつあります。
さらに建設資材や人件費の高騰という構造的なコスト上昇が、住宅購入や賃貸生活のどちらにとっても避けがたい「重み」となっています。実際、建設会社の倒産は2025年上半期で過去最多水準に達し、住宅市場における供給側のひっ迫を物語っています。
どんな人に向けた記事か
・マイホーム購入を検討している人
・賃貸生活の将来に不安を感じている人
・住宅市場と経済の関係に興味がある人
・不動産投資に関心のある人
金利の復活と住宅ローンの重み
金利が上昇すれば、真っ先に影響を受けるのが住宅ローンです。特に変動金利で借りている人にとっては、月々の返済額が家計を直撃するリスクが高まります。かつては1%以下で借りられたお金が、今では2〜3%になる可能性が現実味を帯びています。
しかし、ローンの金利上昇よりも先に、すでに建築資材費や人件費の高騰が起きていました。ウッドショック、鉄鋼価格の上昇、物流コストの増大──これらの要因はすでに住宅価格に上乗せされており、そこに金利負担が加わるとなれば、持ち家購入のハードルはかつてない高さになっています。
建設コストの高騰と住宅価格への影響 📈
世界的には、建設資材や人件費の高騰により建設コストインフレは続いており、2024年には4.15%上昇、2025年も3.9〜4.0%程度の上昇が見込まれています。日本においても同様の傾向が強く、工事費・資材価格の上昇が住宅価格に直結している状況です。
東京圏では既存マンション価格が2025年1月に前年から7.8%上昇、一方で新築は3.3%下落という二極化も生じています。これは建設費や土地取得費の影響が色濃く、販売価格への転嫁が難しくなっているからです。
さらに注目すべきは、こうしたコスト高騰により中小の建設会社が相次いで倒産している現実です。2025年上半期には建設業倒産が986件に達し、前年同期比で7.5%増加。4年連続の増加で、上半期として過去10年で最多となりました。物価高を主要因とする倒産も118件(全体の約12%)にのぼり、住宅建設の供給基盤が脆弱化していることがうかがえます。
賃貸料の上昇と不動産投資の現実
「それなら賃貸でいいじゃないか」と思うかもしれません。たしかに、フレキシブルで、引っ越しもしやすく、ライフスタイルの変化にも対応しやすい賃貸は、流動性という意味でリスクが低いように見えます。しかし、その賃貸料もまた、建設コストと人件費の高騰、さらにはオーナー側の金利上昇に連動して上がり続けています。
不動産投資をしている貸し手側もまた、法人向け融資やアパートローンの金利上昇に苦しんでいます。加えて、空室リスク、修繕費、固定資産税などを考慮すると、賃料を下げる余地はほとんどありません。
一方で上げすぎれば入居者がつかず、投資として成り立たない。このジレンマは、不動産業界全体を覆う“見えない緊張”とも言えるでしょう。
人口減少というタイムボム
住宅を巡るもう一つの大きな構造的要因が、日本の人口減少です。今後10年、地方では空き家が急増し、賃貸需要も減少するでしょう。しかし、首都圏の駅近物件など、利便性の高いエリアでは依然として需要が集中し、家賃も高止まりする可能性があります。
この「場所による格差」は、賃貸でも持ち家でも避けて通れません。結果として、高所得層は便利で安全な場所に集中し、低所得層は不便な場所で暮らすという構図が固定化されつつあります。
まとめ
住宅を「買うか、借りるか」という選択は、もはや単なる経済的判断ではなく、日本社会の未来を見通す上でのリトマス試験紙のようなものです。利上げ、建設コストの上昇、人口減少、都市の集中──これらが複雑に絡み合い、正解のない問いを我々に突きつけています。
一つだけ確かなのは、「柔軟でいられること」がこれからの時代を生き抜く鍵(頭が柔軟という意味です)であるということ。選択肢を持ち続けられるよう、リスクを読み解くリテラシーを育てていきたいものです。
・・・・・・・・
こうして「家を持つ/持たない」の問いを深く掘り下げていくと、次に浮かび上がってくるのは、私たち一人ひとりの「経済的な現実」と向き合う必要性です。では、今の日本で家を買うということは、どれほどの覚悟とリスクを伴うのか──そして、そもそも家を持てるというのは、どういう立場の人なのか。次回は、建築費の高騰と日本人の所得停滞を背景に、「持ち家を持つことのリアルな重み」について掘り下げてみたいと思います。

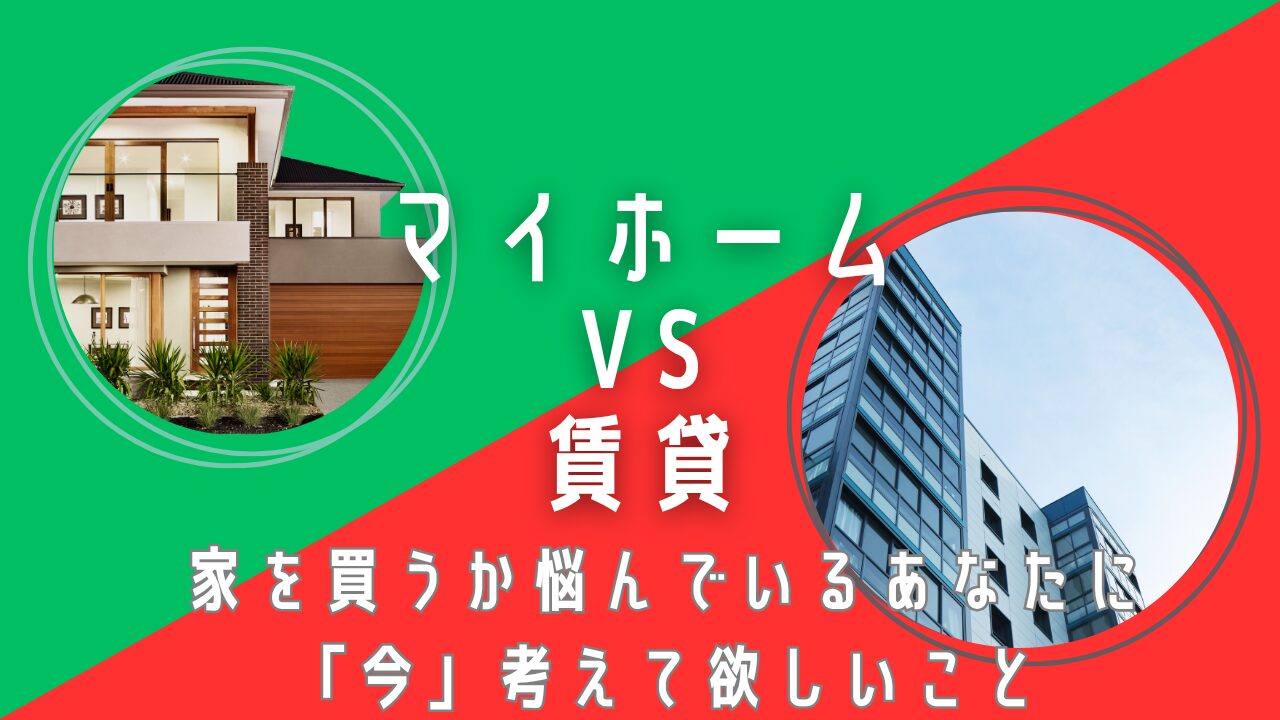

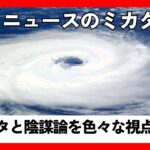

コメント