本質を考えたい医師です。
持ち家を持つということが、今や“夢”ではなく“重荷”になりつつあると感じたことはないでしょうか。特に首都圏で土地から家を買う、あるいは建売を購入するという選択肢は、もはや中間層にとって容易ではありません。コロナ禍を経て急騰した建築費、日本人の賃金停滞、そして政策金利の変化。これらが複雑に絡み合い、「家を買う」という行為にかつてないリスクと覚悟が求められています。
どんな人に向けた記事か
・これから住宅購入を検討している人
・家を買うことに迷いを感じている人
・経済と不動産市場の関係に興味がある人
・格差社会に疑問を持つ人
建築費は上がり続け、賃金は上がらない
日本人の平均給与は、ここ30年間ほとんど上がっていません。厚労省の「賃金構造基本統計調査」によれば、1990年代から日本人の実質賃金は横ばい、あるいは下落傾向さえあります。一方で、建築費は2020年代に入って急上昇しました。
2024年の建設コストインフレ率は4.15%、2025年も約4%前後で推移する見込みとされており(JLL調査)、もはや一般家庭が無理なく住宅を持つという構図が成り立たなくなってきています。特に首都圏で「土地付き注文住宅」を建てるとなれば、土地代だけで数千万円。そこに建築費が加わると、住宅ローンの返済が家計を圧迫するのは避けられません。
建築現場に潜む“見えないコスト削減”の罠
建設会社にとっても、これ以上価格を上げると顧客がつかないという現実があります。結果として、人件費の削減、資材のグレードダウンといった「顧客に見えないコスト削減」が横行するリスクも高まります。
丁寧に施工してくれる業者もいますが、価格競争に晒された現場では手抜き工事が起こる可能性も否定できません。消費者は「価格が高い=品質が高い」と信じがちですが、実際にはその内訳を慎重に見極める力が求められています。
資産形成か、人生の足かせか──住宅ローンという名の賭け
住宅ローンは単なる借金ではなく、国の信用創造の一翼を担っています。つまり、国民が家を買うことで、銀行が貸し出し、経済が回るという仕組みの一部です。
しかしその信用創造は、家計にとっては「未来への投資」か「過剰な負債」かの境界線上にあります。物価上昇と株価上昇により、資産を持つ者と持たざる者の格差はさらに拡大しつつあります。家を買える層と、賃貸すら困難な層に分かれつつあるのです。
「適正価格」での購入という決断
私は2023年、思い切って注文住宅を建てました。コロナ禍の中で投資を始め、日経平均が2万円台から4万円に至る推移を眺めながら、住宅価格もまた「下がる」よりも「上がる」可能性の方が高いと感じていました。
確かに、人口減少による需給の緩和、空き家問題も視野にはありますが、信用創造の仕組みが変わらない限り、住宅価格が劇的に下がることは想定しにくいとも考えました。
僕の偏った思考では「建売住宅の性能はブラックボックス」だと思っています。価格を抑えることの皺寄せが建築会社か消費者のどちらかに来ます。それで普通に考えたら消費者にくる可能性が圧倒的に高いはずです。
であれば、少なくとも「今この時点での適正価格」を考えた時に「信頼のおける建築会社、工務店に注文住宅をお願いする」ことが、自分にとって納得のいく家を建てることであり、「お金の持っている価値を最大限に引き出せる」最良の選択肢なのではないか──そう判断したのです。
この判断が長期的に見て正解だったかはわかりません。ただ一つ確信しているのは、「情報と構造を読み解いたうえで決断した」ということ。その過程こそが、今の時代を生き抜くための知恵ではないでしょうか。そして自分で熟考した上での決断でなので、たとえそれが少し思い描いていたものと違っていてもそれは「自分の人生は自分で責任をとる」という観点で重要なプロセスだったと思います。
まとめ
「家を持つ」という行為は、今や人生をかけた経済的・社会的な選択となっています。建築費の高騰、所得の停滞、そして格差の拡大。その中で、どのように選択し、何に納得して生きていくのか。
大切なのは、将来の“正解”を予測することよりも、“今”の選択に対して誠実であること。その姿勢が、次の時代を形作るヒントになるのかもしれません。
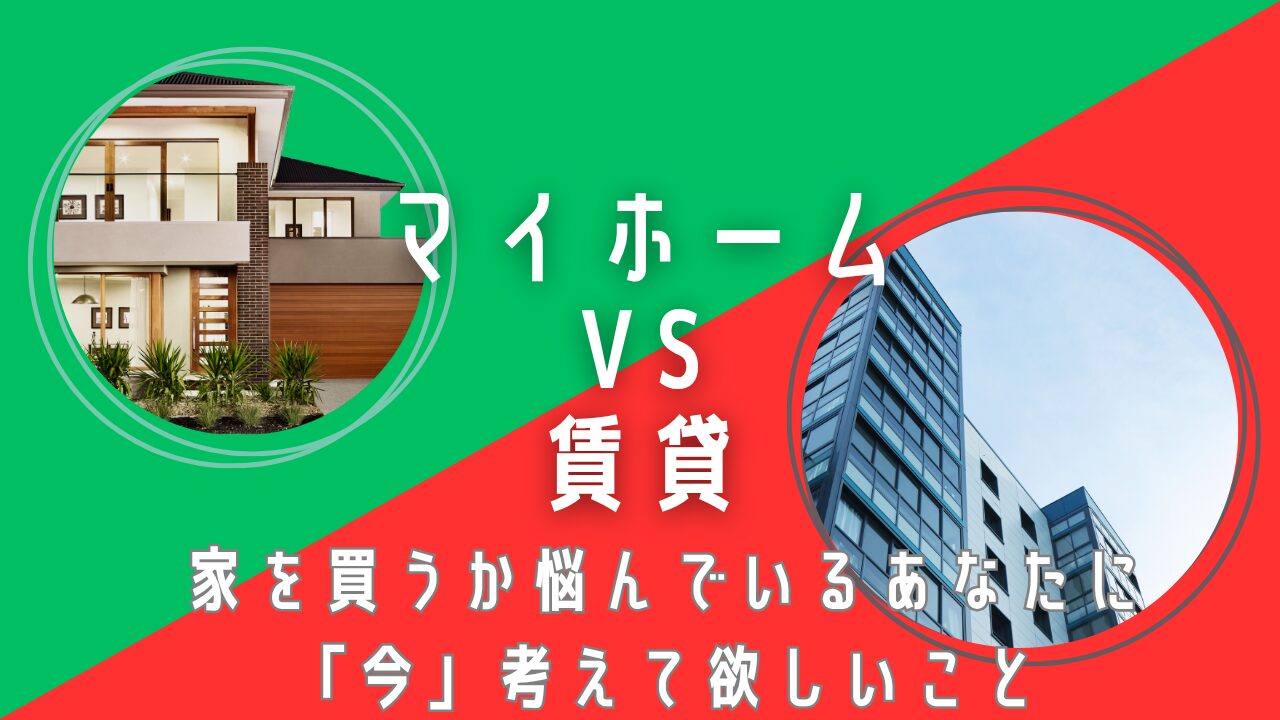


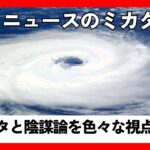
コメント