2025年の「トランプ関税ショック」で株価が急落した際、
多くの個人投資家が大きな不安に襲われました。
特に新NISAが始まり、
投資をスタートしたばかりの20代~30代の若い世代にとっては、
初めて経験する大きな下落だったのではないでしょうか。
実際、短期的な恐怖から損切りをして口座を解約してしまった人も少なくないといわれます。
しかし、長期投資を前提にNISAを活用するのであれば、
このような下落局面こそ冷静な判断が求められます。
自分はどうしたか?
自分は2024年の夏に日本版ブラックマンデーとも呼ばれる
大暴落時にほとんど何もできませんでした
その時の反省を活かして
かといってなんの根拠もないわけではなく
それでも恐怖を感じながらも
リスク許容度の範囲内で買い増ししました。
相場に残ることが一番大事という格言があるように
今回の暴落を経験して
恐怖に打ち勝つ
知識と信念を持つことが最も大事です
半年経った今、
そろそろ暴落が来るとまた言われ始めましたが
それに備えて
トランプ関税ショックに関して
振り返ってみましょう。
1. ニュースと実体経済の「タイムラグ」を理解する
私が今回の急落で少しずつ買い増しできた大前提は
**「トランプ関税は交渉カードである」**と考えていたからです。
株をやっていれば長期投資家であっても
世界の出来事、ニュース
そしてそれの本当の意味をしっかりと把握し
さらには解釈することが重要です
ここで大事なのは、
- 株価はニュースに即反応するが、実体経済への影響は後から出てくる
- 政治的な発言はマーケットの交渉材料として使われることが多い
という2点です。
今回の急落は、実体経済が本当に悪化したわけではなく
「市場心理」のショックが中心でした。
したがって、実体経済に決定的なダメージが出る前に株価は回復する可能性が高いと判断しました。
そして、株価が回復した今、
そろそろ暴落が来ると言われているのは
実体経済の指数が少しづつではありますが
雲行きが怪しくなっているからです
2. 若い世代が陥りやすい「恐怖による損切り」
新NISAで投資を始めたばかりの20代が、
今回の下落で恐怖に駆られて損切りしてしまったという話を耳にしました。
しかし、このタイミングで解約してしまうことは非常にもったいない行動です。
- 株価は「行き過ぎる」ことが多く、暴落後に反発することも多い
- 特に若い世代は時間という最大の武器を持っている
- 下落局面は、むしろ安く株を買えるチャンス
短期的な恐怖で長期資産形成の芽を摘んでしまうのは、最も避けたいパターンです。
株式投資を始めるのならば
自分の手法と目的をしっかりと見据えた上で行うべきでしょう。
NISAで投資を始めた理由はなんでしょうか?
長期投資ならば老後の資産形成ではないでしょうか
であれば若い人ほど
解約という行動は取るべきではないと思います
3. SBI証券の単元未満株を活用する
「わかっていても一度に大きく買うのは怖い」
という心理は誰にでもあります。
私自身も今回、少しずつ段階的に買い増ししました。
その際に役立ったのが、**SBI証券の単元未満株(S株)**です。
- 100株単位ではなく1株から買えるので、資金効率が良い
- 急落局面でも少額でエントリーできる
恐怖心を和らげつつ、安値で仕込むことができる優れた手段です。
僕自身は今回の暴落時は日本の高配当株を買い増ししました。
日本の高配当株は通常単元ずつ(100株ずつ)の購入となります。
例え暴落の際に、普段より狙っていた株があったとて
1株1万円なら100万円必要です。。。
暴落時に1社に100万も注ぎ込める庶民はそうそういません。
そういったリスクを分散する意味合いでも
単元未満株で購入できるSBI証券は
控えめにいって「神」なんでしょう
4. 私が買い増しできた2つの理由
今回の暴落で買い増しができた背景には、次の2つがあります。
- 経験
2020年以降、ブラックマンデー級の急落も経験してきたことで、下落への耐性ができていた。
「下がっても必ず戻る」という相場のサイクルを理解していた。 - ニュースの本質を見抜く視点
トランプ関税が本質的には交渉カードであり、いずれは下げられると予想。
そのため、過剰反応した株価は**「バーゲンセール」**と判断できた。
大体のニュースは短期的な株価の上下を狙ったり
短期的な上げ下げに対する後出しジャンケン的な
内容だったりします。
ですので、ニュースにはあまり振り回されないことが大事です
下がっても必ず戻る、というのは
まだ経済がコテンパンに破壊されていないからです。
5. 実体経済と株価のズレを味方にする
株価はしばしば実体経済と乖離して動きます。
今回も、実体経済が悪化する前に株価が下がり、
悪化が表面化する前に株価は回復する可能性があります。
重要なのは、タイムラグを理解して行動することです。
- 短期的なニュース → 株価は即反応(過剰反応しがち)
- 実体経済の影響 → 後からじわじわ出る
このズレを冷静に観察できれば、
短期的な暴落に動じず、
むしろ資産形成のチャンスに変えられます。
まとめ
- 暴落局面では恐怖に支配されず、「何が実体経済に影響するのか」を見極める
- 若い投資家は下落を「資産形成の入口」として活かすべき
- SBI証券の単元未満株などを活用して、少額から買い増しする戦略が有効
- 経験と知識が、暴落時の冷静な判断を支える
新NISAは長期投資のための制度です。
目先の暴落に左右されず、
腰を据えて投資を続けることが、
最終的には大きなリターンを生みます。



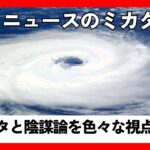
コメント