投資の世界に身を置いていると、「陰謀論なんて非合理だ」「データとファンダメンタルだけを信じろ」といった言葉をよく耳にします。確かに、感情や空想に基づいた取引は、大きな損失を招くリスクがあります。
けれども、逆に問いたいのです。なぜそこまで「陰謀論を排除せよ」という言説が支配的なのか。その背後には、意図的に思考の幅を制限しようとする力が働いているように思えてなりません。私たちは、世界の動きを「市場原理」や「需給バランス」だけで説明しようとしていないでしょうか。
「陰謀」とは、他者の意図に思いを巡らせること。そして「投資」とは、その意図を先読みする行為。ならばこの二つは、本来分けられるべきものではなく、むしろ“混ぜて考えるべき”なのではないでしょうか。
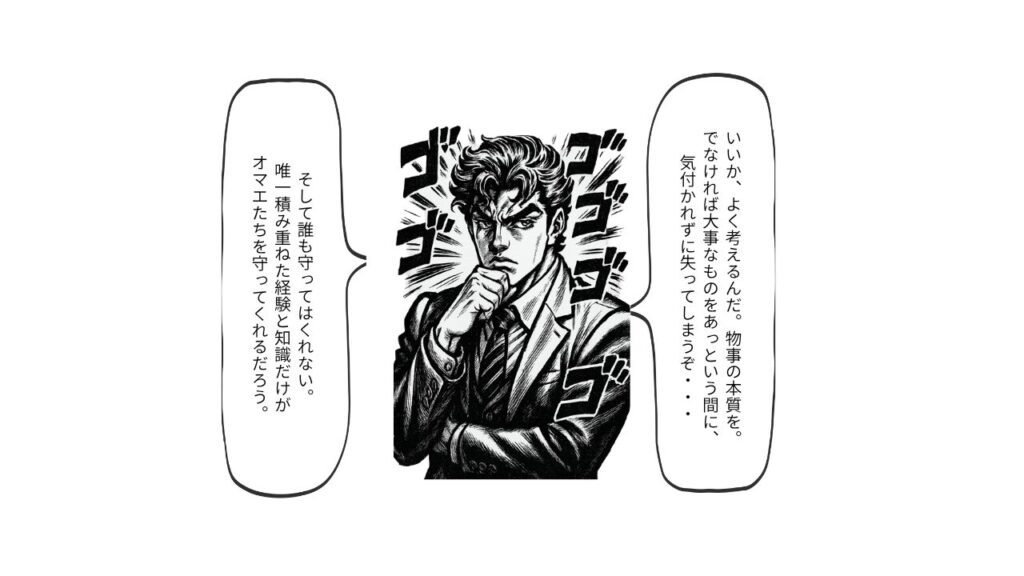
この記事はこんな方に向けています
- 投資や経済に興味を持ちつつ、メディアや政府の発信に違和感を覚えている方
- 「陰謀論=悪」とされる風潮に疑問を抱いている方
- より深い視点から世界と市場の関係性を理解したい方
投資は意図の読み合い

私たちはつい、チャートや数値の変化ばかりに目を奪われがちです。ですが、株価や金利の背後には「誰かの決定」が必ず存在します。利上げを決める中央銀行、戦争に踏み切る国家、買収を仕掛ける企業。それらの動きには明確な「意図」があります。
つまり、投資とは偶然の積み重ねではなく、意図の読み合いです。そして意図の先には、得をする者と損をする者が生まれる構造がある。そこには時に、不正義や不平等、そして「陰謀的なもの」が介在します。
「陰謀論」というラベルがもたらす思考停止

「それって陰謀論じゃないの?」という一言で、あらゆる思考が封じられる光景をよく見かけます。この言葉は、まるで「陰謀」という概念をタブー化し、人々に“考えさせないための装置”として機能しているように感じます。
冷静に考えてみましょう。金融危機や戦争、ウイルスの拡散、メディア統制など、歴史をひもとけば“偶然の一致”にしては腑に落ちない出来事が数多くあります。そうした出来事を「なぜそうなったのか」と疑い、構造や背景を探る姿勢は、投資家にとってむしろ必要な視点です。
リーマン・ショックと「選別された破綻」

2008年のリーマン・ショックでは、なぜリーマン・ブラザーズだけが救済されなかったのか?
政府とFRBの動きに意図はなかったのか?
そしてその破綻後、利益を得た者たちは誰だったのか?
こうした問いを封じるのは簡単です。「それは陰謀論だ」と切り捨てればよい。しかし、それを真剣に考えることが、次の危機から身を守る「生きたリテラシー」となりうるのです。
混ぜることで見えてくる「もう一つの世界」

私は、「投資」と「陰謀論(的視点)」を混ぜることを、冷静に推奨します。それは妄想に溺れることではなく、「世界には語られざる意図がある」という前提に立ち、複数の視点から構造を読むということ。
数字を信じることと、意図を読むこと。両者をバランスよく携えてこそ、変動する時代を生き抜く投資家たりえるのではないでしょうか。と偉そうに初心者ながら思うのです。
でも実際に自分が行なっているのは「インデックス投資」と「日本の高配当株」のみです。投機的な投資や、短期投資、仮想通貨など一般的に「リスクの高い」ものは避けています。ですので「陰謀論的視点」は自分の投資手法とはあまり関係はありません。それでも、世の中を見る目というのは常に磨いておいて損はしないと思うわけです。
まとめ
「投資と陰謀論を混ぜるな」という警句には、一理あります。確かに、無根拠な噂に踊らされるのは危険です。しかし、完全に分離してしまうのもまた、同じくらい危うい行為です。
私たちが生きているこの社会は、数字と意図、構造と偶然、光と影が複雑に絡み合った世界です。「混ぜなきゃ危険」とは、表面と裏面を同時に見るための、ひとつの哲学です。
「信じすぎず、疑いすぎず」──このバランス感覚こそが、今後のリテラシーの鍵となるのだと思います。




コメント