インフレは静かに私たちの生活を蝕みます。パンの値段が上がり、光熱費が上がり、預金の価値が少しずつ目減りする。気がつけば「100万円」が「実質的には60万円程度」の力しか持たなくなる――これがインフレの正体です。では、この時代をどう生き抜くのか。円という幻想を超えて、資産と生活を守る戦略が求められています。
100年前は今でいう50万円ほどの購買力のあった100円を、100年握りしめて「いざ、今使おう」と思っても、どうですか??このメチャクチャ暑い夏にアイスも買えないです。ガリガリくんを除く。

誰に向けた記事か
- 円預金しかしていない人
- インフレ時代に漠然とした不安を抱く人
- 資産を守りたいけれど、投資が怖い人
- 医師や専門職など忙しくても対策を考えたい人
通貨リスクを分散する
円だけに依存するのは一点集中投資です。円が沈めば一緒に沈みます。だからこそ分散が必要です。
- 株式:企業の成長は物価上昇を超える力を持ちます。特に世界市場で稼ぐ企業は強い。
- 外貨建て資産:ドルやユーロを一部持つことで、円安リスクを和らげられる。
- 金(ゴールド):利息は生みませんが、通貨の信認が揺らぐときに最後の避難所となる。
注意したいのは、「外貨建て」というワード。これだけが頭の片隅に残っていると「外貨建て保険」と言われるような「資産を減らす」商品に引っかかってしまう可能性があります。間違ってもそういったものには手を出さないように。ネット証券を通じて購入するSP500のインデックス投資も立派な「外貨建て資産」です。すでに持っている人も多いのではないでしょうか。
仕組みを理解しましょう。仕組みを。

生活基盤を守る
インフレは必需品から直撃します。守るべきは生活の基盤です。
- 住居:固定金利の住宅は「家賃インフレ」を防ぐ盾になる。
- エネルギー・食料:小さな自給や共同購入は、インフレに揺らがない生活を支える。
住宅ローンで住宅を購入することには精神的な負担も大きく、これ自体を推奨するわけではありません。理論的に、家賃もインフレが進む世界では、固定金利で住宅購入をする方が住居費は安く抑えられる可能性があるという程度の話です。賃貸は流動性があるため、その都度収入に応じて借り換えるなど、リスクを分散できます。そのためのコストと考えることもできるので、ここら辺はライフプランに応じて柔軟に考える必要があります。

小さな自給や共同購入??
これは家庭菜園などの無理ない範囲で可能な時給であったり、そこから作る保存食であったり、「生活のちえ」と呼ばれるような範囲での活動をイメージしてください。
また共同購入とは、生協などの活用です。
我々は「生協」でお米のサブスクをしています。幸い米価格が高騰する前でした。市場価格の高騰前は市場より若干高価ではあったのですが、現在は市場価格の方が高いです。これは独自の流通経路を確保していることで流通コストを削減できているためです。「直売所」などの積極的な活用もこういったものに含まれます。モロヘイヤなどもスーパーでは400円、直売所では100円だなんてこともよくありますよ。
所得を多層化する
労働所得だけではインフレに追いつけません。複数の収入源が必要です。
- 副業・スキル投資:専門職でもデジタルスキルや副収入を持つことが防衛策になる。
- 配当所得・家賃収入:資産からの収益は、インフレに連動して伸びやすい。
最も大事なのは「自分で稼ぐ力」です。知識をつけ、自己投資することでインフレに対応できる能力を着実に身につけることができるでしょう。本業以外の副業で知識や能力に幅を持たせておくというのもリスク分散になります。
株式などの配当所得もインフレに応じて上昇する傾向が強いです。むしろここ何年かの株式市場を見ているとインフレの前から株式は上昇を始めていました。このように株式のような資本家の資金が集中する「場」に参加することが非常に大事なことになります。「株式投資はギャンブルですよね」という考えは改めた方が良い時代です。

教育と共同体への投資
お金より強い資産があります。それは「人」と「つながり」です。
- 教育:知識や技術はインフレに奪われない。自分と子どもへの投資は最大の資産防衛。
- 共同体:市場で買えない助け合いこそ、社会が不安定化するときの支えとなる。
知識や技術はインフレに奪われない。に関連して現在世界の金融を牛耳るユダヤの勢力は、知識こそ財産だという教育を受けると聞きます。現在の世界の構造を理解するとこれがいかに真実であったのかを痛感します。彼らは、知識こそ真の財産と捉え、家庭でも学校でも徹底して教育に投資してきました。タルムード(ユダヤの律法解釈書)には「父は子に知識を授ける義務がある」と説かれています。

まとめ
インフレは避けられません。けれど「舐めなければ」備えることはできます。円にしがみつくのではなく、世界に広げる。消費を減らすのではなく、基盤を固める。孤立するのではなく、学びと共同体に投資する。これが、インフレ時代をサバイブする本質的な戦略です。
書いていて思ったのは、これからの時代は変わらないことと変わっていくことの差が激しいと思います。変わっていくことの中に収入を増やす「仕掛け」が潜んでいると思います。常にアンテナを張る、そんなことが大事ではないでしょうか。そのためにはまずは、知識と行動です。
いち早く、知識を利用して、この世界の仕組みを作り上げてきたのはユダヤの勢力です。彼らを羨んでるだけでは何も変わりません。我々も彼らを見習っていくべきでしょう。
そこで次は、「ユダヤ的教育観とインフレ時代の日本」という切り口で考えてみたいと思います。これからの時代を生き抜くヒントが隠されているかもしれません。

FAQ

Q1: インフレ時代に円預金は安全ですか?
A1: インフレ下では円の購買力が下がるため、円預金は実質的に目減りします。
Q2: インフレ対策に有効な資産は何ですか?
A2: 株式、外貨建て資産、ゴールドなど分散投資が有効です。
Q3: 生活防衛で大切なポイントは?
A3: 住居費や食費など固定費を守り、自給や共同購入などの工夫が効果的です。
Q4: 所得を増やすにはどうすればよいですか?
A4: 労働所得に加え、副業や配当所得、家賃収入など複数の収入源を持つことが重要です。
Q5: インフレ時代に教育や共同体がなぜ大事なのですか?
A5: 知識やスキルは価値を失わず、共同体は市場に代わるセーフティネットとなるからです。
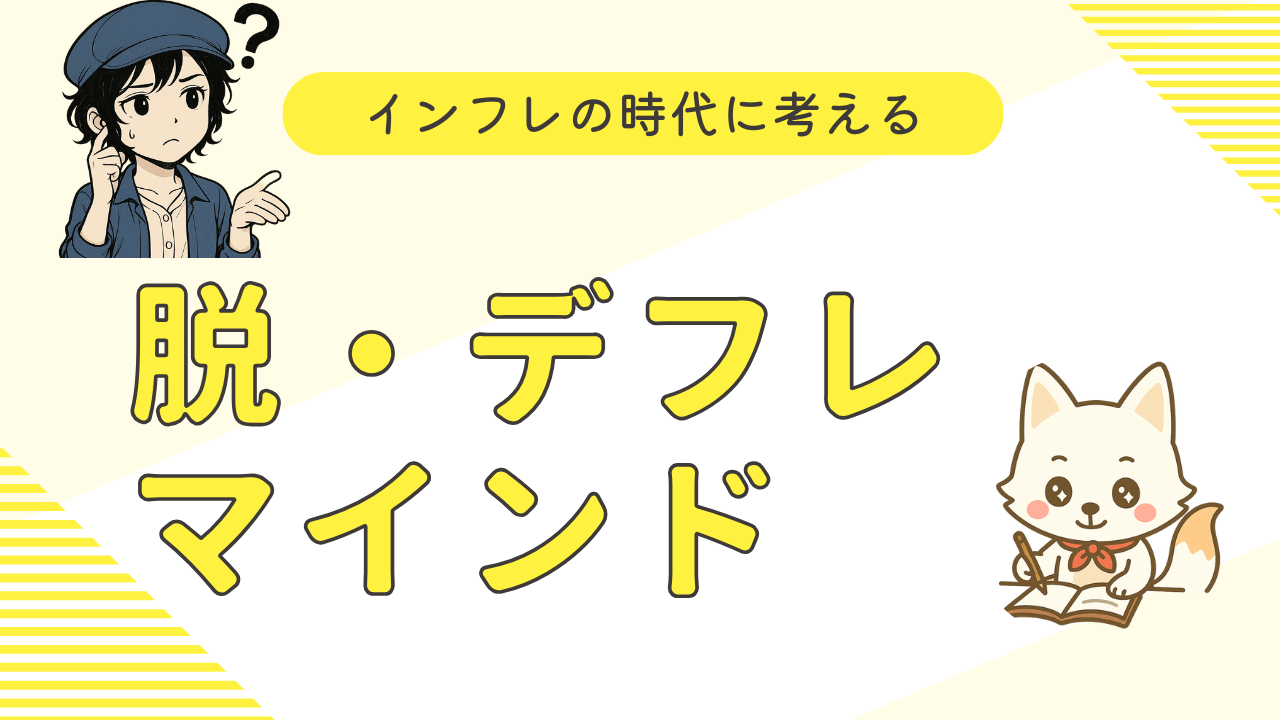

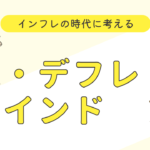
コメント