2025年8月1日、大統領であったドナルド・トランプ氏は、7月に発表された雇用統計の内容とそれ以前2ヶ月分(5月・6月)の大幅な下方修正を受けて、雇用統計を作成する米国労働統計局(BLS)の長、エリカ・マクエンターファー氏を解任しました AP Newsニューヨーク・ポストThe Washington PostBusiness Insiderマーケットウォッチ
アメリカの雇用統計が発表されるたびに、マーケットは一斉に息を呑みます。金利政策、株価、ドル相場──あらゆる指標がその数値ひとつで揺れ動く。だが、その数字に疑念を抱いたことはないだろうか?
直近の雇用統計の「ミス」に対して、「これは意図的だったのではないか」と考える人々が多く見受けられました。確かに、その修正は数ヶ月後にしれっと行われることも珍しくない。そして、こういった微細な「修正」すらも、実は巨大な意図の中で機能しているのではないか──そんな問いが、私の中で静かに膨らんでいます。
この記事はこんな人におすすめです
- マクロ経済や金融政策の背景に興味がある方
- 政治と経済の繋がりに疑問を感じている方
- アメリカの金利政策やFRBの動向を追っている投資家
- 統計やメディア情報の「裏」にある意図を考察したい方
数字は中立ではない──「統計」が語る物語
「数字は嘘をつかない。ただし、嘘つきは数字を使う」──この言葉の重みが、最近の雇用統計を巡る報道を通じて、改めて実感されます。統計とは本来、客観的な事実を提示するもののはずですが、その“タイミング”や“構成”、さらには“解釈”によって、大きく印象を変えることができます。
特に、中央銀行が利下げの是非を議論している状況下で、雇用統計がどのように発表されるかは、金融市場にとってきわめて重要です。雇用が堅調に見えれば金利は据え置き、悪化すれば利下げの正当性が生まれる。ここに、トランプ政権時代から続く「政策金利を巡る政治」と「反トランプ勢力としてのFRB」の対立構造が見え隠れします。
なぜ「誤差」は数ヶ月後に修正されるのか?
アメリカの雇用統計では、速報値が毎月第一金曜日に発表され、その後、1ヶ月後と2ヶ月後に「修正」が入るのが通例です。この修正、実は大きな意味を持っています。なぜなら、マーケットの反応は速報値に強く引っ張られ、修正値は多くの場合、注目されないからです。
つまり、最初の数値は“印象操作”に近い力を持ち、その後の修正で帳尻を合わせればいいという考え方が成立してしまう。意図的に行っているという証拠はないにせよ、「意図を疑われても仕方のない構造」であることは否定できません。
誰が統計をコントロールしているのか?
統計を操作することで何が得られるのか。考えるまでもなく、「政策的正当性」と「市場の誘導」です。FRBが金利を維持したいと考えているならば、雇用統計は強めに見せた方が都合がいい。逆に政権側が景気対策として利下げを望むならば、統計が“悪化”していた方が筋が通る。
そしてこの統計の裏には、FRB、労働省、政権、そしてその背後にいる金融ロビイストたちの影がある。誰かが明確に命令を出しているとは限りませんが、システム全体として、「誰かの意図に沿うように動く構造」が出来上がっている可能性は否めません。
まとめ──数字を鵜呑みにせず、構造を見抜く目を
雇用統計に限らず、あらゆる「統計」は、現代社会において一種の「言語」です。そしてその言語は、しばしば誰かの“意図”によって編まれた物語であることを忘れてはなりません。表層の数字に踊らされるのではなく、その裏にある構造を読み解くこと。これこそが、現代を生きる私たちに求められるリテラシーなのではないでしょうか。
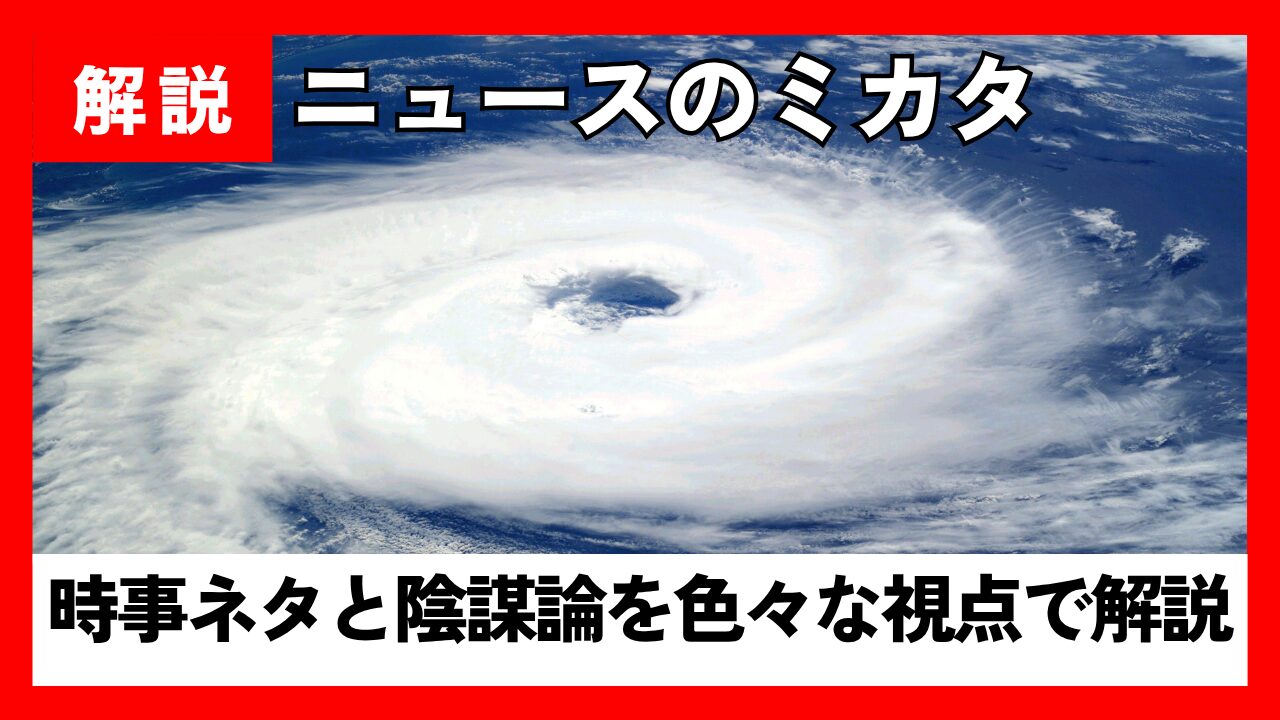

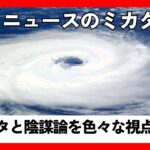

コメント