昨年から、株式市場はいくつかの暴落を経験しました。しかし、それらはすべて驚くほど短期間で回復しています。かつてのアノマリー、つまり「暴落=長期低迷」という経験則は、もはや通用しなくなっているのです。
背景には、世界の仕組みそのものの歪みが加速している現実があります。経済学で言われる「r > g」(資本収益率が経済成長率を上回る構造)も、かつてないほどの広がりを見せています。その結果、株式市場と庶民の給与や生活は、別々の世界線を歩むようになりました。市場は短期マネーゲームの舞台と化し、暴落してもすぐに回復する──そんな時代に、私たちは生きています。
どんな人に向けた記事か
- 株価と実体経済の乖離に疑問を感じている人
- 金融政策や国際金融機関の動きに関心がある人
- リーマンショック以降の市場構造の変化を知りたい人
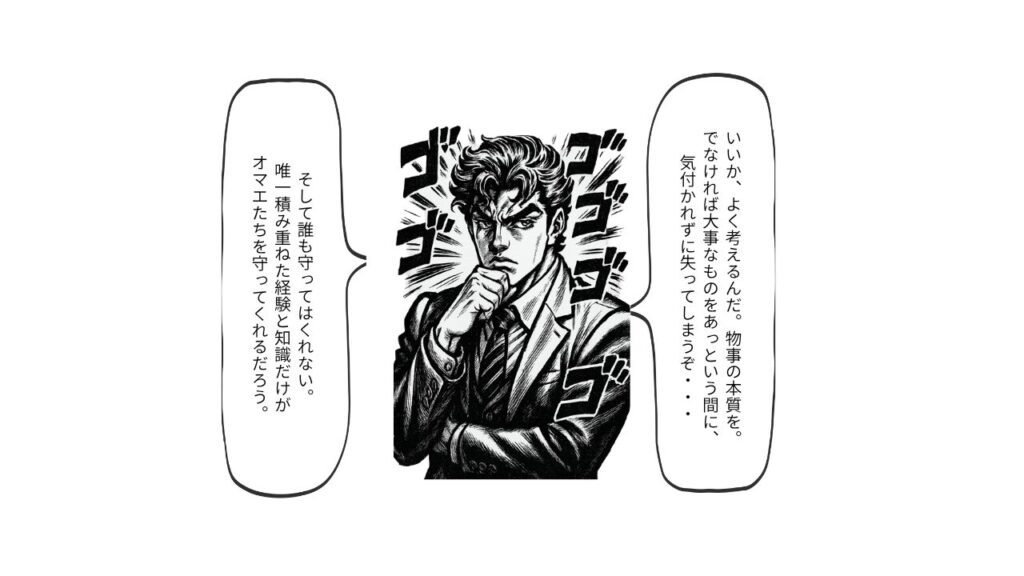
1. 暴落が長引かない時代
ここ数年、S&P500や日経平均は急落しても数週間〜数ヶ月で元の水準を取り戻しています。以前のように数年単位での回復を待つ必要はなくなりました。
その理由の一つは、各国政府と中央銀行、そして国際金融機関が、かつてないスピードで市場を支えるようになったことです。金利の即時調整、資産買い入れ、流動性供給──これらは下落を“即座に”反転させます。
2. r > g の拡大と市場の分離
トマ・ピケティの「r > g」は、今やさらに極端になっています。資本を持つ人々は株式や不動産の値上がりで富を増やし、賃金で生活する人々はその波に乗れません。株式市場の回復は資本家の現実であり、庶民の家計には反映されない。この二重構造が固定化されつつあります。
3. リーマンショックからの学び──そして反省
2008年のリーマンショックでは、世界は長い低迷期に入りました。社会不安と政治不安が重なり、各国は経済立て直しに苦しみました。
その経験を経て、国際金融機関は「次に大規模な下落が起きたら、ためらわず市場を下支えする」という暗黙の方針を持ったように見えます。結果として、市場は長期的な健全性よりも、短期的な価格安定を優先する構造に変わったのです。
まとめ
短期的な安心感の裏で、長期的な構造的格差が広がっています。株式市場は実体経済を映す鏡ではなくなり、巨大な短期資金の遊技場と化しています。
暴落が暴落でなくなる世界線は、見方によっては安定の時代とも言えますが、それは同時に「庶民と市場が切り離された時代」でもあるのです。
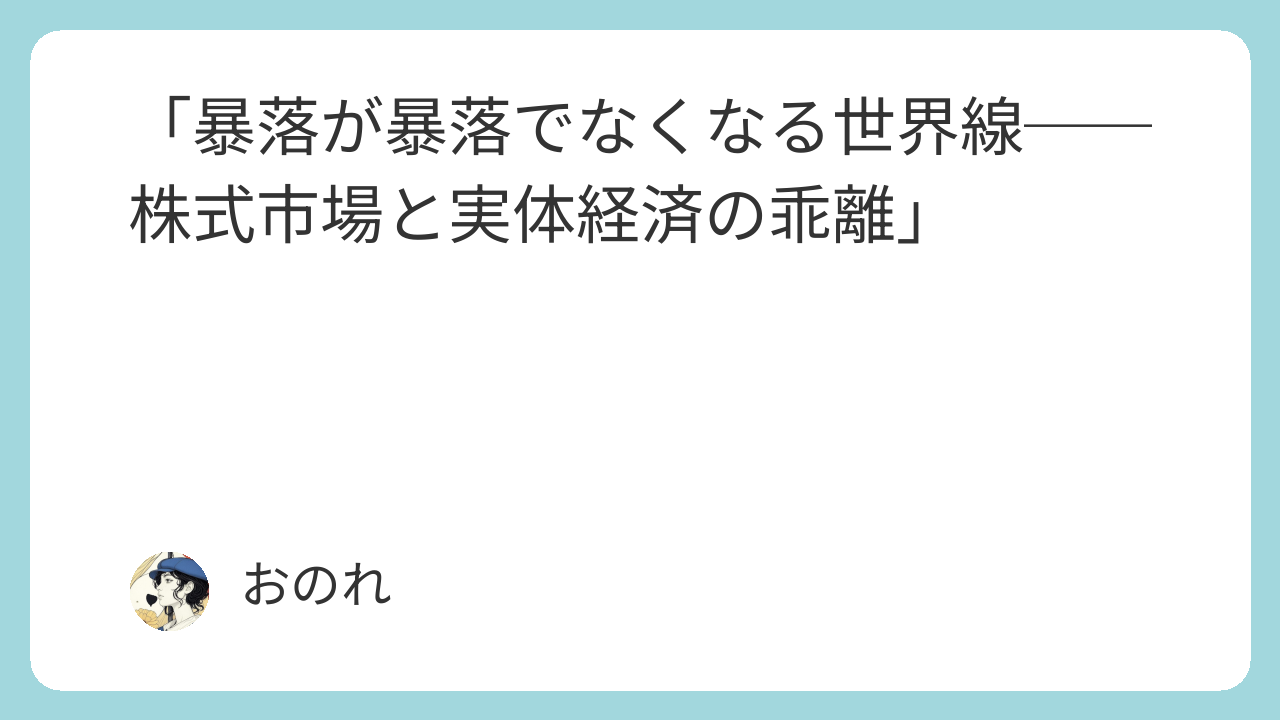

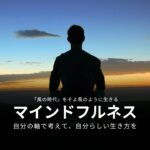

コメント