本質を考える医師です
SDGsに関する記事の後編です。こういった世界の潮流から日本は常にワンテンポ遅れているような気がします。慎重な姿勢とも取れますし、グローバリズムの最後の砦とする味方もできます。どちらですかね?後者ですかね。
前編はこちら⬇️
SDGs関連株と投資の動向
SDGsやESG投資をめぐる動きは、国内外で異なる傾向が見られます。
海外の動向
- ESGの後退:米国では、2023年にカンザス州でESG要因の考慮を制限する法律が成立するなど、「反ESG」の動きが広がっています。ESGファンドのリターンが期待を下回り、投資家の撤退も報告されています。
- 欧州の慎重姿勢:欧州はESG投資の先進地域ですが、グリーンウォッシュ批判や高コスト問題から、投資家が現実的なアプローチを求める傾向にあります。
日本の状況
- 政策の推進:日本では政府や経団連がSDGsやカーボンニュートラルを強く推進。2050年カーボンニュートラル宣言や「GX経済移行債」など、産業振興を目的とした政策が目立ちます。
- 投資の過熱:再生可能エネルギーや電気自動車関連株への注目が高まる一方、海外ファンドが撤退する中、日本が「最後の買い手」となるリスクも指摘されています。
- 国会での議論:SDGs関連企業への投資や支援が議題に上るものの、多くは技術開発や経済振興を目的としたもの。国際的潮流への追従か、経済的負担を押し付ける意図かは、政策の効果次第で評価が分かれます。
メディアと政治家の役割
地球規模の問題は、情報の切り取り方で大きく印象が変わります:
- 政治的アジェンダ:気候変動やSDGsは、国際協調や産業改革を正当化する「便利な物語」として使われます。日本の場合、脱炭素を口実に原発再稼働や新技術投資を進める動きも。
- メディアの偏向:温暖化の脅威を強調する報道が主流で、懐疑論は「科学的異端」として扱われがち。日本のメディアは国際潮流に追従し、批判的検証が不足するとの指摘。
- 商業的動機:SDGsは企業にとって「倫理的ブランド」を構築するツールであり、メディアも危機感を煽る報道で視聴率を稼ぐ傾向があります。
「上手な商売方法」としてのSDGs
SDGsが商売として機能する例は多いです:
- グリーンウォッシュ:HISのパーム油バイオマス発電事業が、森林破壊を引き起こすとして批判されたケース。
- 投資市場:ESG投資の市場規模は数十兆ドルに達し、ブラックロックなどの運用会社が巨額の手数料を得ています。
- 補助金ビジネス:各国で脱炭素技術に巨額の補助金が投入され、関連企業が政策頼みのモデルを構築しています。
どう考えるべきか?
SDGsや気候変動は、科学、経済、政治が絡む複雑な問題です:
- 批判的思考:科学的コンセンサスを尊重しつつ、懐疑論にも耳を傾ける。陰謀論は証拠を慎重に検証。
- 利権の追跡:太陽光パネルやEV関連企業の株価、補助金配分をチェックし、誰が利益を得ているかを見極める。
- 日本の立ち位置:国際的プレッシャーに追従しつつ、技術力(CCSや水素)を活かせば競争力強化も可能。
- 個人の行動:IPCC報告書や企業のESG報告書など一次資料を確認。投資はファンダメンタルズを慎重に分析。
結論
SDGsや温暖化をめぐる議論は、利権や政治的意図が絡む「上手な商売」である一方、環境課題の解決に寄与する可能性もあります。日本がSDGs投資に前のめりなのは、国際潮流への追従と産業振興の両面があるものの、海外の「反ESG」トレンドやグリーンウォッシュのリスクを軽視すべきではありません。情報を多角的に検証し、不透明な構造を見抜くことが重要です。



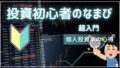
コメント