「搾取型金融商品」という言葉を、あなたは聞いたことがありますか?
これは正式な金融用語ではなく、造語です。ですが、意味するところは極めて明確です。
消費者が損をし、販売者や仲介業者が儲かるよう設計された、不公正な構造の金融商品
簡単に言えば、お金の知識がない人ほどカモにされやすい商品のこと。
本質からかけ離れた「過剰な手数料」や「不透明なリスク」が潜んでいるものが多く、知らずに買ってしまうと、資産形成どころか逆にお金を失ってしまうこともあるのです。

この記事はこんな人におすすめ
- 銀行や保険会社に「おすすめ」と言われた商品に違和感がある人
- 投資を始めようとしているけど、よくわからない金融商品が多くて不安な人
- 自分や家族の資産を守りたいと思っている人
搾取型金融商品の5つの特徴
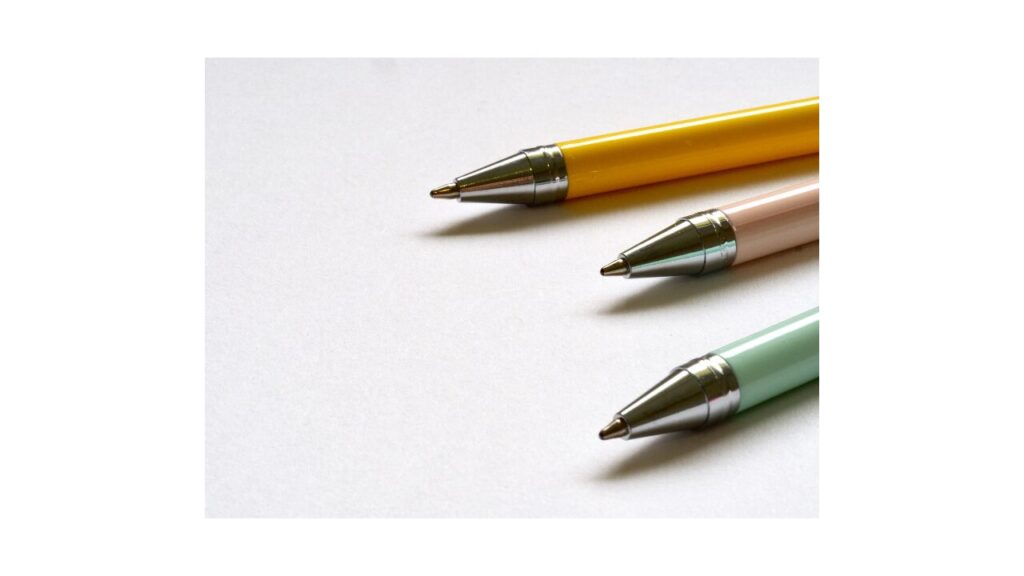
- 複雑な仕組みで中身がわかりにくい
- 販売者だけが得をする構造
- 長期保有でもリターンが期待できない
- 解約すると手数料で大損
- 「安心」「保障」「安定」など、不安を煽るワードが並ぶ
代表的な搾取型金融商品の実例
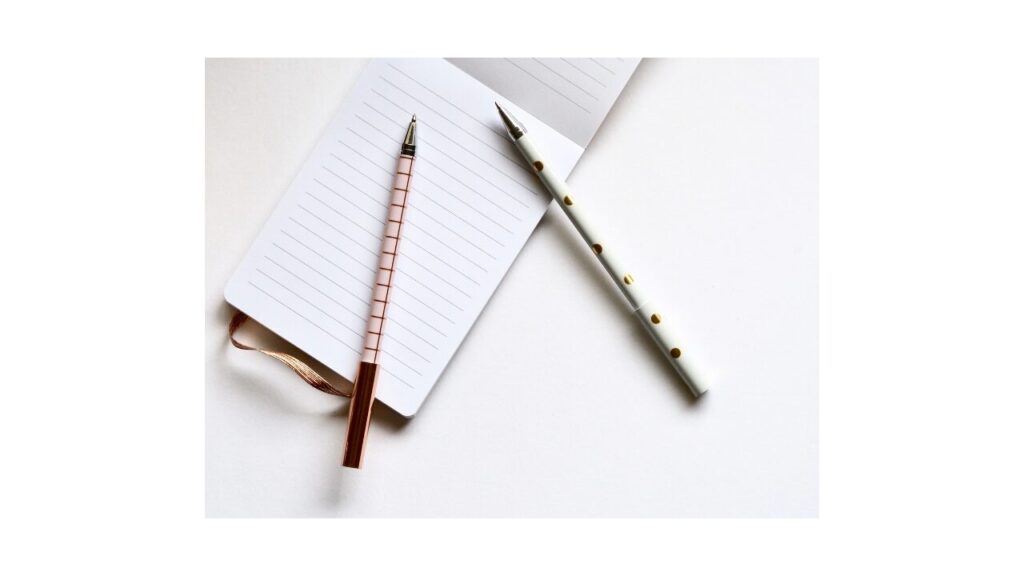
◆ 外貨建て保険(一時払い型)
- 銀行窓口で高齢者に多く販売
- 為替リスクがあるにも関わらず「安全」と強調される
- 解約手数料が高く、途中解約で損する可能性が大
途中解約しようとすると「もう少しで返戻金がプラスマイナスゼロになる」という悪魔に襲われます。プラマイゼロまであと数年あったらどうしますか??一時払いしたお金の「資金拘束」がすごいですよね。自分だったら解約して手数料の低いインデックス投資信託を買います。
◆ ラップ口座(投資一任口座)
- 手数料の二重・三重取り
- 利回りよりも手数料の方が上回るケースも
- 投資初心者に「おまかせ運用」として勧められやすい
複雑でよくわからないけど「プロに任せておけば増えるみたいだし」という情弱からお金を搾取する仕組みの典型例。
◆ 毎月分配型の投資信託
- 「毎月お金がもらえる!」という印象を与えるが、元本を削っていることも
- 長期で見れば資産が減る場合が多い
分配されているお金、実はあなたが預けたお金を「切り崩している」だけかもしれませんよ。
◆ ワンルームマンション投資
- 表面利回りは高く見せかけるが、実際は管理費・修繕費・空室リスクでマイナス
- 売却しようとしても二束三文
業者は売った時点で利益確定。買った人は業者の利益分を負債として押し付けられているだけ。
◆ 高額な投資スクールや情報商材
- 「誰でも稼げる」などの甘い言葉に注意
- 高額な初期費用を取った後、紹介される投資商品も搾取型の可能性大
誰でも稼げるほど世の中甘くないのは自分が一番わかっているはず。「貧乏になるとバカになる」みたいなので気をつけてください。
なぜ搾取が起きるのか? 〜商流に潜む「中抜き」構造〜

商品からサービスに至るまで、私たちが払うお金には多くの中間業者が関わっています。
たとえば、コストの高い投資信託というものは:
| 費用の内訳例(年間) |
|---|
| 販売手数料:2% |
| 運用管理費用:1.5% |
| 営業担当へのインセンティブ:1% |
| 広告・販促費用:0.5% |
→ 本来10,000円の価値の商品が、15,000円で売られていることもあるのです。
これはつまり、「搾取されている分、あなたのリターンが減っている」ということ。資産形成の足を引っ張る“見えない敵”と言えるでしょう。
搾取型金融商品に引っかからないための3つの視点

① その商品で、一番得をしているのは誰か?
販売者や仲介業者のノルマが優先されていないかを疑ってみましょう。
② 途中解約するとどうなる?
「やめたくなったとき」の損失を事前に確認することが重要です。
③ 自分が“理解できるまで”買わない
「プロが勧めてくれたから」ではなく、「自分で納得したから」買う姿勢を。
まとめ|情報を持つことが最大の防衛
金融商品は、本来「お金を増やすため」のものです。
ところが、情報を持たないまま飛び込んでしまうと、資産を減らすための罠に変わることもあります。
「搾取型金融商品」という視点は、今後ますます重要になるでしょう。大切な家族と未来を守るためにも、ぜひ「誰が得をしているか?」という視点を忘れずに。
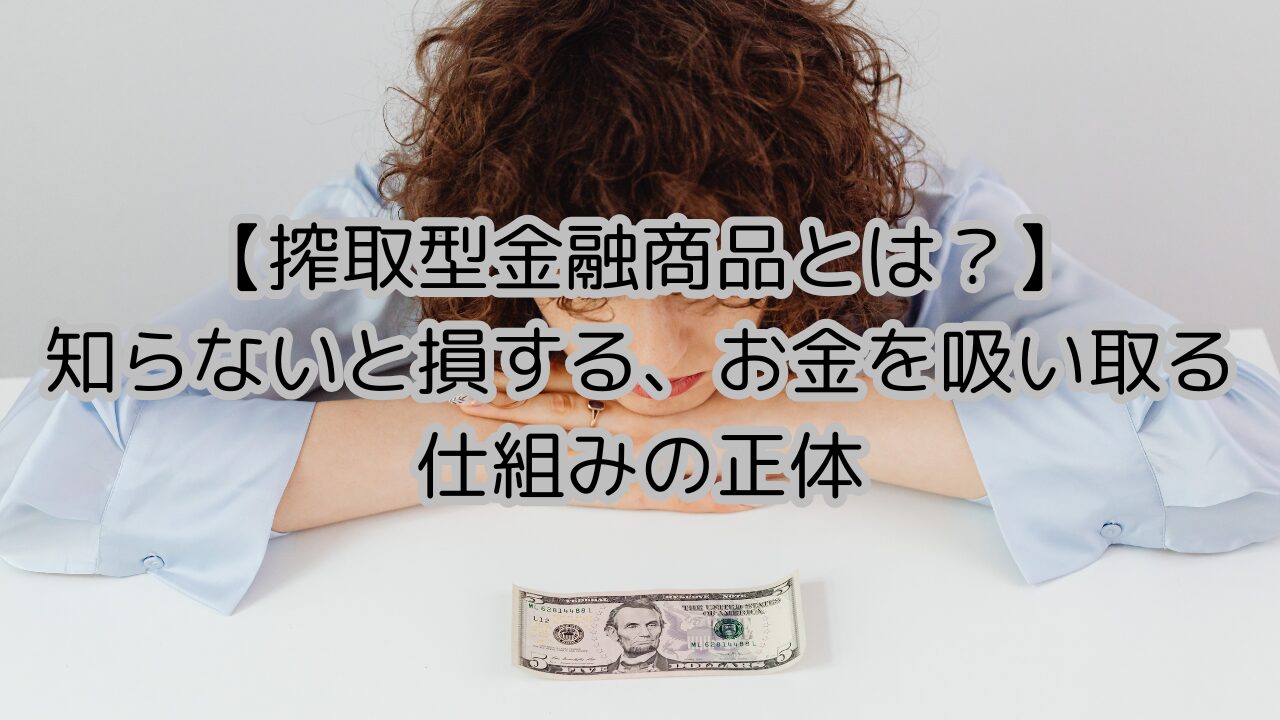



コメント