この30年、日本の平均給与はほとんど変わっていません。もはや日本を体現する常套句です。
SNSやメディアでもたびたび話題に上がり、「なぜ我々の生活は豊かにならないのか?」という疑問が、国民の潜在的な不満として蓄積しています。しかし、冷静に考えてみれば、日本はいまだGDPで世界トップクラスの経済大国です。これほどの価値を生み出していながら、なぜ国民の懐は温まらないのでしょうか。
これが構造的な問題である、と気づいた人は「構造の外」へ目を向けて脱出するしかありません。
どんな人に向けた記事か
・経済ニュースを見て違和感を感じている方
・給与が上がらないことに疑問を感じている若手労働者
・日本経済の構造に関心を持つビジネスパーソンや医師などの知識層
GDPの虚像と現実

日本のGDPは世界で今も上位に位置し、多くの製品やサービスを世界に供給しています。しかし、GDPという指標は必ずしも“国内に還元された豊かさ”を意味するものではありません。むしろそれは、全体の経済活動の大きさであり、誰がその果実を得ているかまでは問わない数値です。
どこに消える我々の価値

我々が生み出した価値は、内部留保として企業に滞留し、あるいは法人税の優遇や多国籍企業への配当、海外への再投資という形で日本国外へと流れています。つまり、日本という土台の上で、他国の富や一部の人間への富が構築されているという構図です。給与という形で還元されず、消費にも回らず、ただ資本の論理に従って「使われないお金」として眠っているのです。
国民はそこの抜けた桶

一方で、個人の家計はどうか。携帯料金や保険料、エネルギーコストなど、必需的支出は増え続け、手元に残る余裕は減っています。加えて、社会保険料や税負担の増大が、それに拍車をかけています。政府はプライマリーバランス黒字化という目標を掲げていますが、その裏で国民の財布は着実に削られているのです。
日本という市場の草刈場化

日本は単なる労働力供給地としてではなく、その市場や公共資産が構造的に外資に開放されてきました。郵政民営化を皮切りに、外資が日本の金融資産やインフラにアクセスする道が整備され、下水道や水道といった生活基盤すら海外企業に売却される事例が現れています。トランプ政権時代の関税交渉の見返りとして、日本は80兆円規模の対外投資を約束したとも言われています。これらは、単なる民間レベルのグローバル化ではなく、国家政策として資本を国外へ流す「仕組まれた草刈場化」である可能性があるのです。
まとめ
我々が生み出した価値は、どこかへ消えてしまっているのではありません。それは構造的に、意図的に、外へと流れるように設計されているのです。日本は経済成長を支える土台として利用され、その上に築かれた富は、国民のものではなくなっています。
草刈場としての国家、そこの抜けた桶としての家計。この二重の構造の中で、国民が真に豊かさを実感することは難しい。果たして、我々はいつまでこの「出涸らし」を受け入れ続けるのでしょうか。次に問うべきは、これが偶然の産物か、それとも誰かの意図によって導かれた結果なのか──という視点なのかもしれません。
しかし、どちらにしろこの構造をひっくり返すことは難しいです。「うまく利用する」方法を考えていくべきなのだと思います。
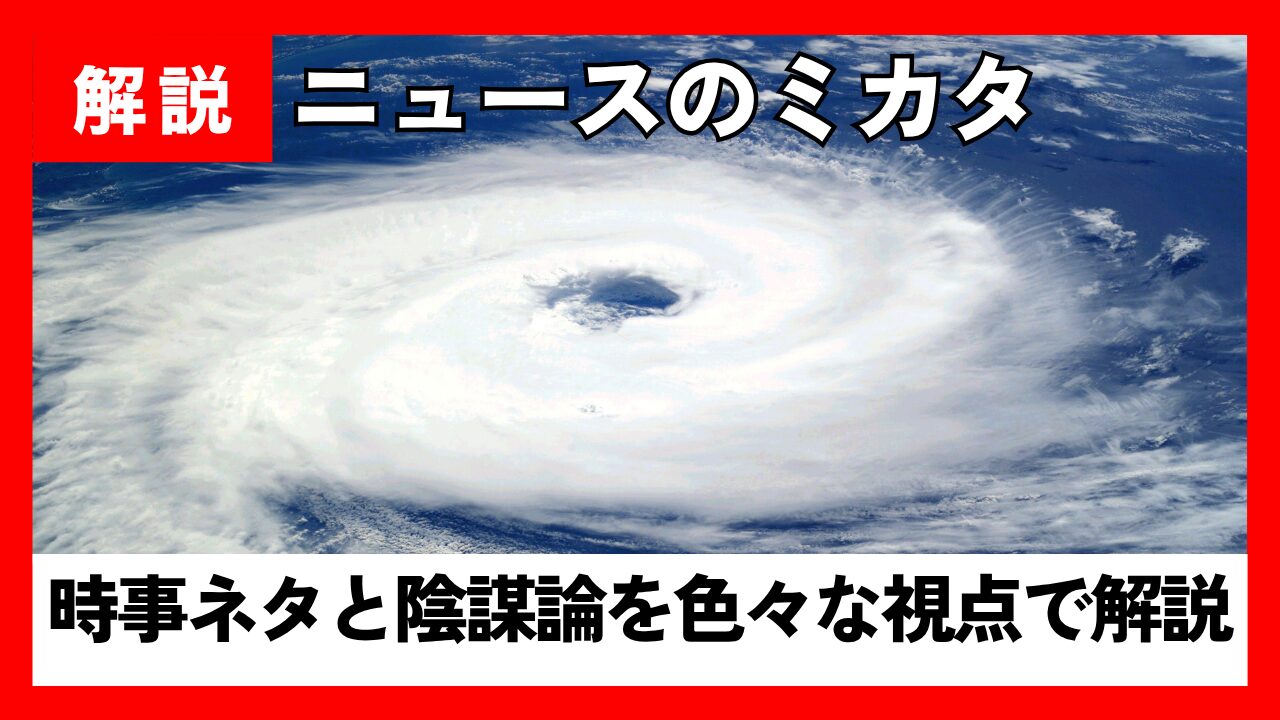

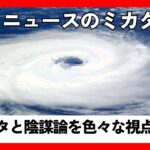
コメント