私たちは日々、失敗や不快な出来事に直面しながら生きています。そんなとき、「自分が悪かったのだ」と自責に陥るか、「あの人のせいだ」と他責に傾くか──多くの人がこの二項対立のあいだで揺れ動きます。でも、その思考の枠組み自体が、じつは私たちの心を重くしているのではないか。2025年7月26日のこの瞬間、私はそんな問いを持ってこの文章を綴っています。
本当に必要なのは、「誰が悪いのか」を問うことではなく、「なぜそうなったのか」を静かに見つめる視点です。失敗は個人の問題ではなく、たいていはそれを許容しない仕組みや構造にこそ原因がある。逆に、すばらしい出来事は誰かの意志と優しさが重なった証なのだと考えてみると、心の中に静かな余白が生まれてくるのです。
どんな人に向けた記事か
この文章は、日々の暮らしや仕事のなかで、つい自分や他人を責めてしまいがちな方、また、責任と感謝のバランスについて思いを巡らせたいと感じているすべての方に向けています。
自責でも他責でもなく
仕事の現場で、あるいは家庭や人間関係の中で起こる「ミス」。たとえば医療の現場であれば、確認ミスによる投薬の誤り。教育の現場であれば、児童の変化に気づけなかったという後悔。それらはしばしば「人間のエラー」とされ、責任の所在が追及されがちです。
けれども、少しだけ視点をずらしてみると見えてくるものがあります。それは、「そのエラーが起こらざるをえなかった仕組みはどうだったのか」という問いです。なぜヒューマンエラーが起きたのかではなく、「ヒューマンエラーが起きても致命的にならないようにする設計」がなされていたのか──そこにこそ、本質的な原因が潜んでいるのではないでしょうか。
どんなに注意深い人でも、集中力の持続には限界があります。多忙なスケジュール、過重な責任、孤独な意思決定。そうした状況は、個人の努力では解消しきれません。つまり、ミスの根は個人ではなく、構造や制度、文化にあることが多いのです。
感謝とは、構造を超える意志へのまなざし
逆に、ものごとがうまくいったとき。「あの人が気を利かせてくれた」「運が良かった」「たまたま間に合った」──そんなふうに片付けてしまいがちな場面ほど、そこに誰かの配慮や思いやり、つまり意志が介在していたのではないかと考えてみる。
すると、不思議なことに、うまくいった「構造の偶然」ではなく、「個人の意志による介入」が見えてきます。人間の善意、余計なことをしてくれた誰か、手間を惜しまずに支えてくれた人たち──感謝の対象は、見えないけれど確かに存在しています。
これはとても逆説的です。失敗のときは「構造のせい」と考え、成功のときは「人の意志」とみなす。すると、責任の重荷からは解放され、代わりに感謝の念が心に満ちていくのです。
構造を見つめる知性、感謝を抱く感性
心を軽くするために必要なのは、「責任を問う」思考から一歩離れ、仕組みや構造を冷静に見つめ直す知性です。そしてもう一つ、他者の善意や働きかけに気づき、そっと感謝する感性。
これは、単なるポジティブ思考ではありません。社会の中で生きる私たちが、自分を責めず、他人も責めず、それでいて問題に目をそらさないための、構造的かつ人間的な生き方なのだと思うのです。
まとめ
「それは誰の責任か?」という問いを抱えるたびに、私は一歩引いて、こう考えるようにしています。
それは、どんな仕組みの中で起こったことだったのか?
そして、その中で誰かが自分のためにしてくれたことは何だったのか?
この二つの視点を持つだけで、心の重荷は少し軽くなり、現実に対する見方もまた変わっていきます。ヒューマンエラーを責めることなく、ヒューマンウェアの意志を讃えること。それこそが、これからの社会に必要な「優しいまなざし」なのかもしれません。
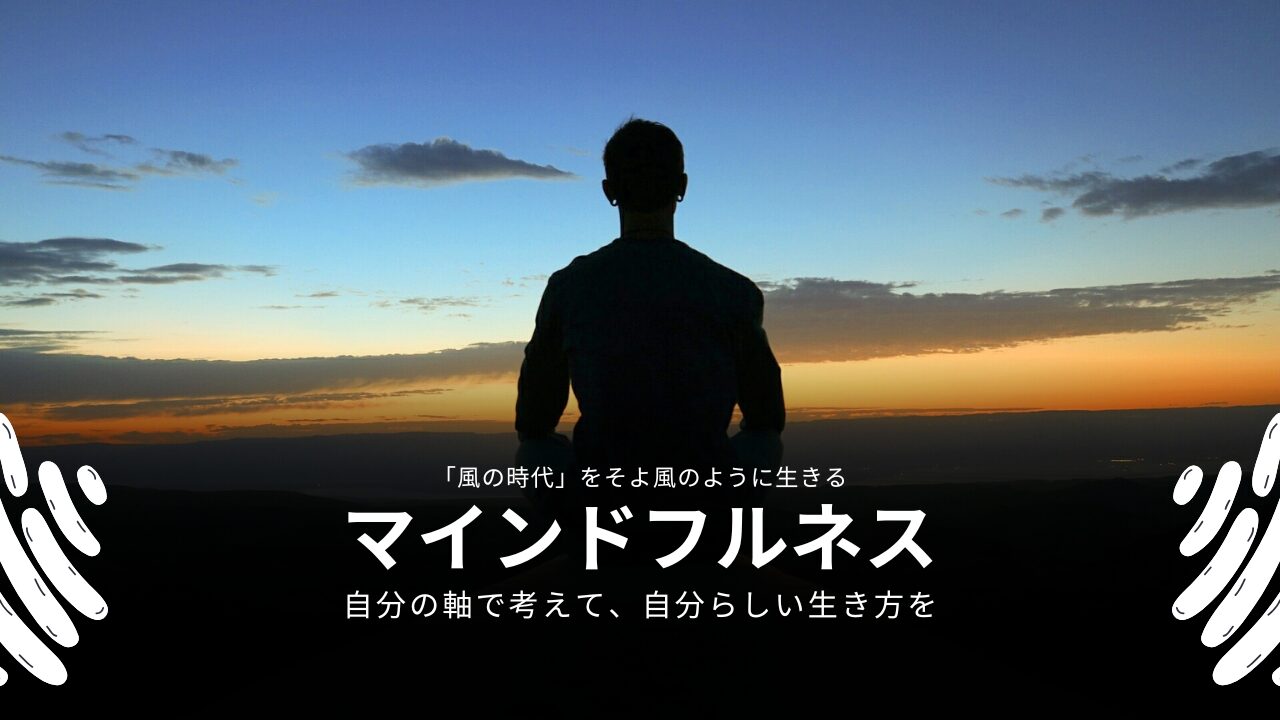


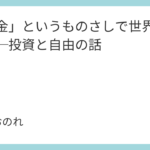
コメント