なぜ日本では、学校で「お金の仕組み」を教えないのでしょうか?
通貨発行の仕組み、銀行の信用創造、複利の力、リスクとリターンのバランス。
これらは、私たちが人生を設計する上で不可欠な知識であるはずなのに、義務教育では一切触れられません。
実は、お金を「知らないまま」にしておくことが、社会にとって、ある種“都合がいい”からかもしれません。
そして、その無知の上に成立しているビジネスが確かに存在しています。
今回は「なぜお金の教育がないのか?」という視点から、
民族性と教育の関係、そして“知らない人々”を前提とした金融構造について深掘りしていきます。
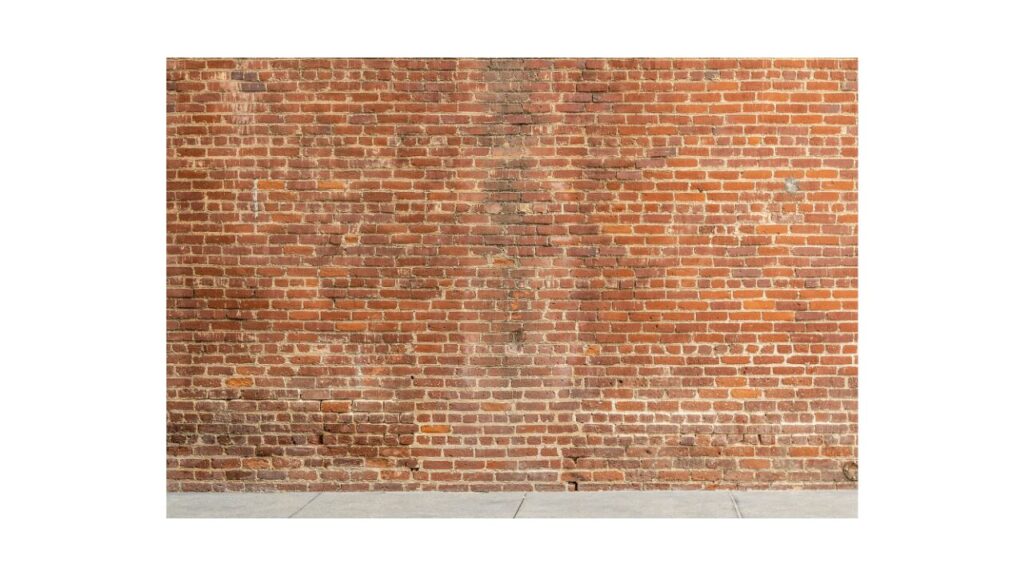
【こんな人におすすめの記事】
- 投資や金融に関心はあるけれど、どこか怖さを感じている方
- なぜ日本ではお金の教育が遅れているのか疑問に感じる方
- 保険やローン、貯蓄が本当に得なのかを考えたい方
- 「知らなかったことが損につながっている」と感じたことがある方
- 金融・経済を“支配構造の視点”から読み解いてみたい方
■ 民族とお金の価値観の違い
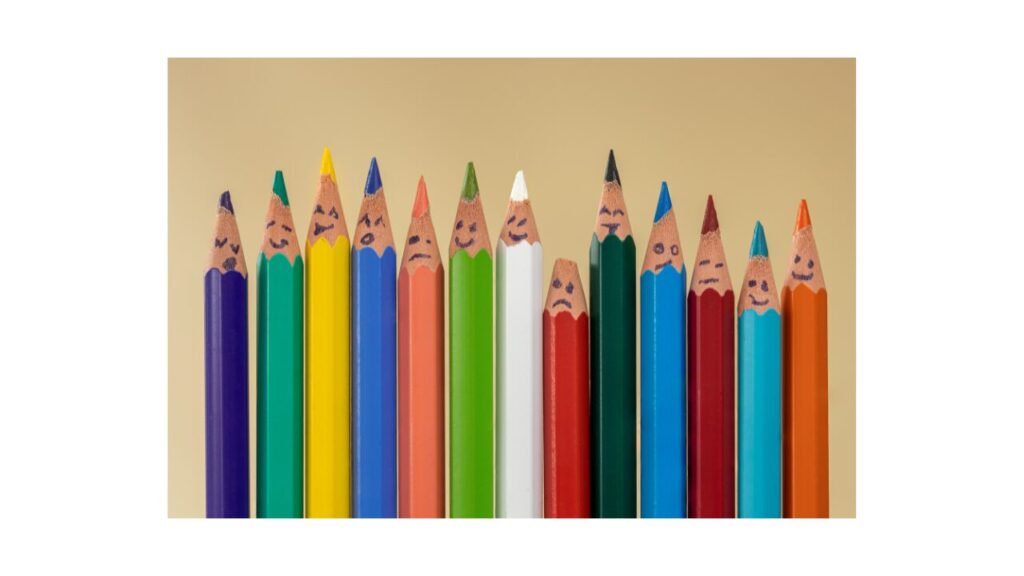
お金に対する考え方は、民族性や文化によって大きく異なります。
- アメリカ人:消費社会。クレジットカード文化。未来の収入を担保に今を楽しむ
- ユダヤ人:資産運用のプロ。お金は“寝かせるものではなく働かせるもの”。貯金は貨幣価値の目減りと見る
- 日本人:倹約・貯金好き。リスク回避型。お金=“汚いもの”という道徳観に影響された文化
この背景には、戦争・宗教・国家制度など複雑な要因がありますが、特に日本人に根強いのが「お金を語るのははしたない」という価値観です。
これは本能的なものというより、長年の“道徳教育”と“メディア教育”の結果として刷り込まれたものとも考えられます。
■ 学校ではなぜお金を教えないのか?

「なぜ?」を真剣に考えてみましょう。
それは、日本の義務教育が「勤勉な労働者」を育てるために設計されており、
お金を“持つ側”ではなく、“使う側”として位置づけられているからです。
- 投資より貯蓄
- 利益より節約
- 知識より我慢
こうした教育を受けた国民は、“従順な消費者”として非常に都合が良い存在になります。
もしも多くの人が、お金の本質(インフレ・複利・税制・信用創造)を理解し始めたら、
現在の「搾取型金融商品」は成立しなくなってしまいます。
■ 教えないことで儲かる仕組み
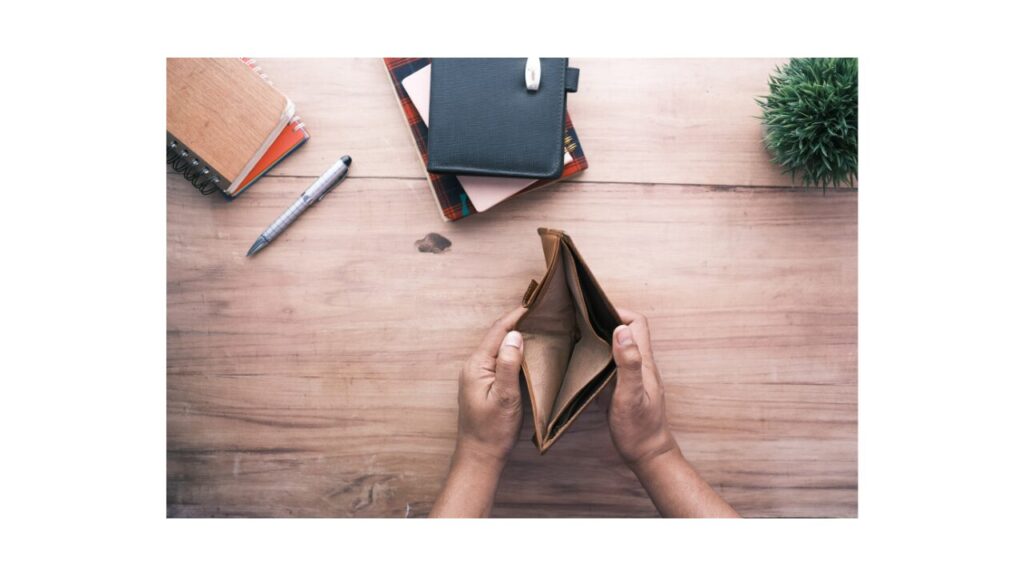
実際に、金融リテラシーの低さに乗じて利益を得ているビジネスは数多く存在します。
例えば:
- 貯蓄型保険:リスクとリターンを隠し、「安心」の名で高額の手数料を吸い上げる
- 住宅ローン:低金利でも長期契約による利息総額で莫大な利益
- カーローン:利便性と分割の罠
- 銀行の信用創造:1万円の預金が10万円の貸し出しを生み出す仕組み
これらは、国民が“仕組みを知らないこと”を前提に成り立っているビジネスモデルです。
つまり、知られては困る人たちがたくさんいるのです。
■ 知れば変わる「お金との向き合い方」

では、仮に私たちが「知ってしまったら」どうなるでしょうか?
- 投資と貯金のバランスを考えるようになる
- 保険は必要最小限にし、資産運用に目を向ける
- 借金と金利の怖さを理解し、浪費を見直す
- 税金や手数料に敏感になる
- 自分の時間とお金の価値を意識し始める
これだけでも、経済的に搾取されるリスクは劇的に下がります。
「賢く生きる人」が増えると、金融機関のビジネスは大きな転換を迫られるでしょう。
■ 教育は“教えない”ことにも意味がある
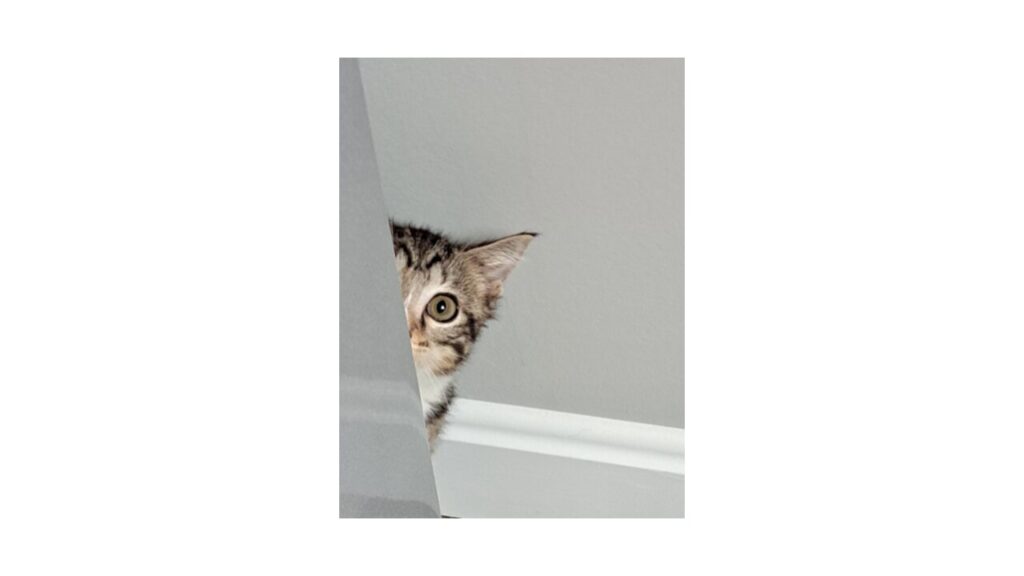
つまり、学校でお金を教えないのは偶然ではなく、“設計”なのです。
それは:
- 国民が労働者として、消費者として、税収の源泉として「安定的に機能する」ため
- 「お金を知らない人」が社会を回す歯車として都合がいいから
- 「知ってはいけない本質」に踏み込まない教育こそが、支配の道具だから
【まとめ】
「お金のことを話すのは下品だ」
「投資なんてギャンブルだ」
「とにかく貯金が一番安全」
そう思わされてきたとしたら、それはあなたの中に「誰かの都合」が埋め込まれている証拠かもしれません。
お金の教育がないことに“怒り”を覚える必要はありません。
ただ、「知らないままでいることが損になる時代」だと気づいた今、
あなたは自分の人生の舵を取り戻すことができるのです。
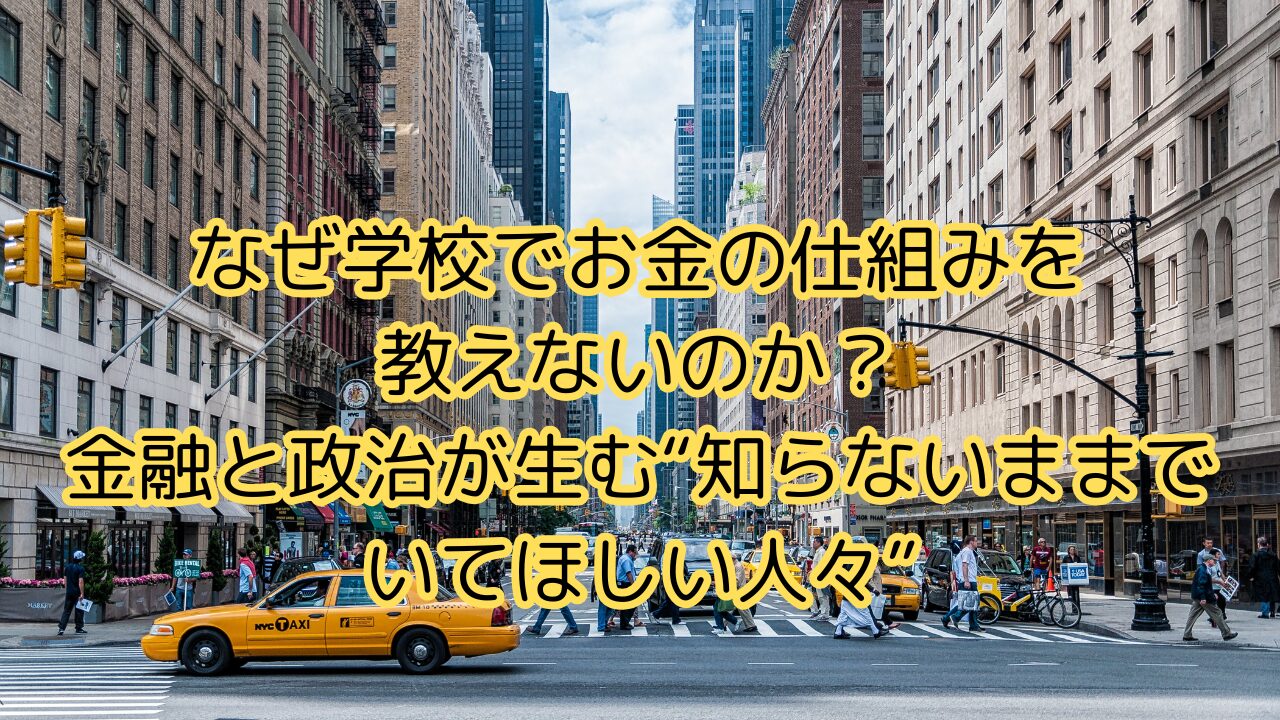



コメント