ここ10年で市場が拡大した「仮想通貨」
自分は所有していませんが、
その仕組みに興味を持ちました。
仮想通貨という市場ができ、バッファーとなることで
株式市場への過剰なマネーの供給を抑制し
株式市場が実体経済とかけ離れすぎないようにする
その調整役として機能しているのではないか?
株価ばかりが上昇すると労働者から不満がたまりかねないので
それを隠すための目眩し?
と勘繰ってしまいます。
どうやら仮想通貨(暗号資産)が生まれた背景には、
複数の要因が絡み合っているようです。
「増え続けるマネーの受け皿」という側面も後から結果として現れていますが、
最初の発想は少し違うものでした。
以下、順を追って説明します。
1. 誕生の背景:ビットコインの思想
仮想通貨の始まりは、2009年にサトシ・ナカモトが発表した「ビットコイン」です。
その背景には、2008年のリーマンショックが大きく影響しています。
- リーマンショックでは、銀行や政府が巨額のマネーを発行して金融システムを救済しました。
- その結果、
- 通貨発行権を持つ中央銀行が「無限にお金を刷る」ことができる
- 個人はその影響を避けられず、インフレや税負担の形でリスクを背負う
という不公平さが顕在化しました。
サトシ・ナカモトはこれに対して、
「政府や銀行に依存せず、数学とアルゴリズムによる信頼で価値を保てる通貨をつくろう」
という思想を持ちました。
つまり、**最初の目的は「中央集権からの解放」**です。
これは金(ゴールド)と似ていますが、デジタル空間で取引できるという大きな進化がありました。
2. ブロックチェーン技術による革命
ビットコインはブロックチェーンという分散型台帳技術を採用しました。
- 誰か一人が管理するのではなく、世界中のネットワーク参加者が同時に記録を監視。
- 「二重払い(同じコインを2回使う問題)」を技術的に防止。
- 政府や銀行に頼らずに、数学的な証明だけで価値のやりとりが可能。
この仕組みによって、国家や銀行の信用を前提としない通貨が初めて実現しました。
3. 投資対象としての広がり
当初は理想主義的なプロジェクトでしたが、次第に投資対象として注目されるようになります。
- 2010年代後半からは、世界中で金融緩和が続きました。
例:アメリカFRB、日本銀行の量的緩和 - マネーが過剰に供給されると、株式や不動産などにお金が流れ、バブルが形成されます。
- 投資家は**新しい「マネーの逃避先」**を探し、ビットコインをはじめとした仮想通貨に資金が流れました。
この意味では、株式市場への過剰な資金集中を分散させる効果があったと言えます。
ただし、これはビットコイン誕生時の意図ではなく、結果的な副産物です。
4. 株式バブルとの関係
仮想通貨がなかった場合、余剰マネーは株式市場や不動産市場にさらに集中した可能性があります。
仮想通貨は次の2つの役割を果たしています。
① マネーの受け皿としての「逃避先」
- ビットコインは「デジタル・ゴールド」と呼ばれ、インフレヘッジ手段として買われる。
- 実際に2020年のコロナショック後、FRBが巨額のマネーを刷ったことで株と同時に仮想通貨も高騰しました。
② リスク分散による株式市場の過熱抑制
- 投資対象が株と不動産しかなければ、資金が集中してバブルが極端に膨らむ。
- 仮想通貨が存在することで、資金の一部が分散され、株式一本集中を和らげる作用があったと考えられます。
5. 政府・金融当局の視点
政府や中央銀行から見れば、仮想通貨はコントロールしにくい存在です。
- 本来、通貨発行権は国家が独占するもの。
- 仮想通貨はその独占を揺るがすため、各国は規制を強化しています。
しかし一方で、金融当局にとっても「資金の逃げ場」があることは完全に悪いことではありません。
- 株式や不動産だけに資金が集中すればバブル崩壊リスクが高まる。
- 仮想通貨は、リスクマネーを一部吸収してくれる「バッファ」の役割を果たしているとも言えます。
6. まとめ
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 誕生の目的 | 中央銀行や政府に依存しない通貨を作る(分散型・数学的信頼) |
| 技術革新 | ブロックチェーンにより二重払い防止、管理者不要を実現 |
| 投資マネーとの関係 | 余剰マネーが仮想通貨に流入し、株式市場への過熱を一部抑制 |
| 副産物 | 株や不動産のバブルを分散する「逃避先」になった |
| 政府視点 | 規制強化しつつも、資金の分散先として完全否定はしない |
7. 結論
仮想通貨はもともと、
**中央集権型の金融システムへの不信から生まれた「自由な通貨」**でした。
しかし、世界的な金融緩和でマネーがあふれた結果、
株式市場や不動産市場への資金集中を和らげる投資対象
という役割も担うようになりました。
つまり、
誕生の理由は「理想」だが、現代での存在意義は「マネーの逃避先」
という二重構造になっていると言えます。
株式市場や不動産市場への資金集中を回避するバッファーとしての役割は、
株式や不動産のバブル崩壊を和らげてくれているという見方ができます。



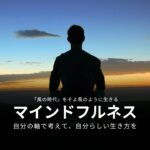
コメント