今日は何も書けない。頭の中は静かで、言葉がどこにも見当たらない。そんな日が、ふいにやってくる。焦るわけではないが、どこか落ち着かない。それでも、ふと立ち止まって自問する——「本当に、これは停滞なのだろうか?」と。もしかするとこの静けさは、心が満たされ、余計な感情が波立たないという、ある種の“整い”のサインかもしれない。
日々考え、書き、発信し続ける人。ときに自分の中から湧き上がる思いや疑問が言葉にならず、「今日は何も出てこない」と感じる人。そんな“創造の沈黙”に出会ったことのあるすべての人へ。
私たちは日々、何かを生み出そうとしている。
言葉、行動、意志。それらはすべて、外界との接点を持とうとするエネルギーの表現だ。しかし、それが出てこない日がある。まるで井戸が一時的に枯れたように。
こうした状態を、私たちはしばしば“停滞”と捉えてしまう。何かが滞っている、進んでいない、自分が鈍くなっている……そんな自己否定の感情が忍び寄る。しかし、本当にそうだろうか。
実はその逆なのかもしれない。思考も感情も落ち着き、怒りも不安も焦燥もない日。そんな日は、満ち足りていて言葉という刺激が必要ない日なのだとしたら。たとえるなら、外に向かって成長する春夏の時期に対して、内側で静かに養分を蓄える秋冬のような時間。
哲学者マルティン・ハイデッガーは、
「沈黙の中にこそ、最も深い思索がある」と語った。言葉が消えることで、むしろ私たちは自分自身の“あり方”と向き合うようになる。それは表現ではなく、存在への問い。
そしてもう一つの可能性もある。「なぜ何も書けないのか?」と問うこと自体が、すでに創造の一歩であるという視点だ。何もないことはゼロではなく、むしろ“まだ現れていないもの”への扉なのかもしれない。
まとめ
「今日は何も書けない」——それは、創造の終わりではなく、始まりの前の静寂。書けない自分を責めるのではなく、その沈黙の質に耳を澄ますとき、私たちは本当の意味で“思考している”と言えるのかもしれません。
停滞か、充足か。それはその日、自分の内側にどんな風が吹いているかによって変わる。そしてその風の音に気づけたとき、人はまた一歩、自分を知るのではないでしょうか。
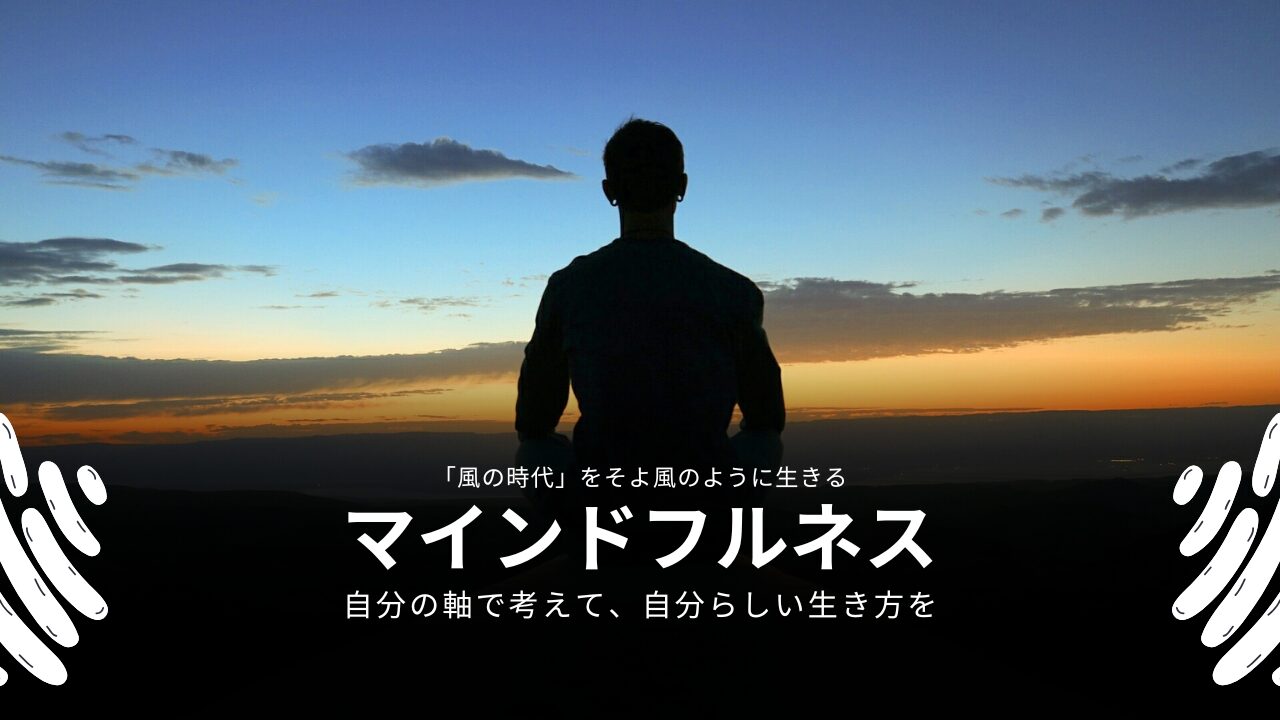

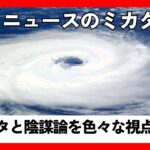
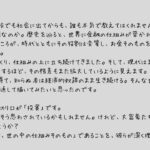
コメント