2008年のリーマンショック。
自分はまだ大学生でした。遠いアメリカでの不動産の話でしょ?程度の認識です。
※リーマンショックとは?
リーマンショック(2008年の金融危機):
簡単に言うと、「アメリカで住宅ローンを返せなくなった人が増え、その影響が世界中の金融機関に広がって、世界の経済が大混乱した事件」です。住宅ローンが返せない → 銀行が損する → 投資家も損する → 株やお金の動きが止まるという連鎖反応が起きて、株価が大暴落し、たくさんの会社がつぶれたりしました。特に象徴的だったのが、大手の投資銀行「リーマン・ブラザーズ」の破綻です。これにより世界中の市場がパニックになり、深刻な不況が始まりました。
あれから15年以上が経ち、今の若い世代にとっては、もはや教科書の中の出来事かもしれません。ですが、あの「世界が止まった瞬間」は、私たちが生きる金融の構造、そして“意図”というものを考えるうえで、今もなお色褪せないヒントを与えてくれます。
今回の記事では、リーマンショックを「陰謀論」という視座から読み直してみたいと思います。ただし、ここで言う陰謀論とは「非合理な妄想話」ではありません。
むしろ「誰が得をし、誰が損をしたのか」を冷静にたどるための、もうひとつの道具です。
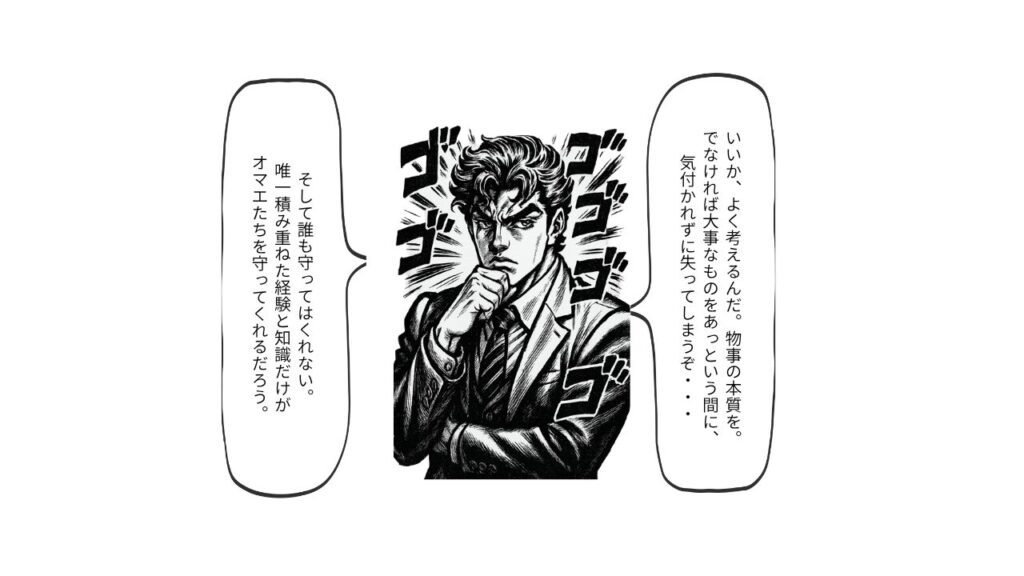
この記事はこんな方に向けています
- リーマンショックの構造的背景を深掘りして知りたい方
- 陰謀論という言葉に違和感を持ち、何かの“操作”を感じている方
- 金融の本質と権力構造に興味を持ち始めた方
「破綻させるべきではなかった銀行」が選ばれたという事実
2008年9月15日、アメリカの大手投資銀行リーマン・ブラザーズが経営破綻しました。そのとき、世界の市場はまさに凍りついたように機能不全に陥りました。
けれど、奇妙なことがあります。
リーマンよりも前に経営危機に陥っていたベア・スターンズは、政府の支援を得て救済され、保険会社のAIGも、18兆円もの公的資金で延命されました。
なぜリーマンだけが“見捨てられた”のか。
この問いには明確な答えが提示されていません。むしろ、そこに政治的・金融的な「意図」を読み取る視点が求められます。
※ベア・スターンズ、AIGとは?
ベア・スターンズ(Bear Stearns):アメリカの大手投資銀行の一つで、サブプライムローン問題で経営が悪化し、2008年に政府の支援のもとJPモルガン・チェースに買収されました。
AIG(American International Group):世界的な保険会社で、金融商品にも多く関わっていました。リーマンショックの影響で経営危機に陥りましたが、政府から約18兆円という巨額の支援を受けて救済されました。2006年から2010年にかけての4年間、マンUのユニフォームの胸に刻まれていたロゴを覚えている人も多いのではないでしょうか。

単なる住宅バブルの崩壊ではなかった
教科書的には、リーマンショックの原因は「サブプライムローン」という返済能力の低い人向けの住宅ローン商品が破綻したことにあります。ですが、それだけでは説明のつかない「準備」と「タイミング」が、あまりに整いすぎていた。
市場が崩壊したその瞬間に、CDS(クレジット・デフォルト・スワップ)※3という“保険”を使って巨額の利益を得た金融機関があったのです。
※2:サブプライムローンとは、返済能力の低い人に貸し出す高金利の住宅ローンです。リスクの高い貸し出しで、結果的に大量の不良債権となりました。
※3:CDSは「貸した相手が破綻したときに備える保険のような商品」。しかしこれを“賭けの道具”として利用することで、他人の破綻に巨額の利益がつく仕組みが生まれていました。
「偶然」を装った権力再編だったのか?
事後的に見れば、リーマンの破綻は金融再編の引き金として働きました。小さな金融機関が淘汰され、JPモルガン、ゴールドマン・サックスといった巨大金融資本だけが生き残る構造が生まれた。
さらには、FRB(連邦準備制度)とアメリカ財務省が前例のない介入権限を手に入れ、世界の金融政策は国家を超えて動かされる時代へと突入していきました。
こうした現象を「陰謀」と見るか、「構造的な帰結」と見るかは、読み手次第です。ただ一つ言えるのは、誰かにとって都合が良かったという事実だけです。
陰謀論=妄想ではない。意図を読む訓練
私たちは、「陰謀論」という言葉によって、意図を読む思考そのものを封じられがちです。けれど、投資や経済というのはそもそも、人間の意図を読み取るゲームでもあります。
この世界は、偶然だけで動いてはいません。
そして、語られないことこそ、真実に近い。
リーマンショックを単なる経済危機として学ぶのではなく、「なぜそうなったのか」「誰が主導したのか」「誰が儲けたのか」を考えることこそが、私たちの生きる感度を高めてくれるはずです。
まとめ
リーマンショックは、決して「自然災害」のような偶発的出来事ではありません。政治、金融、情報、そして意図が交錯する中で、選ばれた犠牲だった可能性すらある。
陰謀論という言葉を恐れず、むしろ「複雑な構造を読む道具」として活用すること。それがこれからの時代を生き抜くための知恵であり、金融や社会を理解するための本当の“リテラシー”なのだと思います。



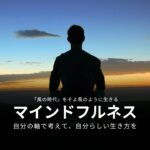
コメント