インフレが進む中、日本人の多くは「円預金こそ安心」という信仰にしがみついています。しかし現実には、物価上昇が続けば預金の実質価値は毎年目減りし、長期的には半減してしまいます。その背景には、日本社会全体で「金融リテラシー教育」が欠如してきた事実があります。学校でも家庭でも「お金の知識」を学ぶ場が乏しいまま、社会人となり、やがて資産を守れない大人を生み出してしまうのです。
今の60代、70代の親世代は「保険に入れ」「株式はギャンブル」だとコメントすることが多いと思います。それは、その方々の時代背景がそうさせたわけであり、その時代の正解であった可能性はあります。
ただ、ネット証券ができ、誰でも簡単に優良なインデックスファンドに投資ができるようになりました。長引くデフレで低金利が続き、「保険商品」の利率から見た魅力は親世代の時よりも著しく低下しています。お金を再現性高く増やす方法がそれ以外にもある現在で、あえて増やすことを目的に「保険に入る」は時代遅れの選択肢なのです。
年寄りの意見を聞くな、信用するなといっているわけではなくて、時代に合わせて知識をアップデートする必要があるということを理解しましょう。常に学ぶ姿勢が重要です。

誰に向けた記事か
- インフレに漠然と不安を抱く人
- 円預金が安全だと信じている人
- 株式や投資を避けてきた人
- 教育に関心がある親世代
- 日本の将来を真剣に考えたい人
日本人とお金のタブー
日本では「お金の話は下品」という文化が根強くあります。そのくせ貯金大国である日本。実は卑しいと思いながらお金が大好きで溜め込んでいるのが日本人の習性なのです。どうしてそうなるか?それ以外にお金と付き合う方法を知らないからです。家庭でも学校でも「稼ぎ方」「増やし方」「守り方」を学ぶ機会はほとんどありません。結果、多くの人が労働収入だけに依存し、資産形成や投資を「危険なもの」と誤解してきました。
金融リテラシー教育の国際比較
- 米国:高校や大学で投資・経済の授業が当たり前。株式投資は生活の一部。
- 北欧:家計管理や社会保障を学ぶ教育が徹底。
- 日本:貯金偏重。投資や保険の仕組みを学ぶ機会はほぼゼロ。
この差が、個人資産の規模や金融市場への参加率の違いを生んでいます。

インフレが暴くリテラシーの欠如
- 預金の実質価値はインフレ率2%で30年後には半減
- 株式や不動産など「実物資産」を持つ人との差が拡大
- 「学ばない」ことが最大のリスクになる
インフレは、金融教育を受けなかった世代に最も大きなダメージを与えます。労働所得から生活費を賄い、余った分を貯金する、という行動はインフレにおいていかれる行動です。我々は世の中の構造を理解し、お金を稼ぐことや働くことに関してもっともっと構造的に考えるべきです。
日本が学ぶべきこと
- 金融教育を義務化:高校・大学での基礎教育を制度化
- 家庭での会話:お金を「隠すもの」から「話し合うもの」へ
- 生涯学習:社会人になっても学び直せる仕組みを整える
知識を持つ者が資産を守り、持たない者が貧しくなるのは歴史の必然です。だからこそ教育は最大の資産防衛策なのです。

まとめ
インフレ時代に「お金の知識」を持たないことは致命的です。日本人が円預金に依存し続けるのは、教育で金融リテラシーを軽視してきた結果です。世界では常識となっている知識を、日本もようやく真剣に学ぶべきときに来ています。知識はインフレに奪われない資産――それを教育で広く共有できるかどうかが、日本の未来を左右するのです。
FAQ

Q1: なぜ日本人は円預金に依存しているのですか?
A1: 学校や家庭で金融教育が乏しく、貯金が安全だという文化的信念が根付いているからです。
Q2: インフレ下で円預金は安全ですか?
A2: いいえ。物価上昇により実質的な価値が目減りし、長期的には資産を失います。
Q3: 海外では金融教育はどのように行われていますか?
A3: 米国や北欧では学校で投資や家計管理を学ぶ授業があり、生活に直結しています。
Q4: 日本に必要な金融教育とは?
A4: 金融リテラシー、投資の基礎、家計管理、社会保障の仕組みなどを学ぶ教育です。
Q5: 金融リテラシー教育は資産防衛にどう役立ちますか?
A5: お金の価値減少を理解し、分散投資や資産形成を通じてインフレから資産を守る力になります。
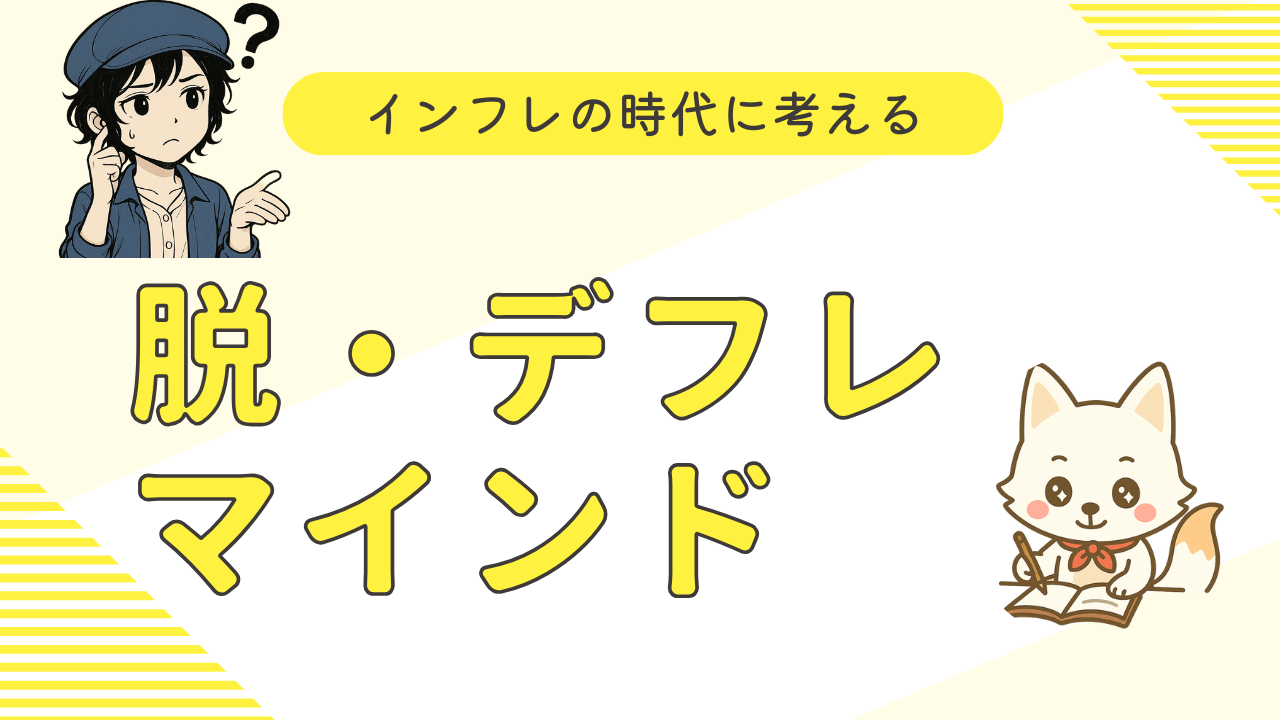

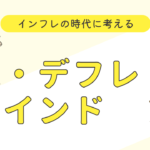
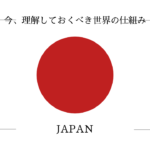
コメント