長らく日本は「デフレの国」と呼ばれてきました。物価が下がる時代には、円での貯金が最も安全だと信じられてきました。しかし近年、物価は着実に上昇し、2024年の消費者物価は前年比で約2~3%増。数字は小さく見えても、複利で積み重なれば30年で資産価値は半分近くに目減りします。円での預金は決して「安全」ではなく、むしろインフレに対しては最も脆弱なのです。円貯金こそ幻想――その事実に気づく必要があります。

誰に向けた記事か
- 貯金が唯一の資産防衛策だと思っている人
- 最近の値上げに不安を感じている人
- 株式投資を避けてきた人
- 歴史的にお金の価値がどう動いたか知りたい人
- 医療や専門職で時間がなくても資産を守りたい人
インフレとは何か
インフレは「物価が上がり、お金の価値が下がる現象」です。100円で買えたパンが110円になれば、同じ100円では足りません。つまり私たちの資産は毎年少しずつ削られているのです。逆にデフレは「物価が下がり、お金の価値が高まる」現象。日本は長くこのデフレに浸かってきましたが、それが逆回転を始めたのです。
デフレ時代と日本人の幻想
バブル崩壊後の日本は需要不足と賃金抑制で物価が上がらず、むしろ下がる局面が続きました。この環境が「貯金は減らない」という安心感を育てました。銀行に預けておけば安全、という思考はデフレが支えた幻想でもあったのです。
最近のインフレ事情
- 2023年の消費者物価指数(CPI)は前年比3.2%上昇
- 2024年も食品・エネルギー価格の上昇が続く
- 2%の物価上昇が30年続けば、購買力は約半分に縮小
100万円を円で持ち続ければ、名目は100万円でも実質価値は57万円程度に減る計算です。これが「静かな資産の毀損」です。
円預金は一点集中投資
円での貯金は「リスクゼロ」ではなく、「円という一資産に集中投資している」のと同じです。株式や不動産、外貨のように分散されていないため、インフレが続くとリスクはむしろ大きいのです。

歴史の教訓:1925年の100円
1925年の100円は、当時の購買力でいえば数十万円に相当しました。しかし2025年になっても「100円は100円」のまま。名目は変わらないのに価値は失われています。
一方、もし1925年に株式インデックスへ100円を投じていたらどうでしょう。米国株式の長期リターン(配当込み年平均6.5%)で試算すると、100年後には約54,000円。つまり500倍以上に成長していたことになります。これが「インフレを超える力」なのです。
まとめ
インフレは「静かな略奪者」です。気づかぬうちに円の購買力を奪い、生活をじわじわと圧迫します。円預金は安全どころか、最も無防備な資産形態なのです。歴史は明確に示しています――通貨の価値は減り続け、株式や実物資産だけがそれを補ってきたことを。インフレを舐めないリテラシーこそ、これからの日本で生き抜く力になるでしょう。
中央銀行が、インフレは2%くらいで緩やかに起こることが望ましいといいます。どうして2%が好ましいのか??それは経済の成長や、中央銀行のコントロールの力が及ぶ範囲、家計への負担などのバランスを考慮して、のことのようですが・・・
次の記事は「インフレ率2%の秘密――なぜ世界中の中央銀行がこだわるのか」に関してみていきましょう。
FAQ(5問)
Q1: インフレとは何ですか?
A1: 物価が上がり、お金の価値が下がる現象です。
Q2: 日本はなぜ長くデフレだったのですか?
A2: バブル崩壊後、需要不足と企業の賃金抑制で物価が上がらなかったためです。
Q3: 円貯金はなぜ危険なのですか?
A3: インフレ下では円の購買力が減り、実質的な価値が目減りするからです。
Q4: 1925年の100円は今どのくらいの価値ですか?
A4: 名目は100円ですが、購買力では数十万円相当が失われています。
Q5: 株式投資はインフレに強いですか?
A5: 長期的には企業の成長と配当で、インフレを上回るリターンを生みやすいです。
E-E-A-T開示
私は医師として臨床に携わる一方、社会とお金の構造に強い関心を持ち、本記事を書いています。金融の専門家ではありませんので、最新の一次情報の確認を推奨します。
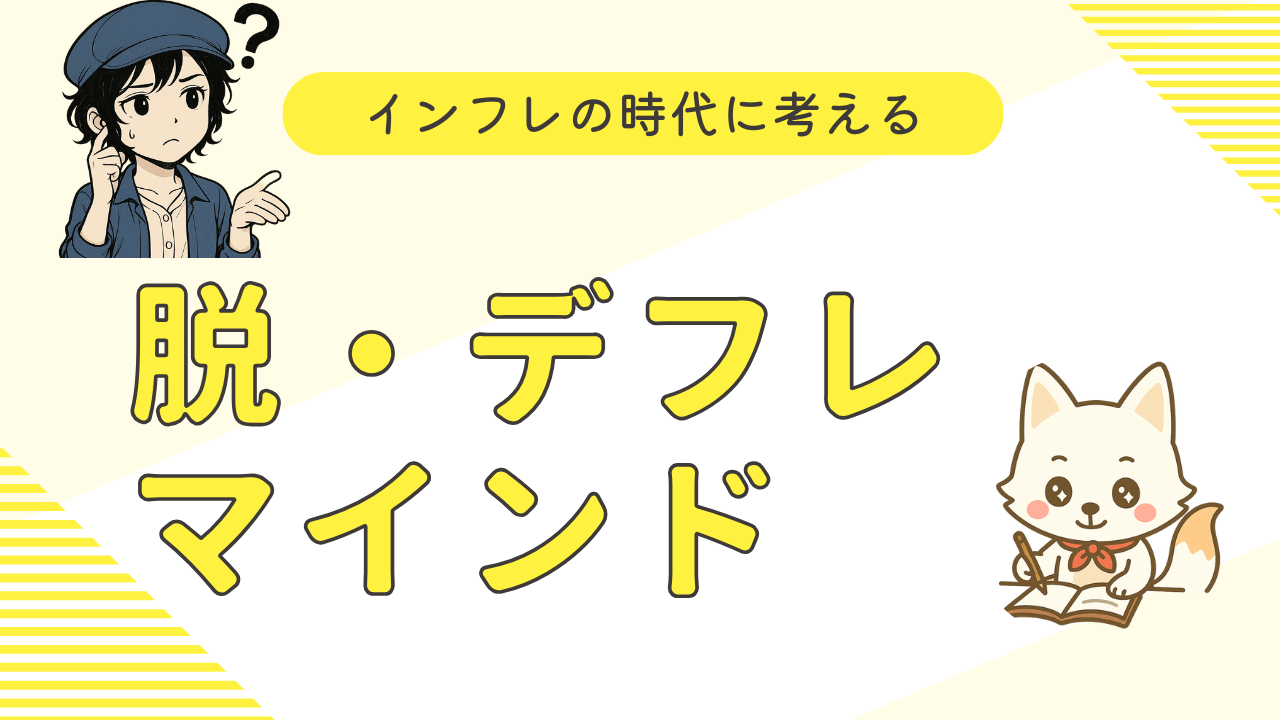

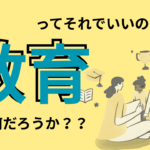
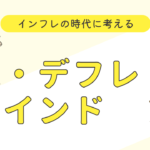
コメント