日本衰退のキーワードである「派遣社員」
この言葉を聞くと思い出すのは
「ハケンの品格」というドラマ
『ハケンの品格』というドラマがあることを、
私は長らく知ってはいたものの、
実際に観たことはありませんでした。
ただ、そのタイトルがやけに耳に残る。
「品格」
――なにやら正義を感じさせる言葉です。
そして「ハケン」、つまり派遣社員。
派遣という働き方が広まり、
日本社会がじわじわと変わっていったあの時代。
そして最近、ふとしたきっかけで、
小泉孝太郎氏が出演していたことを知り、
なんとも言えない皮肉を感じました。
親は規制緩和の旗を振り、
子はその制度のもとで描かれる物語に登場する。
偶然と言えばそれまでですが、
こうした“符合”のような現象には、
どうしても意味を見出したくなるものです。
派遣という制度、その“始まりの物語”
派遣制度の本格的な普及は、
1990年代から2000年代にかけての日本の構造改革期に端を発します。
バブル崩壊後の不況。
企業の生き残り策として、人件費の柔軟化が求められ、
そこに投入されたのが“非正規雇用”という便利な仕組み。
小泉政権が進めた労働市場の自由化は、
まさにこの波に乗る形で制度化されていきました。
そして、この制度の定着を“物語”として受け入れやすくするために登場したのが、
『ハケンの品格』のような作品だったのではないか。
もちろん、ドラマはドラマです。
娯楽であり、フィクションであり、直接的な政策プロパガンダではない。
でも、時代に沿って描かれたフィクションは、時として“現実の補完装置”として働きます。
美化された個と、語られぬ制度の影
派遣社員が、正社員以上に有能で、自立していて、何にも縛られず、格好よく働いている。
そんな描写を通じて、
「派遣だって輝ける」「正社員じゃなくてもいいじゃない」という空気が、
知らず知らずのうちに社会に広がっていく。
これは、ある種の“希望の物語”でもある一方で、制度の持つ本質的な問題
――不安定さ、権利の欠如、キャリア形成の困難さ――
を覆い隠す装置としても働き得る。
そして、こうした物語に親和性が高いのが、
“改革”を掲げた政治とメディアの関係です。
構造改革で得をするのは誰か。
制度が変わることで負担を背負うのは誰か。
物語が光を当てる“個人の成功”の背後には、
声を失った無数の“その他大勢”がいるということを、
私たちは忘れてはいけないのだと思います。
エンタメに込められた“時代の匂い”
『ハケンの品格』というドラマを、私はいまも観ていません。
だからこそ、逆に自由に語れるのかもしれません。
観ていたら、登場人物に感情移入して、描かれる物語に共感し、
制度の影を見落としていたかもしれない。
この物語の中で、小泉孝太郎氏が登場していたというのは、
あくまで俳優としての出演に過ぎない。
けれども、その父が推し進めた派遣制度の中で、
息子が役を演じるという構図は、
どうしても示唆的に思えてなりません。
制度を物語が浸透させ、メディアが空気をつくる。
そんな循環が、この国には確かに存在していたように思います。
おわりに:物語の奥に制度を見る目を
制度の問題は、とかく“難しい”と思われがちです。
でも、その制度が私たちの働き方や生活の安定、
ひいては人間関係にまで影響を与える以上、
それを理解しようとする姿勢は不可欠です。
そして、その制度がどのように社会に受け入れられ、
正当化されていくか。
その過程で、物語やエンタメが果たす役割を見抜くことも、
またリテラシーのひとつだと思うのです。
『ハケンの品格』は、良質なドラマだったかもしれない。
でも、だからこそ、その背景にある“時代の設計図”を一緒に読み解く目を持ちたい。
制度が語られぬまま、
美徳だけが残る時代。
その先に何があるのか。
私たちは、物語の感動と現実の構造の間にある距離を、
少しずつ測っていく必要があるのかもしれません。
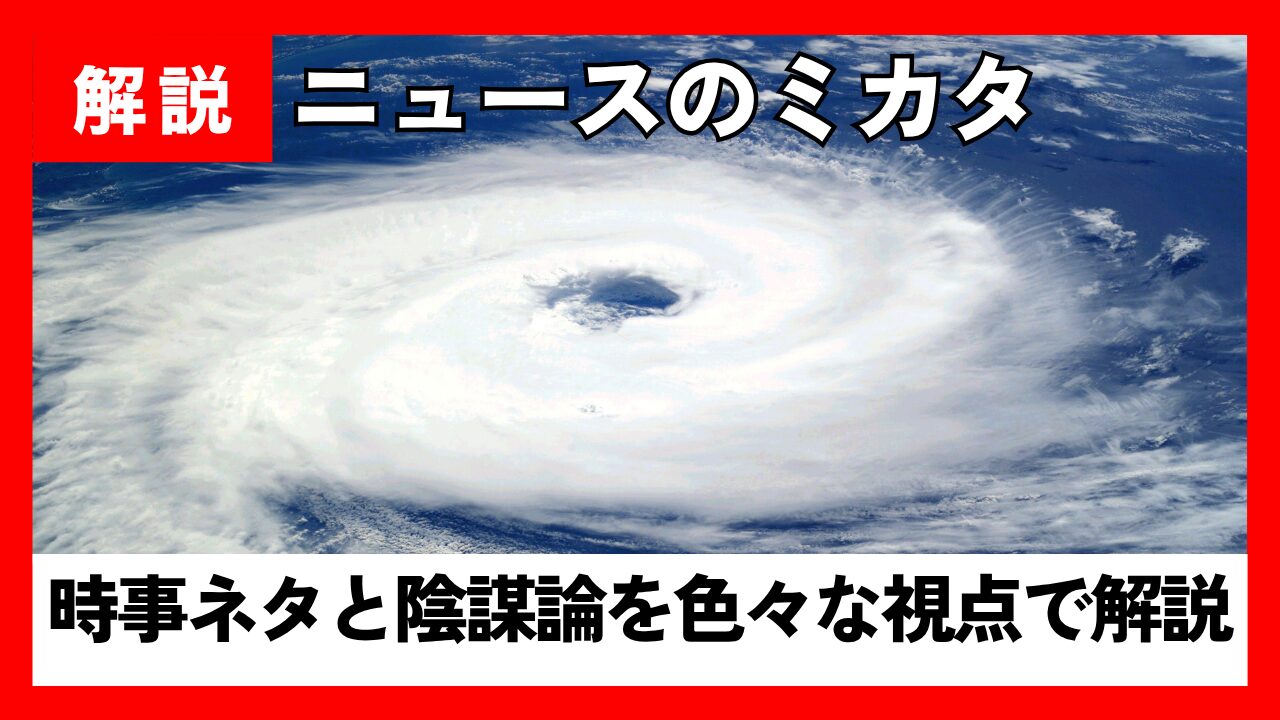



コメント