食は命の源。だからこそ「食育」が未来をつくる

食は、健康、医療、農業、さらには生き方や価値観にまで深く関わる、私たち人間の根幹をなすものです。
しかしこの「食」が今、さまざまな側面から脅かされています。
私たちの食卓は、知らず知らずのうちに欧米化され、安くて手軽でおいしいものが主流となりました。
しかしその代償として、健康被害や農業の衰退、食の安全性の問題など、多くのリスクをはらんでいます。
一見、個人の選択のようでいて、実は「国の根幹」に関わる分野でもあります。
食の支配は、サイレントインベージョン(静かな侵略)とも呼ばれ、国家の独立性すら脅かすことがあります。
この問題を根本から変えるためには、まず一人ひとりが「食に関心を持つこと」が出発点になります。
病気はどこからやってくるのか?その根本に「食」がある
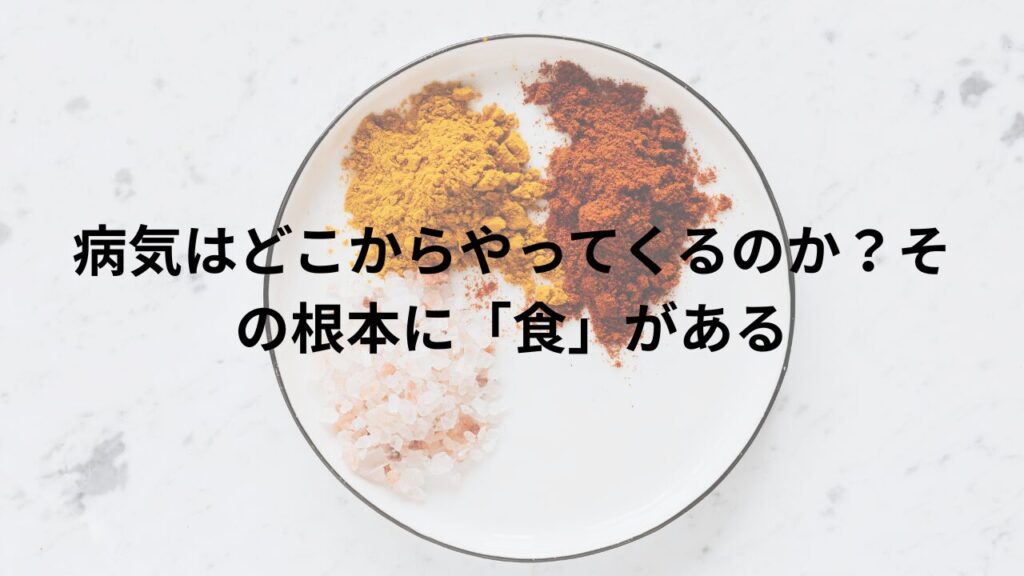
なぜ病気になるのか。なぜ体調が優れないのか。
それを考えると、行き着く先にはやはり「日々の食生活」があります。
例えば、低所得層ほど高カロリーで栄養バランスに欠けた食事を摂る傾向があり、肥満や生活習慣病のリスクが高くなるというデータもあります。
メキシコの一部地域では、子どもが2歳からコーラを飲み、1日2L消費することも珍しくありません。その結果として、肥満や糖尿病のリスクが急増しているにも関わらず、住民は無関心なケースも多いのです。
まずは「関心を持つ」こと。
「何を食べているのか」「それは誰のためなのか」——そこに目を向けることが、変化の第一歩です。
石塚左玄に学ぶ、食育の原点
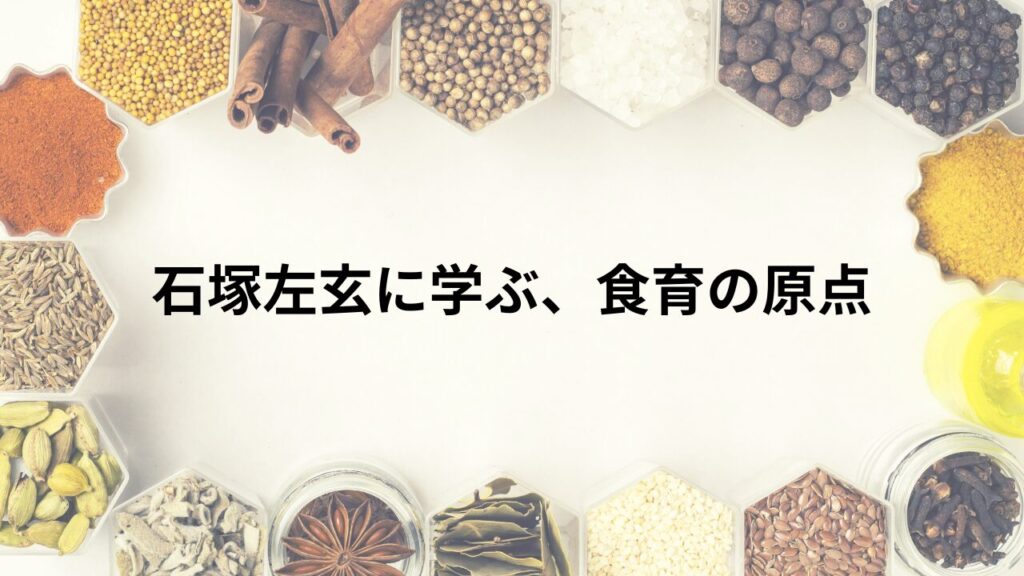
「食育」という言葉を生んだ人物、それが**石塚左玄(いしづか・さげん)**です。
彼は明治時代の医師・薬剤師であり、1896年に著書『化学的食養長寿論』を発表し、以下のように語りました。
「学童を持つ人は、躰育も智育も才育もすべて食育にあると考えるべきである」
また、
「民族の伝統的食習慣を軽々しく変えるべきではない。各地の風土に合った食生活にこそ意味がある」
とも述べています。
左玄の教えは、のちにマクロビオティックとして世界に広まり、彼の弟子たちは仏教用語「身土不二(しんどふじ)」——身体と土地は一体である——という理念を掲げました。
石塚左玄の「食の六訓」

彼の教えの中でも有名な「食の六訓」は、現代に通じる本質を突いています。
- 家庭での食の重要性
- 命は食にあり
- 人間は雑食動物である
- 食べ物は丸ごと食べる
- 地産地消・旬のものを食べる
- バランスの良い食事をとる
これらは、現代の私たちにも必要不可欠な「食の基本」といえるでしょう。
現代の食卓に起こっていること

現在の日本の食卓はどうでしょうか?
「和食」は世界的に評価される健康的な食文化ですが、実際に日本人が日常的に食べている回数はどれくらいでしょう?
戦後、欧米化が進み、高脂肪・高糖質の食生活が一般化したことで、肥満や生活習慣病が増加しています。
「安くて、簡単で、うまい」は、私たちの体と社会にどんな代償をもたらすのでしょうか。
現代における食のリスクと責任

・小麦アレルギーやグルテン不耐症
・大量の食品添加物
・加工食品やファストフードの依存性
・価格重視の購買傾向
これらの問題の中で、大人は「選択の自由」を持っています。
しかし、その選択は子どもたちの「味覚」や「健康」に直結し、家庭の文化として次世代へと受け継がれていきます。
つまり、「大人が変わらなければ、子どもは変われない」のです。
我が家の「現代版・食の訓え」

私たちの家庭では、以下のような姿勢で日々の食事と向き合っています。
石塚左玄の六訓をベースにした実践:
- 家族で一緒に食卓を囲む
- 「いただきます」に感謝の心を込める
- 食物繊維を多く取り、米や根菜を中心に
- 丸ごと食べられる調理(蒸す、煮る)を工夫
- 季節のものを楽しむ
- 彩りバランスを意識した献立
現代版・追加訓え:
- 食品添加物に関するリテラシーを高める
- 本物の調味料を選ぶ
- 外食の頻度を見直し、質の高い外食を楽しむ
最後に:食育は、未来を守るという選択

食育とは単なる「栄養教育」ではなく、未来の社会や文化を守るための行動です。
病気になってから薬で治すのではなく、「病気を防ぐための食」に意識を向けましょう。
子どもたちの未来のためにも、大人が今できることを始めていきたいと思います。
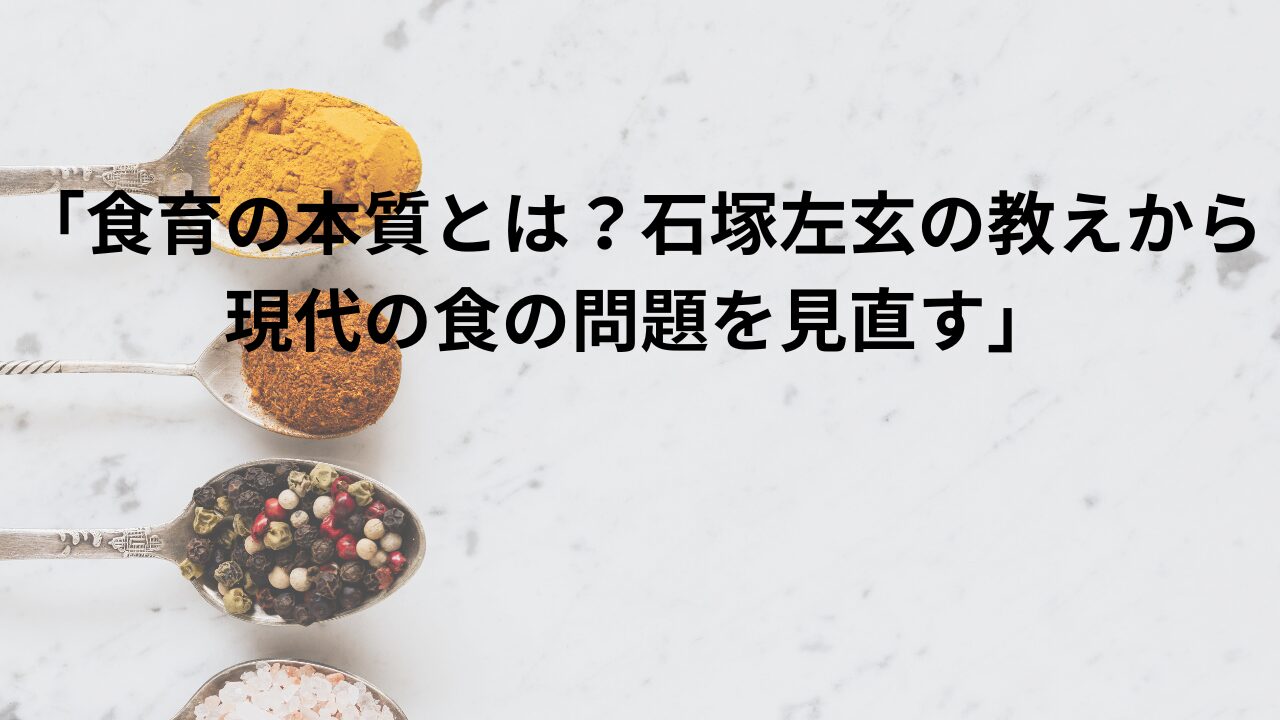

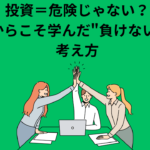

コメント