参院選が盛り上がっていますね。自分もSNSを通じて興味のある話に耳を傾けています。無所属連合のつじ健太郎候補が演説で語った「ベーシックインカム」。この言葉の裏には、貨幣の本質や資本主義の構造的課題、そして私たちが生きる上で避けては通れない”お金”に関する深い問いが潜んでいます。
この記事では、ベーシックインカムを入り口に、「信用創造」や「r > g」という経済の核心に迫りつつ、現代社会で私たちがどう生きるべきかについて考察します。
小難しい話かもしれませんが、これを理解しないと世の中の構造がわからず、いつまでたっても「労働するだけ」の人生から抜け出せません。是非、この記事をきっかけに興味を持って自分でも調べる、考えるを実行してください。
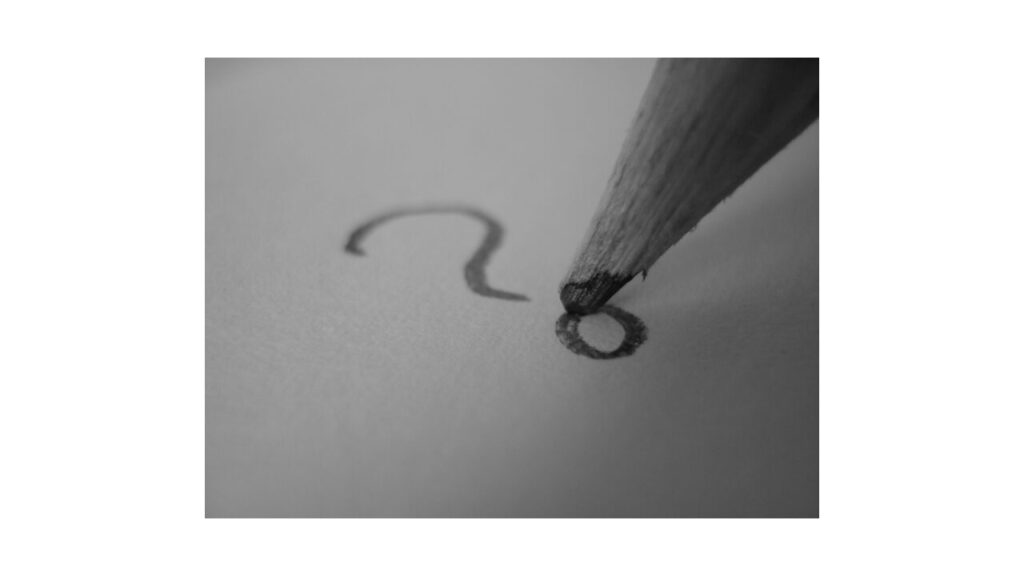
こんな人におすすめしたい
- 現代の経済構造に違和感や疑問を感じている人
- 資本主義のルールを理解し、自分の人生に活かしたいと考える人
- お金や投資に興味はあるけど、仕組みがよくわからないと感じている初心者
- 政治家の「ベーシックインカム」発言の本質を深く理解したい有権者
- r>gの不等号が示す意味に興味を持った知的好奇心の高い読者
- 自分や家族の未来の生活を守るために「r側」に立ちたいと考えている人
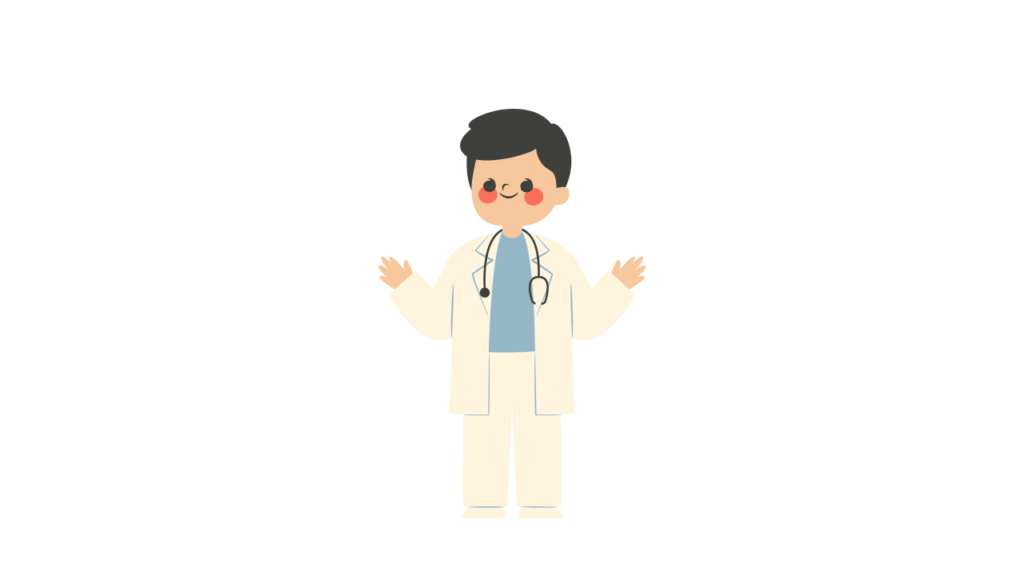
第1章:銀行はなぜ”存在しないお金”を貸せるのか? — 信用創造の正体
銀行が企業に1億円を貸す時、実際には現金を渡すわけではありません。企業の口座に「1億円」と数字を記帳するだけ。これが現代の通貨創造、つまり信用創造です。
かつては銀行が保有するゴールド(貴金属)を裏付けに紙幣を発行していました。これが金本位制です。しかし、現代では金などの実物資産を持たずとも、銀行が貸し出せる仕組みになっています。これは「お金=信用」という考え方のもとで成り立っており、通貨は誰かの借金によって初めて創造されるのです。
大事なことなのでもう一度言います。
「通貨は誰かの借金によって初めて創造される」
この仕組みによって市場に出回るお金は拡大し、経済活動が活性化するのです。しかし、注意が必要なのは、返済が前提となっているため、利子分も含めて回収される設計になっていること。これが経済格差や景気循環の源でもあります。
第2章:金本位制からの脱却 — 無限にお金を想像できる時代

1971年、ニクソン・ショックによりアメリカは金とドルの兌換を停止し、世界は**管理通貨制度(fiat currency)**に移行しました。これは、国家や中央銀行の「信用」さえあれば通貨が成立するという考えです。
つまり、お金の発行量には実質的な制限がなくなったということ。政府は通貨を発行し、財政政策として市場に供給できるようになったわけです。この点をベースに現代貨幣理論(MMT)も議論されるようになりました。
ただし、ここで問題となるのがインフレ。市場に過剰な通貨が流れると、物価が上昇し庶民の生活が苦しくなります。しかし、現在の日本のようにインフレがなかなか起きない状況は、むしろお金が一部の資本家の間でしか動いていない、つまり信用創造によるお金が実体経済にまで届いていないことを示しているとも言えます。
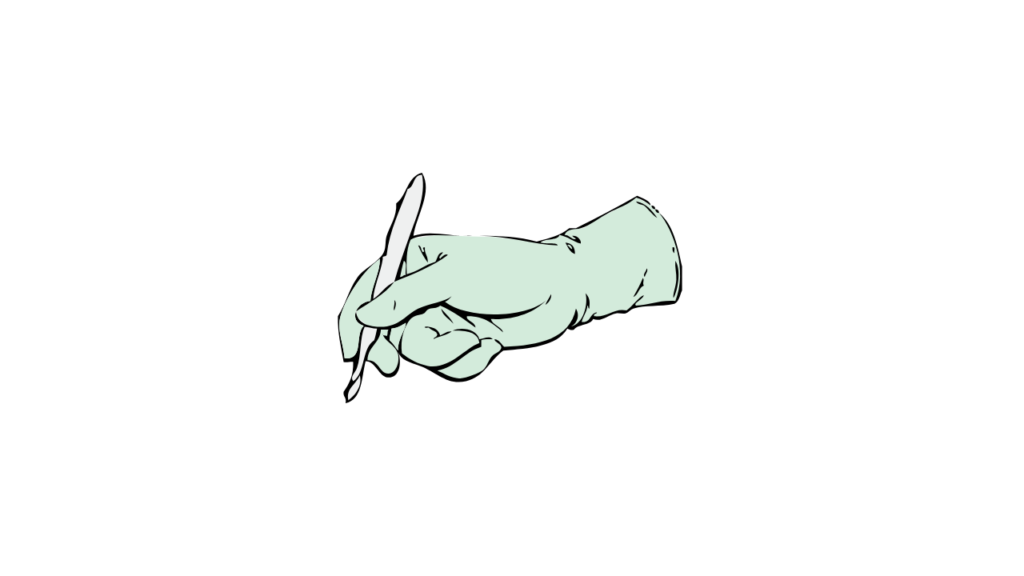
大事なことなのでもう一度言います
国は実物資産がなくても貨幣を発行できるようになった。言うなれば無限にお金をすることができる。
ただしインフレが問題となる。
つまり日本が30年間インフレが起きなかったのは、簡単に言えば一部の人間が「ガメている」ということ。
第3章:r > gの不等号 — 資本主義社会の構造的な不平等

トマ・ピケティが著書『21世紀の資本』で示した「r > g」という不等号。
- r:資本収益率(資産から得られるリターン)
- g:経済成長率(労働所得やGDPの成長)
この不等式が意味するのは、資本家の方が労働者よりも早く豊かになっていくという構造です。
これはまさに、信用創造されたお金が企業や富裕層(r側)に集中し、労働者や消費者(g側)には回ってこないという実態を示しているとも言えます。r > gの構造が続けば続くほど、格差は広がり、実体経済は冷え込み、インフレは起きにくくなるのです。
第4章:もしr = gになったら? — インフレが起こる世界

ここで逆説的な仮説を立ててみましょう。もし、rとgが等しくなったら?
r = gとは、労働者の賃金上昇率と資本収益率が同じになる社会です。これは理想的な平等のようにも思えますが、実は非常に強いインフレ圧力を生みます。すべての人にお金が行き渡れば、消費が加速し、物価は上昇します。
つまり、r > gの不等号は、単に不平等を象徴しているだけでなく、インフレを抑える一種のブレーキ装置としても機能している側面があるのです。これは、労働者を抑圧する構造であると同時に、社会の暴走を防ぐための均衡でもある。

大事なことなのでもう一度言います。
誰かが富をガメているからけしからん、というわけですが
大事なのはそこではなくて、だからこそインフレが起きないという側面があるということ
物事には常に2面性があるということです
第5章:ベーシックインカムはr > gの是正になるのか?
ベーシックインカム(BI)は、g側の生活基盤を安定させ、格差を是正する政策として注目されています。BIの財源には様々な提案がありますが、重要なのは「r側」からの再分配です。
- 富裕層への課税
- 金融取引税
- MMT的な通貨発行
これにより、g側にお金が流れ、rとgの差が縮まる可能性があります。ただし、やり方を間違えると、過度なインフレやモラルハザードのリスクもあります。
結論:だからこそr側に立つしかない
資本主義がこの構造を変えない限り、我々ができることは限られています。
- 労働だけに頼らず、投資や資産運用を始める
- 消費者から生産者・保有者への視点転換
- 教育によって”お金のルール”を学び、r側の立場を理解する
つまり、「資本主義というゲームのルールが不平等だからこそ、そのルールを理解し、味方につけるしかない」のです。
これは逃避ではなく、主体的な選択です。私たちはr側に立ち、同時にg側の人間としても尊厳を持って生きる。その二面性を受け入れることが、これからの時代を生き抜く知恵なのです。
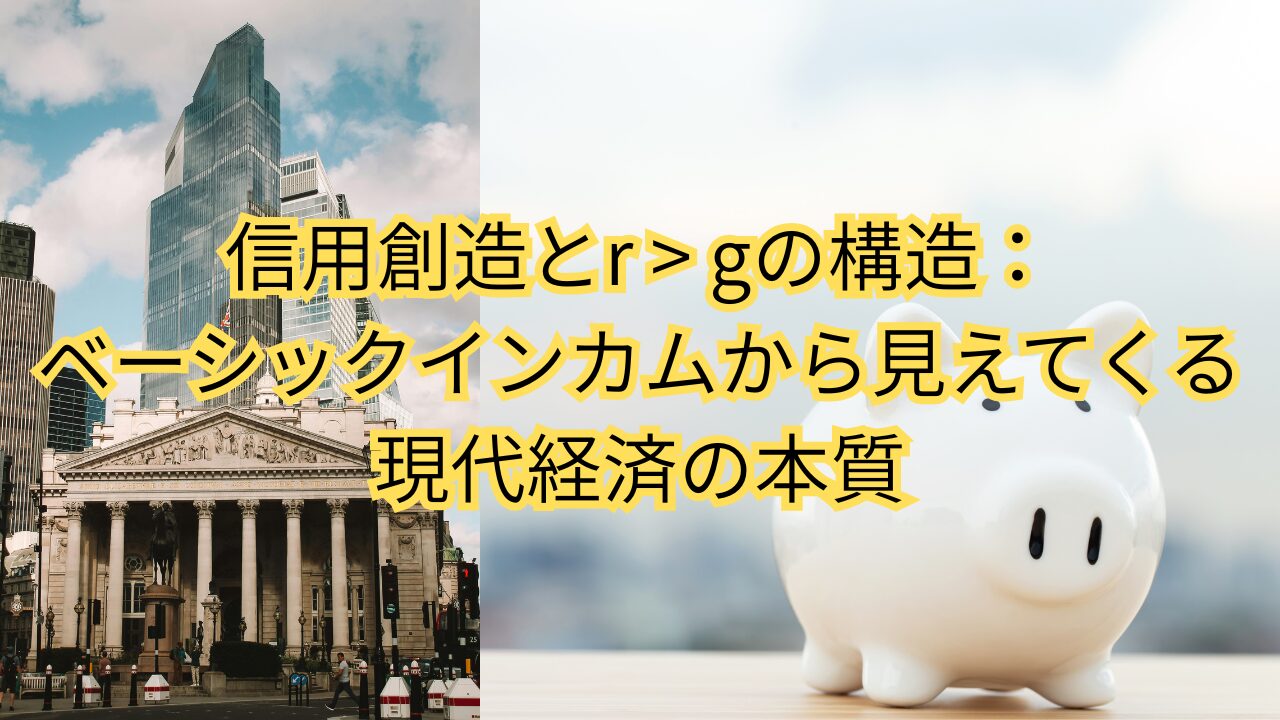

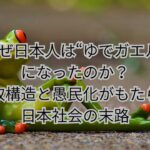
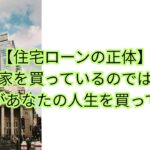
コメント