街を歩いていると、不思議な感覚にとらわれます。
高級マンションの広告は華やかに並び、
株式市場は歴史的な高値を更新し続けているのに、
私たち一人ひとりの財布はどこか寒々しい。
どうしてこんなにお金が世の中に溢れているのに、
自分の暮らしは一向に楽にならないのだろうか。
この問いは、単なる愚痴ではなく、
現代日本の「構造」に突きつけられた根本的な矛盾だと思います。
所得が上がらない理由を一つずつほどく
第一に、生産性の問題。
日本人はよく働くのに、効率や付加価値を生み出す力が他国に比べて伸びていない。
長時間働いても「賃金が上がらない」
という不思議な現象は、実はここに原因があります。
第二に、雇用の二重構造。
非正規雇用が増えた結果、
平均賃金は押し下げられました。
正規と非正規の間には大きな溝があり、
その溝は年々深まっています。
第三に、年功序列と内部留保。
企業はリスクを嫌い、利益を従業員に分配するよりも、
内部にため込みがちです。
株主や資本市場には利益が回るのに、
社員には「据え置き」。
この構造が、私たちの生活感覚と「数字上の景気」の間にギャップを生んでいるのです。
「お金の意図」を見抜く
お金は存在しているのに、自分のところに来ない。
これは「分配の意図」が働いているからです。
資本に厚く、労働に薄く。
そうした流れが制度によって固定化されている。
税制、雇用制度、為替政策
――どれも無意識のうちに、あるいは意識的に「お金の流れ」を決めています。
もちろん、そこには利害がある。
企業にとって、政府にとって、資本市場にとって都合のよい流れが作られてきた。
その中で私たちの所得は、後回しにされてきたのかもしれません。
それでも「豊かさ」を取り戻すには
では、どうすればよいのか。
簡単ではありませんが、道はあります。
企業は成果や役割に応じた賃金体系を取り入れるべきでしょうし、
政府は再分配や中小企業支援をもっと強める必要があります。
私たち個人も、ただ「給料が上がらない」と嘆くだけでなく、
自ら学び、交渉し、声をあげることが求められているのだと思います。
「日本人は勤勉なのに貧しい」と言われて久しい。
けれど、その勤勉さを新しい形で活かすことができれば、
もう一度「豊かさ」を感じられる国になるはずです。
余白としての問いかけ
結局のところ、豊かさとは数字だけでは測れないものです。
賃金が上がっても、心が貧しければ意味はありません。
しかし、働く人々に正当に報いる社会でなければ、人は希望を持てません。
私たちが問うべきは、単なる経済の成長ではなく、
「誰のために成長させるのか」という意図なのだと思います。
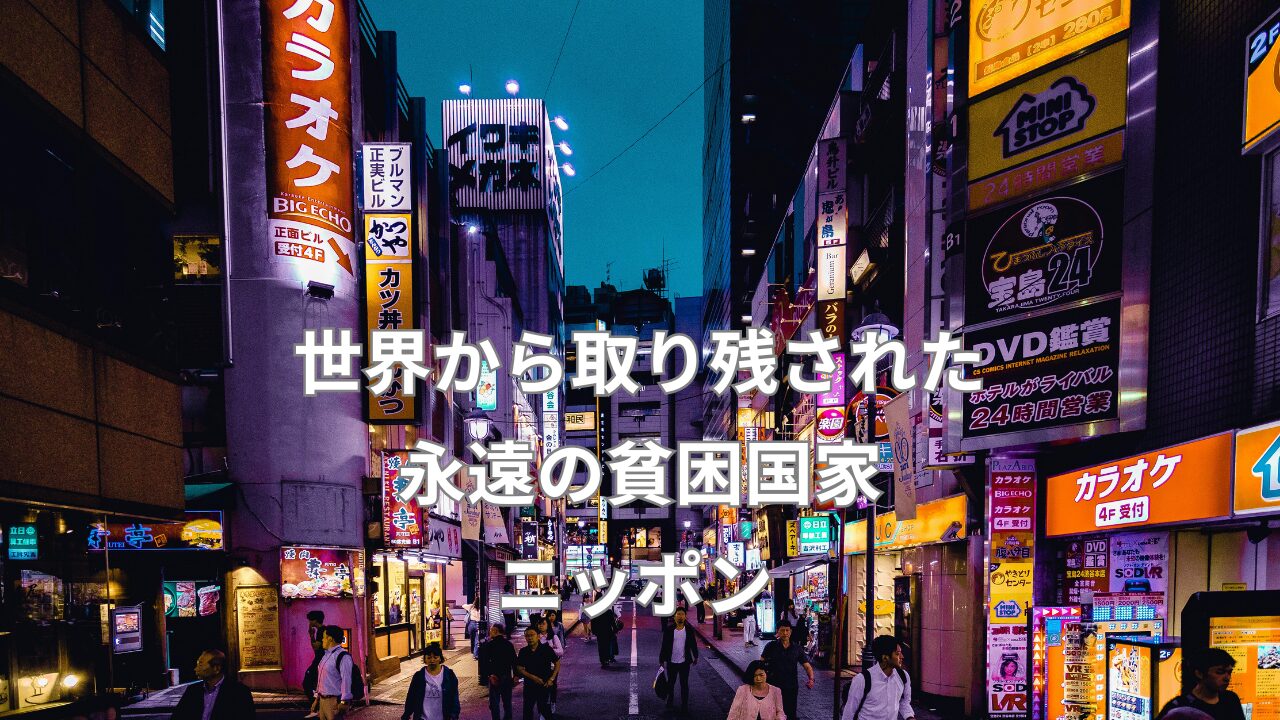

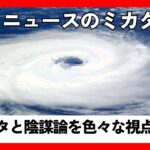

コメント