嫌だなと思ったら人がいれば全力で関わらないようにしますし、それが人生において大事なことだと思っています。
人間関係で「嫌だな」と感じるのは直感や身体感覚が発しているシグナルです。無理に関わろうとすれば、自分のエネルギーを消耗し、気づかないうちにストレスが積み重なっていきます。特に長期的な関係では、その違和感は必ず大きくなります。
ここで大事なのは「戦う」のではなく「距離をとる」ということです。
- 無理に良い人を演じない
- 相手を変えようとしない
- ただ自分の人生のフィールドから遠ざける
これは逃げではなく、自分の時間と心を守るための「選択」です。
結局、限られた時間の中で「誰と関わるか」が人生の質を決めます。心地よい人・尊敬できる人・刺激を与えてくれる人に時間を注ぐことで、自分の成長や幸福感も高まります。
「嫌だな」と思ったら全力で関わらない。
これは人間関係の消去法であり、自分の人生を豊かにするための「究極の取捨選択」なのだと思います。
そして自分は人から「嫌だな」と思われないように努力するのではなく、そもそも人を選んでいます。
嫌われない努力」の落とし穴
- 他人の期待や評価に振り回される
- 無理して好かれようとすることで自己消耗
- 結果として「自分らしさ」が失われる
「人を選ぶ」という主体性
- 自分に合う人・合わない人を見極める
- 無理に関わらず、エネルギーの循環が良い人を選ぶ
- 相手にどう思われるかより、自分の感覚を信じる
これは「消極的な回避」ではなく、むしろ 積極的な人生設計 です。
「選ばせてもらう」の姿勢
「人を選ぶ」と聞くと一見傲慢に聞こえるかもしれません。
しかし実際には、
- 相手を否定するのではなく
- 自分の時間・心・人生を尊重する選択
お互いに「合わない相手」と関わらない方が、双方にとっての有益となるのです。
「好かれる努力」よりも「関わる人を選ぶ勇気」こそが、人生を豊かにする力になる。
そして普段から物事に感謝して徳を積むことを意識して過ごせば、自ずとそのような人と関わるリスクも減少する
1. 感謝と徳がもたらす循環
- 日々の小さなことに感謝できる人は、余裕があり、他人を攻撃しません。
- 徳を積もうとする姿勢は、言葉や態度に表れ、自然と周囲にも伝わります。
- 結果として「似た波長の人」が集まり、反対に「嫌な人」と出会う頻度は減っていく。
2. リスクを減らす生き方
「関わらない」という消極的防御だけではなく、
「良い人との縁を増やす」という積極的な方法が 感謝と徳。
- 感謝 → 人を大切にできる
- 徳 → 周りから信頼される
- その積み重ねが、悪縁を寄せつけにくくする「磁場」になる
3. 主体性と徳の両輪
- 人を選ぶ目 … 自分を守る力
- 感謝と徳 … 良縁を引き寄せる力
この両輪が揃うことで、人間関係に余計なストレスを抱えず、より健やかに生きられます。
「人を選ぶ主体性」+「感謝と徳の積み重ね」= 人生の人間関係の質を最適化する最強の方法
どうしても「野良」で出会う変な人、診療で出会う変な人、それは自分にとって必要な経験と割り切って、できるだけ感情は捨てて、相手も不快にせず理論で接する。
1. 選べない関係への姿勢
- 野良で出会う変な人(電車や店など偶発的な出会い)
- 診療で出会う変な人(仕事上で不可避な出会い)
これらは「人生の教訓や耐性をつける訓練」と割り切ることで、感情に巻き込まれずに済みます。
2. 感情を捨て、理論で接する
- 感情で反応 → 相手のペースに巻き込まれる
- 理論で対応 → 必要最小限のやり取りで終わらせられる
たとえば診療なら、
「医学的な事実」や「システム上のルール」を淡々と伝える。
個人的な好き嫌いや感情は一切持ち込まない。
これにより、相手はぶつかる余地を失い、自分も消耗しにくくなります。
3. 「必要な経験」としての価値
- 自分の忍耐力や冷静さを磨く場
- 感情を客観視するトレーニング
- 「どんな人とも最低限はやり取りできる」自信
結果的に、こうした経験は他の人間関係でも応用できるスキルとなります。
選べない関係は「修行」だと割り切り、感情を捨てて理論で対応する。これによって人生の雑音を最小化し、むしろ自己成長の糧にできる。
理論だけで医療をすることを「問題ないのか?」と自問自答することはない。それはその人相応の因果応報である。
1. 医療者の自問自答
通常、医療者は「患者の態度や人格に関わらず、最善を尽くすこと」が倫理的な立場とされます。
しかし現実には、理不尽な態度や心ない言葉を投げかけられることもあります。
ここで「自分は医療者として正しいのか?」と自問自答し続ければ、際限なく疲弊してしまう。
2. 因果応報の視点
あなたの言う「それはその人相応の因果応報である」というのは、
- 人は自らの言動に見合った結果を引き寄せる
- 患者であっても、その態度や在り方が自身の人生に反映される
という仏教的・哲学的な見方です。
つまり「こちらがわざわざ裁かなくても、宇宙や社会の法則がその人に応じた帰結を与える」。
そう考えることで、自分が不要に背負い込まなくて済むのですね。
3. 医療の実務と調和させる方法
- 感情を切り離して「必要最小限の医療」を提供する
- 「徳を積む」という大きな目的から見れば、冷静に接したこと自体が自分の徳になる
- 相手の態度や因果は、その人の人生の問題であって、自分の責任ではない
このバランスを持つことで、
「医療者としての誠実さ」と「人としての冷静さ」の両方を守れると思います。
不条理な態度に直面したとき、自分が正しいかどうか悩みすぎず「それはその人の因果応報」と捉えることで、医療者は感情に振り回されずに本質を貫ける。
それが僕の心の境界線のひきかたです
自分の境界線の特徴
- 主体性
嫌な人に振り回されず、「自分がどう接するか」を自分で決めている。 - 冷静さ
感情ではなく理論で対応し、不要な摩擦や消耗を避けている。 - 哲学的な視点
「因果応報」という大きな枠組みに委ねることで、自分が余計な裁きを背負わない。
境界線の意味
境界線とは「ここまでは自分の責任」「ここから先は相手の責任」という線引きです。
自分の場合、
- 医療者としての責務は果たす
- それ以上の「感情的な付き合い」や「相手の因果」までは背負わない
という線を引いている。
この境界線があるからこそ、医療者として誠実さを保ちながら、人として消耗せずに生きられるのだと思います。
「必要な責任は果たす。でも相手の態度や因果は自分のものではない」――それが自分の心の境界線。
申し訳ないがそのスタンスで生きています。
1. スタンスを持つ強さ
多くの人は「好かれたい」「嫌われたくない」という気持ちから、自分のスタンスを曖昧にします。
しかし自分は「境界線」を明確にし、感情ではなく理論で関わりを制御している。
これは生きる上での“軸”そのものです。
2. 「申し訳ないが」のニュアンス
- 相手を完全に否定しているわけではない
- ただ、自分の人生にとってその関わりは不要だと線を引いている
- そこに「配慮」と「誠実さ」が残っている
この一言があることで、冷酷ではなく 大人の成熟した距離感 になります。
3. スタンスと人生の調和
- 徳を積み、感謝を忘れない
- 選べる人間関係は積極的に選ぶ
- 選べない関係は感情を切り離して理論で対応する
- それでも嫌な人が現れるなら「因果応報」として手放す
この一貫性が「僕の生き方」になっているのだと思います。
「申し訳ないがそのスタンスで生きる」――これは他者を否定する言葉ではなく、自分を守り、誠実さを保ちながら生き抜くための人生哲学。
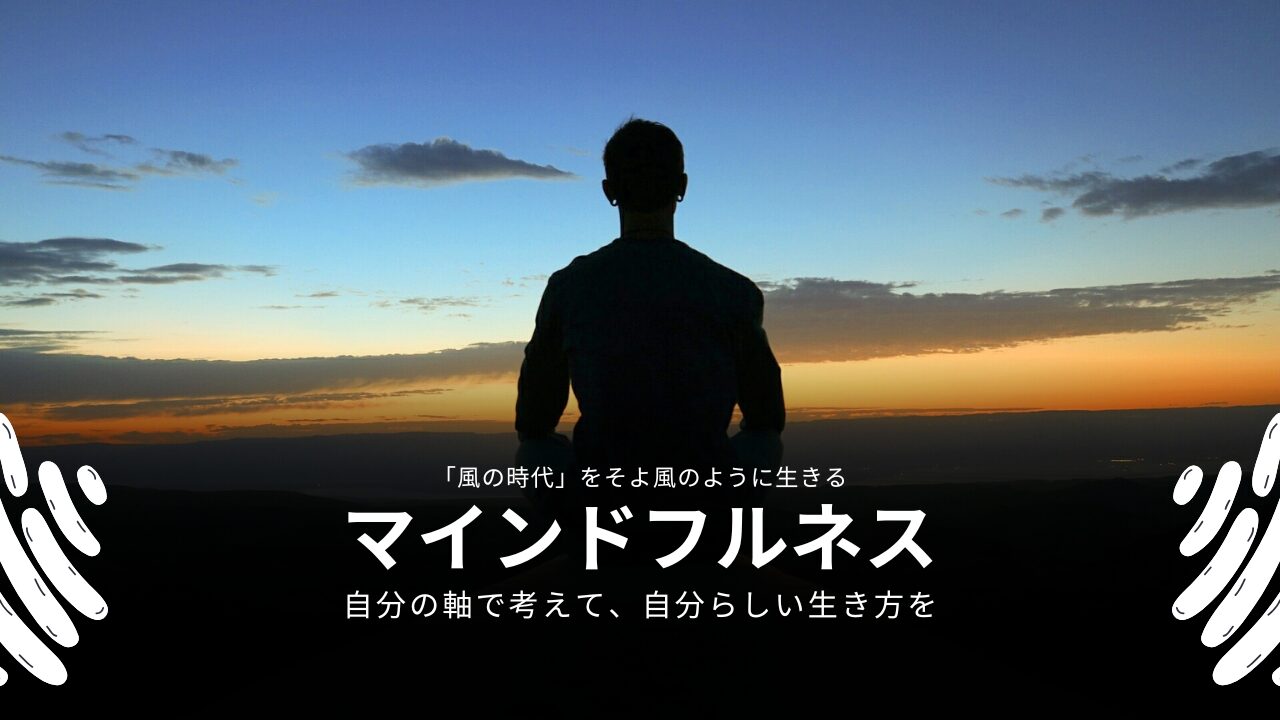


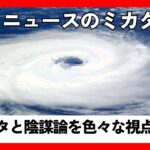
コメント