これまで、私は「時間に縛られる人間、解き放たれる人間」から始まり、仏教的な時間観、死生観、そしてお金との関係を語ってきました。
最終章では、この三つに「権力」という要素を加え、社会構造の奥に潜む意図まで見ていきます。
権力は時間を支配しようとする
歴史を振り返れば、権力者は常に「時間」を支配してきました。
暦を作ること、時刻を定めることは、人々の生活のリズムと生産活動を管理する手段でした。農耕社会の太陰暦、産業革命の工場の時鐘、現代のシフト制――時間の管理は権力の管理でもあります。
現代では、この「時間の支配」はもっと見えにくくなりました。働く時間、休む時間、老後の時間――その配分は法律や経済システム、教育制度によって間接的に決められています。私たちは、気づかぬうちに「時間の使い方」を奪われているのです。
お金は時間を売買する通貨
お金は、時間を取引するための通貨です。
時給や日給という形で、私たちは自分の時間を市場に差し出し、その代価としてお金を受け取ります。企業はその時間を集め、商品やサービスを生み出して利益を得ます。
しかし、この構造の中で「死」が抜け落ちると、時間は無限に売れるものと錯覚されます。現実には、私たちの持つ時間は有限であり、権力と市場はこの有限性をできるだけ意識させないように仕組まれているのです。
死は権力の外にある
どれほど権力やお金を持つ者でも、死を避けることはできません。
だからこそ、死は権力の外にある最後の領域です。しかし、現代社会はこの領域すら管理しようとします。医療制度による延命、終末期医療の選択、死の場を病院に集中させる構造――これらは死の形を制度的に統制する試みです。
死が個人の内面的な問題であると同時に、社会的に管理される現象になったとき、私たちは「自分の死」を自分のものとして生きにくくなります。
死生観を持つことは抵抗である
権力と市場が時間を管理し、お金で時間を売買する社会の中で、死を直視し、自分の死生観を確立することは小さくも深い抵抗になります。
なぜなら、死を意識することは、「本当に使いたい時間」を自ら選び取ることだからです。
仏教の無常観は、権力やお金の枠組みを超えて、時間を自分のものとして生きるための思想的武器になります。無常と縁起を理解すれば、「社会が決めた時間の使い方」に無自覚に従う必要はなくなります。
まとめ
権力は時間を管理し、市場はその時間をお金に換え、私たちは死を忘れたまま時間を切り売りして生きています。
しかし、死を見据え、自分なりの死生観を持てば、時間もお金も社会の都合ではなく、自分の意志で使うことができます。
この世界を動かす四つの力――権力・お金・時間・死。その中で唯一、絶対に奪われないのは、自分が「どう死ぬか」「どう生きるか」を決める自由です。
それを守るためにこそ、時間と死生観を自覚することが、現代人にとっての最大の防衛策なのです。
FAQ
- Q権力が時間を管理するとはどういう意味ですか?
- A
暦や労働時間など、生活の時間配分を制度や仕組みで支配することです。
- Qお金と時間はどうつながっていますか?
- A
労働によって時間をお金に換える構造が社会経済の基盤になっています。
- Q死は権力から自由なのですか?
- A
死そのものは自由ですが、その形や場は制度により管理されることがあります。
- Q死生観を持つことが抵抗になる理由は?
- A
社会が決めた時間の使い方ではなく、自分の意志で生き方を選べるからです。
- Q仏教思想はこの構造にどう役立ちますか?
- A
無常と縁起の理解は、時間と死を自分のものとして捉え直す力になります。


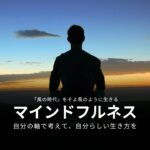
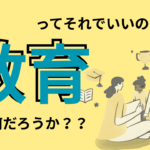
コメント