本質を考える医師です

ここでは、FRBをはじめとした中央銀行と、BIS(国際決済銀行)、IMF(国際通貨基金)、世界銀行などの国際金融組織との繋がりを、分かりやすく整理して解説します。
◆ 国際金融組織と中央銀行の構図(概要)
| 組織名 | 主な役割 | 中央銀行との関係 |
|---|---|---|
| BIS(国際決済銀行) | 「中央銀行の中央銀行」 各国中銀の連携・国際決済の調整・情報共有を担う | FRB、日銀、ECBなど主要中銀が株主として参加し、政策調整や会議を行う。秘密主義が強い。 |
| IMF(国際通貨基金) | 通貨危機時の支援(融資)、各国の経済監視 | 中央銀行・財務省と連携して為替政策を誘導。 緊縮財政を条件とする「構造改革」が物議を醸す。 |
| 世界銀行(World Bank) | 発展途上国への融資・インフラ支援 | IMFと並び、米ドル体制の拡張に関与。米国の影響力が非常に強い。 |
◆ 1. BIS(国際決済銀行):中央銀行ネットワークの要
- 設立:1930年、スイス・バーゼル
当初はドイツの第一次大戦賠償金を管理する目的で設立された
現在は各国中央銀行の協調機関であり、年に数回、バーゼルで秘密会合が開かれている(「バーゼル会合」 - 構成:アメリカFRB、日本銀行、欧州中央銀行(ECB)などが加盟。各国の中銀総裁が定期的に集まる。
- ポイント:
✔ 中央銀行の通貨政策や金融安定の「すり合わせ」の場
✔ BISは一般的な国際機関とは違い、非常に閉鎖的・独立的。スイス法の下にあり、外部の監視が極めて困難。
✔ 各国通貨政策の背後に、BISでの合意形成があるという見方も存在する。
◆ 2. IMF(国際通貨基金):ドル体制の守護者
- 設立:1944年、ブレトン・ウッズ体制の一環
第二次大戦後の国際通貨安定のために設立。加盟国に資金を融通し、為替の安定や経済支援を担う。 - 実質的な権力構造:
✔ 米国の議決権が最大(16%以上)で、IMFの重要決定には85%以上の賛成が必要 → アメリカが拒否権を持つ。
✔ 各国の融資には「構造調整プログラム」として、緊縮政策・規制緩和・民営化などを条件とする(=主権制限)。 - 中央銀行との関係:
IMFは通貨安定を目的として、中央銀行の金融政策と密接に連携している。IMFの分析・指導は事実上、FRBやECBなど先進国の政策モデルに沿って行われる。
◆ 3. 世界銀行:経済発展と金融支配の両面性
- 目的:発展途上国へのインフラ融資・教育支援など。
- 実態:融資と引き換えに、グローバル企業の市場開放を条件とすることも多く、新自由主義的な影響力が指摘されている。
- 中央銀行との関係:表面上は薄いが、為替安定や財政政策の改革など、IMFと連携して進められる。
◆ これら国際組織の構図が示すもの
- 貨幣発行・金融政策の中核は、各国中央銀行(FRBなど)
- → それらを統合するのがBIS
- → 通貨危機時の調整を行うのがIMF
- → 発展途上国に金を貸し、世界の制度設計に介入するのが世界銀行
このネットワーク全体が、「国家」よりも上位の経済ガバナンス構造として機能していると見なすことができます。
◆ よく言われる「グローバル金融支配」のイメージ図(言葉で表現)
[IMF] ←金を貸して国家に条件を課す
↑
│
[BIS] ←中銀が集まり、金融政策を調整
↑
│
[FRB・ECB・日銀など] ←実際の金利・量的緩和を行う中枢
↑
│
[民間金融資本・投資銀行] ←ロスチャイルド系、J.P.モルガン、ブラックロック等
一昔前にギリシャ🇬🇷やアルゼンチン🇦🇷がデフォルト、デフォルトと騒がれていました
ぽかーん🤪と聞いていただけでしたが、少しづつこういった昔のニュースの重大さがわかるようになってきました。
**IMFによる「借金漬け戦略」や「国家の主権制限」の事例(ギリシャ、アルゼンチンなど)**についても深掘りしてみましょう

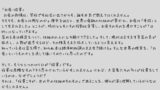


コメント