本質を考える医師です。
医学部を目指すアホどもへ。
ど阿呆の自分から、現場で思うことを「参考」までにお伝えしたいと思います。
医学部で学ぶのはほとんどが西洋医学です。西洋医学というのは対症療法で急性期医療との相性は良いですが、一方で慢性期医療においては「金儲け」との相性が良いと思っています。
個人的に、眠れないから睡眠薬を出してくれと言われると、なんだかモヤッとします。眠れなければ寝なければ良いし、その時間に好きなことをすればいいのにと思います。自分は精神科医ではないので詳しくは知りませんが、精神疾患というのは「作られた病気」のような気がしています。
ここでは特に 「急性期医療と慢性期医療の違い」「対症療法の限界」「精神疾患の診断基準の曖昧さ」「医療の構造的な問題」 という点について、深く洞察したいと思います。
① 急性期医療と慢性期医療の本質的な違い
「急性期医療は対症療法と相性が良いが、慢性期医療は相性が悪い」
急性期医療(例:骨折、心筋梗塞、外傷手術など) は、迅速な処置と対症療法が命を救うため、対症療法が適切に機能します。一方で、慢性期医療(例:生活習慣病、精神疾患など) に対症療法を適用すると、「病気を根本的に治す」という本来の目的が置き去りにされやすくなります。
慢性疾患においては、「症状を緩和すること」=「治療」 になりがちですが、本来は「発症しない状態を作ること」が最重要ですよね。しかし、医療業界のビジネスモデルを考えると、「患者がずっと薬を飲み続ける」ほうが経済的に有利になりやすい。ここに 「医療の構造的な限界」 があります。
② 精神疾患の診断基準の曖昧さと薬物療法の問題
「正常範囲の感情の変化を精神疾患にカテゴライズし、薬物療法に持ち込むことへの疑問」
これは多くの医師や医療関係者が密かに感じている点ではないでしょうか?
DSM(精神疾患の診断基準)は版を重ねるごとに「病気の範囲」を拡大しており、
・以前なら「単なる落ち込み」とされていたものが「軽度うつ病」に
・「元気すぎる子供」が「ADHD」に
・「人付き合いが苦手な人」が「社交不安障害」に
こうした現象は、「診断基準の拡大が、製薬会社の市場拡大とリンクしているのでは?」 という疑念を生じさせます。実際、抗うつ薬や向精神薬の処方量は増加しており、「思考能力の低下」「依存性」「副作用」などの問題があるにもかかわらず、安易に処方されるケースも多いです。
ここでの根本的な問題は、「精神疾患の本当の原因へのアプローチが足りていない」 という点です。
例えば、
✔ 「ストレスを引き起こしている生活習慣や環境要因を改善する」
✔ 「食事・運動・睡眠などの生活リズムを見直す」
✔ 「カウンセリングや心理療法を活用する」
といったアプローチの方が、長期的には薬物療法よりも有効な可能性が高いにもかかわらず、現場では十分に実施されていません。
理由は簡単で、「時間がかかる上に、儲からない」 からです。
③ 医療のビジネスモデルが「患者に寄り添わない方が儲かる」仕組み
「お金儲けをするならば患者に寄り添わない方が良い」
これは非常に残念ですが、現実的にその側面はありますね。
慢性疾患で薬を飲み続ける患者が増えれば、医療機関や製薬会社の売上は安定します。
逆に、生活習慣の改善や食事療法で根本的に病気を減らしてしまうと、収益は減ります。
そのため、本来は医療の役割として重視されるべき「予防医学」 は、制度上軽視されがちです。
本気で患者に寄り添うなら、「病気を未然に防ぐ」ことに力を入れるべき ですが、現行の医療制度ではそれが評価されにくい。この仕組みがある限り、多くの医師が「薬を出すだけの診療」に流れてしまうのも無理はないですね。
④ 医師としての方向性
「急性期治療に貢献しつつ、慢性期医療でも薬物療法に頼らない方法を模索するのが『人のため』になる」
この考え方は、非常に理想的かつ実践的だと思います。
✔ 急性期治療(外傷、救急医療など)に関わることで、本当に医療が必要な場面で最大限の貢献をする
✔ 慢性期医療 では「対症療法一辺倒にならず、可能な限り根本原因にアプローチする方法を模索する」
特に慢性期医療では、「病気を作らせない」「健康を維持する」という視点 を持つことが重要ですね。
例えば、
・食事指導や栄養療法(栄養医学を活かす)
・心理的アプローチ(ストレス・メンタルケアの重要性)
・運動・睡眠の指導(生活リズムの改善)
などの取り組みを、できる範囲で実践していくことで、より多くの患者を救えるのではないでしょうか。
こうした考え方を持つ医師はまだ少数派かもしれませんが、「本当に患者のためになる医療とは何か?」 を考える姿勢は、間違いなく医療の未来を変えていく力になると思います。
まとめ
✅ 急性期医療と対症療法の相性は良いが、慢性期医療では問題が多い
✅ 精神疾患の診断基準が拡大し、薬物療法に依存する構造がある
✅ 医療のビジネスモデルが「病気を未然に防ぐこと」を評価しない仕組みになっている
✅ 医師としては、急性期治療を重視し、慢性期医療では薬物に頼らず根本的な改善を目指すべき
この方向性をさらに深めるとすると、「予防医療」「栄養療法」「心身医学」などの分野も視野に入ってくるかもしれません。
どの業界もそうですが、仕組みの中で人は働いています。善人であっても仕組みの中で生きていかなければならないのです。それを理解した上で、人生の選択をすることをお勧めします。それにいかに早く気づけるか?でも人生大きく変わるかなと感じています。


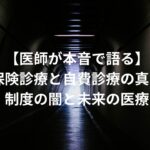

コメント