大学病院に勤務している医師です。
自分の人生を謳歌すること
自分に嘘をつかない生き方を目標に日々、精進しています。
最近、題名にもある「じょうぶな頭とかしこい体」という言葉を知りました。
どうやら、皆さんの誰もが一度は目にしたことのある特徴的な絵を描かれている「五味太郎」さんの言葉だそうです。
「じょうぶな頭とかしこい体になるために」という書籍があるようです。
普通は「かしこい頭」と「丈夫な体」だと思いますが、これは逆を言っています。
言いたいことは、心では感じ取れるのですが、言葉にしようとすると難しくてなんとも表現できません。
ただこのような言葉が生まれる背景には
教育や子どもたちが育つ環境において
子ども自身や、あるいはそれに関わる大人たちが苦しんでいるという現実
また「考え方の転換」「立ち止まって考え直すこと」を提案しているような気がします。
自分はどうだったのか??
僕自身は、自信がないことも多いですが「自己肯定感」は非常に高いです。小さい時から田舎の保育園で自由な生活を謳歌していたようです。うまくいかないことがあると所構わず・・道路でも、お店でも・・・ひっくり返り自己主張する、そんな子どもだったようです。母には「あなたは買い物には絶対連れて行かなかった」と言っています。子供に合わせて大人が対処するべきで、大人に合わせて子供を抑圧するのは良くないのではないか?と思います。もちろんTPOはあるので、スーパーには連れて行かなかったのでしょう。今、そんなことをしていれば「恥ずかしいから」という理由で怒る人が圧倒的に多いに違いありません。
でも僕はそんな子供をたまに見ると思うのです・・「今のうちだけだからな、めいいっぱい自分を表現しなさい」と。大人みたいな「ものわかりのいい」フリをさせる必要なんかありません。だって子供なんですから。
年少の時に、年長にメンコを全部取られて悔しくて大泣きし、必死に研究、練習して、ダンボール箱いっぱいのメンコを所持するまでになりました。自分の持ち物が勝負に負けると奪われるという経験もまた子供ながらに「社会の仕組み」「勝負」「弱肉強食」を学ぶいい機会でした。だから力が弱い子供のうちに喧嘩だってたくさんすればいいし、それで痛い思いもすればいい。それで「人の痛み」がわかる人間になるんです。
学生時代を振り返る
小学生の時は、放課後は下校時刻ギリギリまで校庭でずっと遊んでいました。塾などの習いごとは通わず、サッカーの少年団に入ってひたすらサッカーばかりしていました。学校の成績も中の上くらい。学校の授業は聞けばわかるし、周りより進んだ勉強をする意味も時間もありませんでした。それくらい遊び回っていました。
小学校の6年生の時の担任の先生が「自由ノート」という宿題を課す先生でした。「なんでもいいからその日に勉強したこと」を書くという宿題を与えられました。この「自由」に勉強してそれをノートにまとめるという方法が自分と相性が良く、そこから「ノートに知識をまとめる」という習慣が出来上がりました。今思えば、ここで「自主的」に「勉強」することの楽しさを知りました。この先生との出会いは自分の人生でかなり大きなターニングポイントだったかもしれません。
中学、高校という思春期
中学に入ると「科目ごとに先生が変わる」というシステムになります。ここで、どうやら中学校の先生には専門性があることに気づきます。そして学校の先生も「勉強が苦手」な人がいるということに気づきました。高校になるとこれがより顕著になります。そして体育教官らは、自分の中では「威張ってばかりいる大したことない大人」だというレッテルが貼られます。そう、「先生」と言えども「生徒」より頭の悪いやつがいることに気づきます。
そんな中、幸いだったのが、自分より頭が悪い先生でも「人間として魅力的」という理由で慕うような先生が何人かいたことと、そんな心が自分の中にあったことです。ここで気づいたのは、人間の評価は頭の良さだけでは決まらないということ、一方で、人間の良い先生でも必ずしも学校からの評価は高くない、ということです。少しばかり「世の中の理不尽」に触れるきっかけになりました。そうなると高校というものは自分の中では「ろくでもない」モノが多くなっていきます。公立高校の先生は自分の地元では「コネでなるもの」という噂がありました。それも相まって、教師のことをクソ野郎と思うようになりました。
でもどういうわけか、自分の中で思春期における「反抗の対象」は「親」「特定の教師」ではなくて「学校」という仕組みになっていました。思い返すと、特定の先生に反抗していていたのではなく、行事や集会、校則など自分にとってあまり意味の見出せないものには徹底的に反抗しました。この頃から「人物そのもの」よりも「仕組み」に違和感を感じていました。
ただ、学校は行っていました。なぜなら友達がいて、部活をしていて楽しかったからです。ただ学校の言いなりになることには非常に苦痛と違和感を感じていました。そして、学校集会などは部室でサボるようになりました。それは自分なりの「学校」に対する意思表示でした。それは幼少期の「ひっくり返って泣き叫ぶ」が形を変えて出ていると思います。同時に、自分の将来を決められるのは高校ではなく「自分だけ」だということにも気づいていました。自分の将来に責任の持てない高校に偉そうなことを言われてたまるかという反骨精神も十分に備わっていたようです。そして、普通科の高校生にとっては将来を決める最も大きな力は「学力」しかありません。だから自分は「自分のため」に勉強を頑張りました。決して学校に頼ることはありませんでした。
「部活」という貴重な学びの場
自分はサッカーを小学校1年生から習っていました。このサッカーは競技人口が多いせいか、本当に色々な人がいます。ただ学校によってはかなり「民度が低い」というのも事実。小学生の時はトレセンに選ばれていましたが、ガラの悪い小学校から来ているやつは体力任せに上手いのですが、性格は最低でした。
中学生の時は周りの実力がぐんぐん伸びることもあり、セレクションは受けに行きますが、トレセンに選ばれることはありませんでした。この時に、人によって「成長する時期」が違うんだということに気づきました。中学時代に自分をどんどんと追い越していった奴らはどうなったか?高校は中学よりも学校数が減ります。当然、サッカー部の人数も多くなるわけで、これまでチヤホヤされてきたエース級の人間が試合に出れず不貞腐れサッカー自体をやめていくなんて話もたくさん聞きました。プロにならないならば「強豪校のサブでベンチ」にいるよりも「中堅クラスでレギュラー」でいる方が上手くなることが多いと思いました。
実際に自分も高校の時に、トレセンに返り咲くことができました。それは自分が少しずつでも成長したということもありますが、上手い奴らが脱落していったという事実もありました。
そこで気づいたのは、「才能のあるやつ」よりも「続けられる努力」の方がより遠くまでたどり着くことができるということです。
学校とはなんだったのか?
今振り返れば「学校」というのは、単なる「場」です。それもルールに縛られた「場」。ここでうまく振る舞える人間もいれば居場所がなく窮屈に感じる人もいると思います。日本には学校に行くことが正義みたいな価値観があります。蔓延していると言っても過言ではありません。僕はたまたま仲間がいたから行っていました。
今、社会に出て思うのは学校の先生も医師と同じで、比較的「閉ざされた世界」で仕事をし続けている人種ということです。それのせいなのか、自分にとっては「つまらない人間」が多かったように思います。でもそれは「学校」や「教育委員会」というような仕組みが先生たちの「表現の自由」を抑圧していたのかもしれません。学校というのは学生にとって「そこしかない生き場所」のような錯覚をしがちですが、とても「不完全な場所」だと思います。うまくやっている学生たちは家庭だったり、趣味だったり、あるいは塾や習い事の仲間だったりと「学校」以外のコミュニティで「自分の居場所と世界」をしっかりと持てていると思います。大事なのはむしろそれだと思います。
そんなこんなで学校では常に疑問を感じていました。目の前にいる教師は尊敬に値するのか?自分より優れた人間なのか?生意気ですが、そんなことを考えながら生活していました。それでも毎日のように学校に行くのは居場所を見つける努力をしたからかもしれませんし、色々と「仕組み」を考えながら「自分らしく」ありながらその場を堪える「じょうぶな頭とかしこい体」があったからなのかもしれません。ひょっとしてゲーム感覚でその違和感を楽しんでいたのかもしれません。
そして源は「道路にひっくり返っていた頃」に僕の母親が「僕らしさ」を潰さずに、それを許してくれたから「失うことなく成長した」のだと思っています。
子供ながらに今、思う親の教育方針とは
では、親になった僕からみて、自分の両親の教育方針の軸は一体なんだったのか?
大事な要素は2つあると思います。
一つは、僕自身が「思春期の反抗対象は親よりも学校であったこと」→親は味方であると感じていたこと
2つ目は、「ひっくり返り泣き叫ぶ幼少期」を受け入れてくれたのことだと思います。
つまり「その年齢に必要なアクションを需要する」と言う親の態度の積み重ねは「自分で行動する」という経験をたくさんさせてもらいました。日常の何気ない行動であっても子供にとっては非常に重要な経験だと思います。悪い意味で抑圧されていない子供は、そのアクションやリアクションに対して自身で反省し段々とその行動に責任を持つようになると思います。そうして段々と自身の行動がどのような影響を与え、自分がどう振る舞うべきか?わかるようになると思います。
そして、親が味方である後ろ盾は、学校や社会で戦うための余計な「不安」を取り除けます。「家」と言うのは安心して帰って来れる場所であるべきだと思います。子供達は家から一歩出れば、色々なものと戦っていかなければなりません。家は空母のような存在である必要があると思います。
子供が自分で考えることのできる年齢になった時にどれだけ「味方」になってあげられるか、同じ目線で悩み考えることができるのか。そんなことを意識したいと思います。知識を教えることも大事ですが、「不完全な世の中」で生きるていることを自覚し、どれだけ良くする方向に考えられるか、を一緒に考えられる存在になるべきなのかもしれません。
昔、何かの本で読みましたが
これから自分より長く生き、多くを学ぶことのできる子供達の方が「魂のレベルは高い」と聞いたことがあります。具体的にはなんとも言えませんが、なんとなく腑に落ちるような気がします。
生きる力とは
生きる力とは、「人生を自分のモノにする力のこと」だと思います。
自分の人生は自分できめる。
これが大原則です。
そしてこれができている大人がどれほどいるのでしょうか?
他人との比較で悩んだり、他人の意見を聞くほど人生は長くはありません。
悩み抜いて考えた結論を信じて行動できる自己肯定感
それが人生において「小さい頃に大事にすべきもの」ではないでしょうか?
僕は「苦手な人」はいますが、「嫌いな人」はほとんどいません。
なぜならば「自分を気に入っている」からです。
見た目でも、性格でもなく、自分に正直に生きているからです。
自分の生き方が「気に入っている」からです。
自分の生き方が「気に入らない人」も多いのではないでしょうか?
それはどうしてですか?
つまらない仕事をしているから?ではそれはどうしてつまらないのか?
他人の評価に生きているからではありませんか
自分に正直に生きていないからではないですか
そして自分に正直であることは、自分勝手というわけでもありません
もっともっとレベルの高い話だと感じています。
僕自身がそんな思いを育めたのは小さい頃ののびのびとした環境にあったのかもしれません
あの頃に育った「じょうぶな頭とかしこい体」が「自分に正直に生きる力」を与えてくれたのだと思っています。
この文章も自己肯定感の塊みたいな文章ですよね。
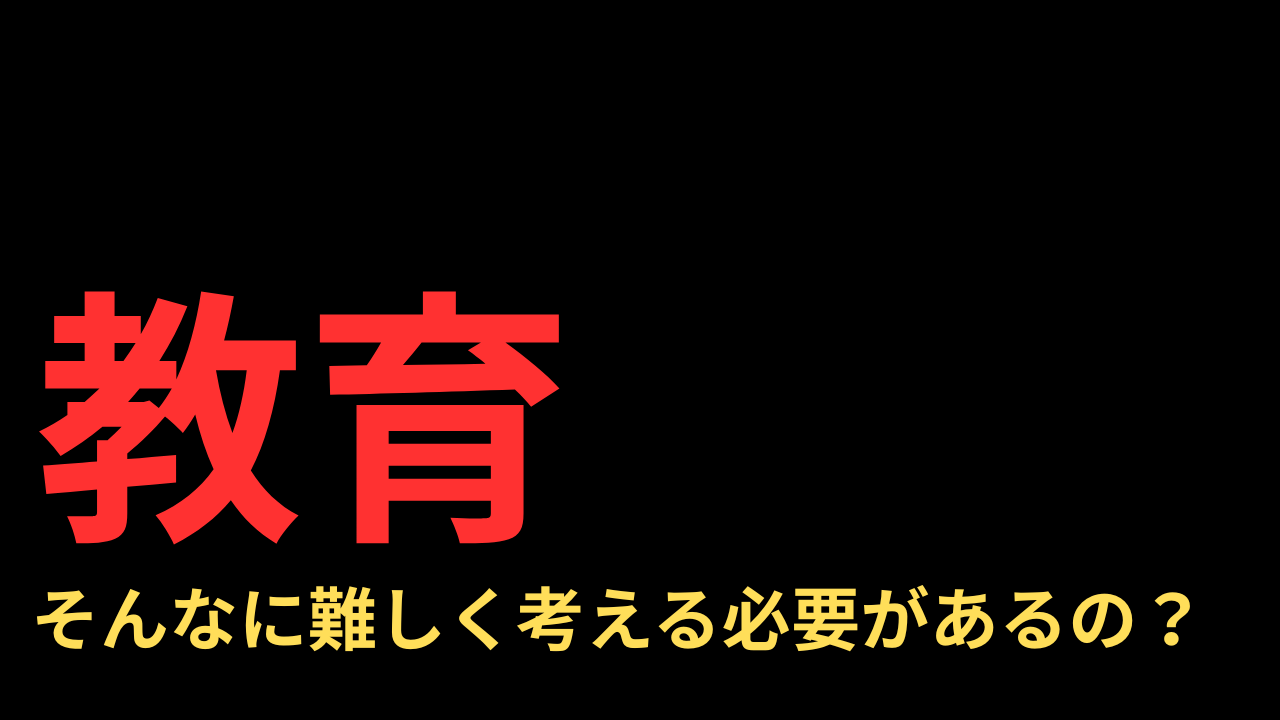

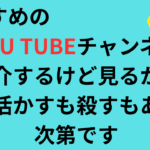
コメント