本質を考える医師です
戦後に日本人に増えた病気と減った病気があると思います。印象として減った病気は感染症や事故による怪我など社会環境の整備によるものが主だと思います、一方で、増えた病気はがん、アレルギー、認知症などの神経疾患などです。これらは高齢化が一つの要因として挙げられますが、アレルギー性疾患などは高齢化とは関係ありません。食を取り巻く環境が大きく変化していることだと思います。それは添加物などもそうですが、精製された糖や小麦などこれまでの日本人があまり口にしてこなかった食事が原因であると考えています。
戦後の日本で増減した病気の背景には、社会環境や医療の発展だけでなく、食生活の変化が大きく関わっていると思います。
減った病気
戦後の公衆衛生の向上により、結核、寄生虫感染症、食中毒、赤痢、コレラなどの感染症が大幅に減りました。また、交通整備や安全基準の向上により事故による死亡率も下がっています。
増えた病気
一方で、がん、アレルギー、自己免疫疾患、糖尿病、心血管疾患、認知症などが増えました。高齢化の影響もありますが、それだけでは説明できない部分も多いです。
特にアレルギー疾患や自己免疫疾患の増加については、食の変化が大きく関わっていると考えられます。
食環境の変化が与えた影響
- 精製された糖や小麦の普及
- 白砂糖やブドウ糖果糖液糖など、血糖値を急激に上げる食品の摂取が増えた。
- 精製された小麦(グルテン)による腸内環境の変化がアレルギーや炎症性疾患の増加に関連。
- 添加物や保存料の増加
- 加工食品に含まれる防腐剤、乳化剤、人工甘味料が腸内細菌叢(マイクロバイオーム)に影響を与え、免疫システムを狂わせる。
- オメガ6系脂肪酸の過剰摂取
- 戦後、植物油(サラダ油、大豆油、コーン油)の使用が増え、炎症を引き起こす脂肪酸の摂取量が急増。
- これにより慢性炎症が引き起こされ、アレルギーや自己免疫疾患の増加につながる。
- 食物繊維の摂取量の減少
- 戦前の食事では発酵食品や野菜が豊富だったが、現代は加工食品中心となり、腸内環境が悪化。
- これにより、免疫バランスが崩れアレルギー疾患の増加につながる。
- 乳製品の普及
- 戦後、欧米型の食生活が広まり、日本人がもともとあまり摂取してこなかった乳製品が増加。
- 乳タンパク(カゼイン)や乳糖が消化しにくい人も多く、腸の炎症を引き起こす可能性がある。
今後の対策
このような状況を考えると、今後日本人の健康を維持するためには、伝統的な和食を見直し、腸内環境を整える食生活を意識することが重要です。
特に、発酵食品・食物繊維・良質な脂肪(オメガ3系)を意識することが、アレルギーや慢性疾患の予防につながるはずです。
生活が進歩して「ととのう」ようで、我々の昔ながらの良き生活スタイル、食文化はむしろ「破壊」されてきていると感じています。
その影響は今を生きる我々の健康上生じているさまざまな問題が「答え」だと思っています



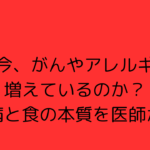
コメント