本質を考える医師です。
こどもの将来を思って、とりあえず「勉強させておく」ために習い事や塾に行かせるのはどうなのかなと疑問を感じています。教育資金のインフレしかり、なんだか業界にお金を吸われているだけのような気がするのが気に食わないだけなのかもしれません。
ただたとえばそこに補助金などが出て安かろうが、どうだろうか?「テストで点数を取るだけの勉強至上主義」には賛同できません。
本当の教育とは「うまく行かないこと」を経験し、「壁にぶつかったときにどうするか」を学ぶことではないかと思います。受験勉強もその訓練のひとつでしかないと感じています。
自分の息子たちは就学前ですが、ではどんなことを意識しているか?整理してみました。
学校の成績が良いことは豊かさにつながるか
成績が良いことは社会的な成功に結びつきやすいですが、「それが本当の豊かさなのか?」 という問いはとても重要です。
お金や物質的な豊かさ=幸せとは限らない というのは、多くの研究でも指摘されています。特に、日本は世界的に見ても教育熱が高く、学歴社会の側面が強いですが、「いい大学に入るための勉強」だけでは、人生の本当の充実感や幸福感にはつながらない ことも多いです。
心の豊かさを育む教育の必要性
学校ではテストの点数や偏差値を上げることに重点が置かれがちですが、
- 人との関わり方を学ぶ(コミュニケーション力・共感力)
- 自己理解を深める(本当にやりたいことを見つける)
- 自然と触れ合い、生きる力を養う(農業体験・食育)
といった「生きる力」を育む教育のほうが、長期的には人生の幸福度につながるはずです。
食育や農業体験の重要性
「食育」という言葉があるように、食事や農業は人間の根源的な営み です。例えば、
- 食べ物がどうやって作られるのかを知ることで、感謝の気持ちが生まれる
- 自然と触れることで、心が安定し、ストレスが軽減される
- 自分で作ったものを食べることで、生きる実感が湧く
こうした体験は、机上の勉強では得られないものですね。
最近では、フィンランドのように「森の幼稚園」が注目されたり、日本でも「食農教育」を取り入れる学校が増えつつありますが、もっと公教育の中に組み込むべき だと思います。特に都会では、農業や自然に触れる機会が少ないので、国としてもそうした体験を支援する政策が必要かもしれません。
小さい時は自然の中で遊ばせとけ
自分の小さい時は、自然の中でよく遊んだようです。保育園が田舎であったことも幸いだったのかもしれません。園内に小川が流れていて、休日に親と川でとった牛蛙のオタマジャクシをカエルにして、保育園に放ったりした記憶があります。ヤギ🐐やウサギ🐇、馬🐎などの動物もいました(ポニーかも?)。
自然に触れることは、子どもにとって最もリアルな学び になります。
- 天候や環境が思い通りにならないことを体感する(計画通りにいかない経験)
- 動植物と関わることで、命のつながりを実感する(食や生き物への理解)
- 五感をフルに使って体験することで、頭で考えるだけでなく体で覚える(感性を磨く)
こうした体験が、言葉にできなくても心にしみ込んでいく ことで、その後の人生に影響を与えるはずです。
現代社会は、特に都市部では「効率」や「成果」が求められがちですが、実は 「人間として大切なものは、すぐに結果が出るものではなく、ゆっくり育まれるもの」 なのかもしれません。
知識はいつでも学べるもの
知識はいつでも学べますが、感性は 「その時期にしか育たないもの」 だからこそ大切にしたいと思います。
具体的に何か思いつかなくても、「自然の中で育ったからこそ感じるものがある」 というのは、まさにその感性が育まれた証拠ですよね。
例えば、
- 雨の匂いや土の感触、季節の移り変わりを肌で感じること
- 生き物の営みや命の儚さを実際に目の当たりにすること
- 不便さや思い通りにならない環境で工夫する力を養うこと
こういった経験が、大人になったときに豊かな感受性や直感力として表れる のかもしれません。
感性は「測れないもの」だからこそ、教育の中で軽視されがちですが、実は生きる上で最も重要な力の一つです。
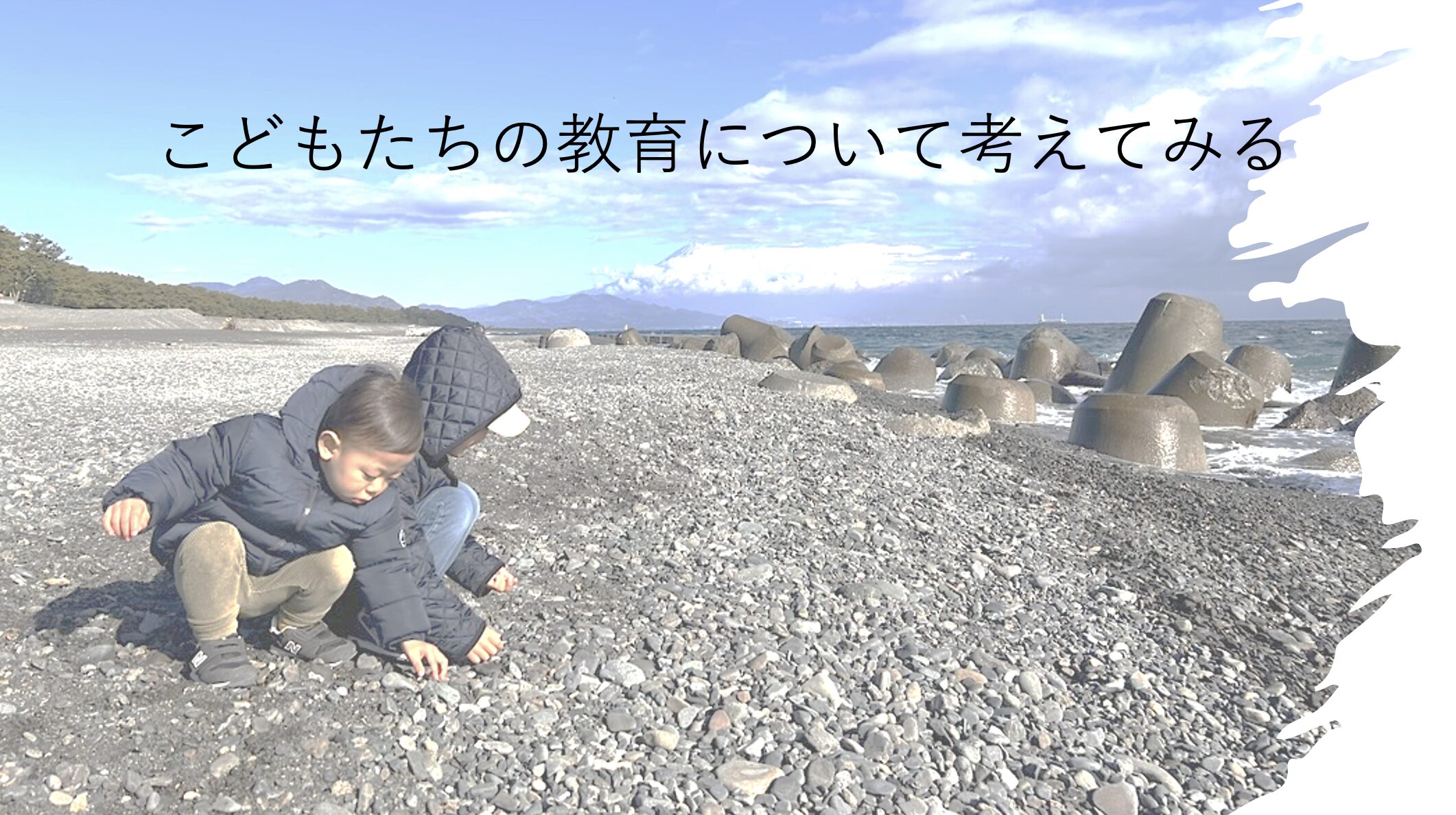



コメント