本質を考える医師です
「もしあなたが世界の裏の支配者だとしたらシリーズ」で少しだけ取り上げた「教育」をテーマに深掘りします。
「教育」というツールも大衆をコントロールする上では非常に重要な要素となります
自分で考えない、従順な大衆を完成させておくことがメディアを含めて人を管理する上では大事なことだと考えます。そんな陰謀論的な思いをベースに抱いているのですが、それを踏まえながら「教育」というものの本質をぶった斬っていこうと思います。
「教育」のそもそも論
「子どもを育てる」と聞くと、多くの人は“何かを教え、正しく導くこと”だと考えるかもしれません。何かを教え導くことと聞くと宗教みたいですが、でも本当に大切なのは、子どもが自ら育つ力を信じ、そっと見守ることではないかと感じています。
親の視点では「そうすると絶対失敗するから」と言って口を挟みがちです。「見守る」ということは大人にとって試練だと思います。ただ我々は「子育ち」を通して、大人であることを学ばなければなりません。
そして「聞き分けが良くて、おとなしい子」が「良い子」ではないと思います。親の責任で暴れられるうちにいっぱい暴れて怒られて学ぶしかありません。親は、どこかで線引きを持って「怒る」(一貫性を持った態度である)ことが大事だと思います。
子供は思っている以上に「親の態度」を観察しています。
子供を「教育」する前に自身の「態度」に一貫性があるか見直してみてください。
この記事では、「教育とは何か」「思考する力を育てる子育て」「順応と個性のバランス」について、私自身の考えをもとにお話しします。
教育とは「教えること」ではなく、「育つ力を支えること」
教育や子育ては、ここ100年で急に生まれた概念ではありません。人類の歴史の中で、数え切れないほどの親や大人たちが試行錯誤しながら受け継いできた営みです。
現代では「教育学」として体系化され、専門家による研究が進んでいます。しかし、特定の事例を切り取って解析するその姿勢は、あくまで参考程度に捉えるべきものだと私は思います。
私が大切にしている考えは、**「子どもは自ら育つ存在であり、親はその成長を見守る存在」**であるということです。
子育ての本質は、愛情を注ぎ“見守ること”
ネイティブアメリカンに伝わる「子育て四訓」は、子どもの成長段階に応じた親の関わり方を示した教えです。
この教えは、以下のように表現されています:
- 乳児は肌を離すな
- 幼児は肌を離して手を離すな
- 少年は手を離して目を離すな
- 青年は目を離して心を離すな
この教えは、子どもの成長に伴い、親がどのように関わるべきかを示しています。乳児期は肌のぬくもりを通じて愛情を伝え、幼児期は手をつなぎながらも自立を促し、少年期は見守りながらも自由を尊重し、青年期には心のつながりを大切にすることが求められます。
この「子育て四訓」は、ネイティブアメリカンの伝統的な子育て観を象徴する教えとして、多くの育児書や教育関連の書籍で紹介されています。例えば、加藤諦三氏とドロシー・ロー・ノルト氏による『子供を伸ばす魔法の11カ条 アメリカインディアンの教え』では、この教えを含むネイティブアメリカンの子育ての知恵が紹介されています。
この言葉は、子育ての本質を端的に表しています。**大切なのは、技術でもノウハウでもなく、子どもに対する“愛情”と“つながり”**です。
知識やスキルを無理に教え込むより、子どもの成長する力を信じ、安心して育つ環境を整えてあげることこそが、最も大切な親の役割ではないでしょうか。
現代教育と“思考しない順応”の危うさ
現代社会では、「他人と違わないこと」「順応すること」が求められがちです。
これは、そもそもそう言ったことを良しとする社会の風潮を作り上げられた、と思う節もありますし、日本人の習性としてそうなのかもしれません。ただ本当は日本人はもともと民主主義が導入されていない時代は全会一致の文化であったと聞きます。「和して同せず」とう言葉があるように(孔子ですが)、本来であれば全会一致するまで、とことん議論をして決めていくというのが本質的な日本人の習性なのかもしれないと思っています。
順応すること・・・その結果、「考えること」や「個性を大切にすること」が軽視されているように感じます。人と違うことを恐れるあまり、思考を止めてしまっている人も少なくありません。
メディアを通じた意見の誘導、
空気に流される多数派心理、
声を上げる人へのレッテル貼り
……こうした社会の仕組みは、“順応しているだけの思考停止状態”を量産しているようにも見えます。
思考する力を育てることが、優しい社会をつくる
「順応」は決して悪いことではありません。社会をうまく保つためには必要な一面もあります。
しかし大事なのは、**“思考した上での順応”**です。
自分の頭で考える力があれば、他者を理解しようとする姿勢も自然と育ちます。多様性を受け入れる社会は、そうした“思考する力”から生まれてくるものだと私は信じています。
多様性は法律で定められているから認めるものではなくて、他者を敬うという考えから自然に出てくる「寛容性」なのではないでしょうか
逆に、思考しない順応が蔓延すると、「違い=悪」として攻撃する風潮が生まれてしまう。それこそが、社会を乱す大きな要因になるのではないでしょうか。
【まとめ:子どもに必要なのは、思考する力と見守られる安心感】
教育とは、「教え込むこと」ではなく「その子が自ら育つ力を支えること」。
今こそ、「順応」よりも「思考する力」を育てる教育や子育てが、必要とされているように感じます。
愛情と信頼をもって、子どもを見守ること。それが、未来を生きる力を持った子どもを育てる一番の近道ではないでしょうか。


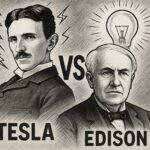

コメント